NewsNewsみんなの障がいニュース
みんなの障がいニュースは、最新の障がいに関する話題や時事ニュースを、
コラム形式でわかりやすくお届けします。

- 寄稿
障がい者プロゲーマーによる【こしづかラジオ】夏休みの思い出/越塚プロがやってみたいゲームは??
【こしづかラジオ】夏休みの思い出・越塚プロがやってみたいゲームは??
みんなの障がい運営会社「株式会社ワンライフ」より、ワンライフ所属、eスポーツプロ選手の越塚さんによるラジオをお送りしています。
今回、ラジオを文字起こししました。「凸凹村」コンシェルジュの町田と、eスポーツプロ選手の越塚さんのeスポーツプロプレイヤーになるまでの道のり、プロゲーマーの活動や日常について語ります!
こしづかラジオ・メインパーソナリティー越塚さんとは?
2021年5月1日より、株式会社ワンライフとプロ契約を結んでいる、越塚竜也選手です。越塚選手は筋力が低下していく「筋ジストロフィー」という障がいと向き合いながら、いくつもの大会に出場してきました。eスポーツ選手としての活動とともに、ワンライフが運営している生活介護事業所「iba-sho」を利用し、日々練習に打ち込こんでいます。
■氏名:越塚竜也(こしづか りゅうや)■生年月日:1988年2月24日■年齢:33歳■出身地:群馬県みどり市■障がい:筋ジストロフィー※息や口の動きで操作するコントローラーや机に置く大きなボタンを使いプレー
トークテーマ【夏休みの思い出】
越塚:海には子供の時結構いってましたね。群馬には海がないんで、海を見ると
テンションが上がりますよね。見るだけでもすごい楽しいなって。
あとは茨城の方に障がい者でも海に入れるところがあってそこにも結構行ってましたね。
町田:障がいがあっても海を楽しめるのはいいですね!
越塚:そうですね。障がいを持ってるとなかなか海に入ることできなかったりするんで、諦めたりしちゃうんですよね。
でもそうやって障がいがあっても普通の人と同じことができるので心に残ってます。
越塚プロのおすすめコンテンツ
越塚:自分、アニメ見るの好きなのでアニメをよく見るんですよ。それで今ちょうどワンピースでルフィが新しいギアを出して盛り上がってるところなので、今おすすめかなって思ってます!
町田:新しいギアっていうのはどういうギアなんですか?
越塚:コミカル的な面白い動きをしたりとかっていう感じのギアですね。
町田:そうなんですね!私はまだ途中までしか見てないのでギアセカンドまでしか知らなくて……ちなみそれは何番目のギアなんですか?
越塚:5thですね。
町田:あ、もうそんなに、かなり増えてますね、笑
越塚:笑。最近のアニメはクオリティや迫力が凄くて、映画を観ている気分になるのですごくおすすめですよ!
こしづかQ&Aコーナー
Q:eスポーツ選手を目指そうと思ったきっかけは何ですか?
A:元々ゲームが好きだったのもあるんですけど、病気があるのでやっぱりなかなか普通に仕事したりとかができなくて……。
仕事したいなとは思っていて、これ(eスポーツ選手)ならできるかなと思って挑戦しました。
Q:一番最初にやったゲームって何ですか?
A:一番最初にやったゲームは「リーグ・オブ・レジェンド」ですね。
よく使っているキャラは「アッシュ」という遠距離から攻撃するキャラです。
ファイターなど他にもキャラは沢山いるんですが、口で操作するには動きが早いので 「アッシュ」をよく使っています。
Q:今後チャレンジしたいゲームはありますか?
A:そうですね……色々あるんですけど、APEXとかフォートナイトとか、人気のあるゲームをやってみたいなって思いますね!PS5のゲームも気になってます!
越塚プロに聞いてみたいことや、
こんな企画をしてほしいなどありましたら
凸凹村やYoutubeなどにコメントください!
■最後に
障がいといっても、⼗⼈⼗⾊。その組み合わせで、⾯⽩い科学反応がきっと起きる。
障がい者が障がい者の課題解決を⾏う新しいコミュニティ『凸凹村』。
今後、村長の乙武洋匡さんが参加するイベントや企画も計画していますので
ぜひご参加下さい!
【凸凹村Facebookグループ】
・総合:どの障がいをお持ちでもOK!
※以下のグループに参加する方は「総合」への参加が必須です
・精神障害
・身体障害
・知的障害
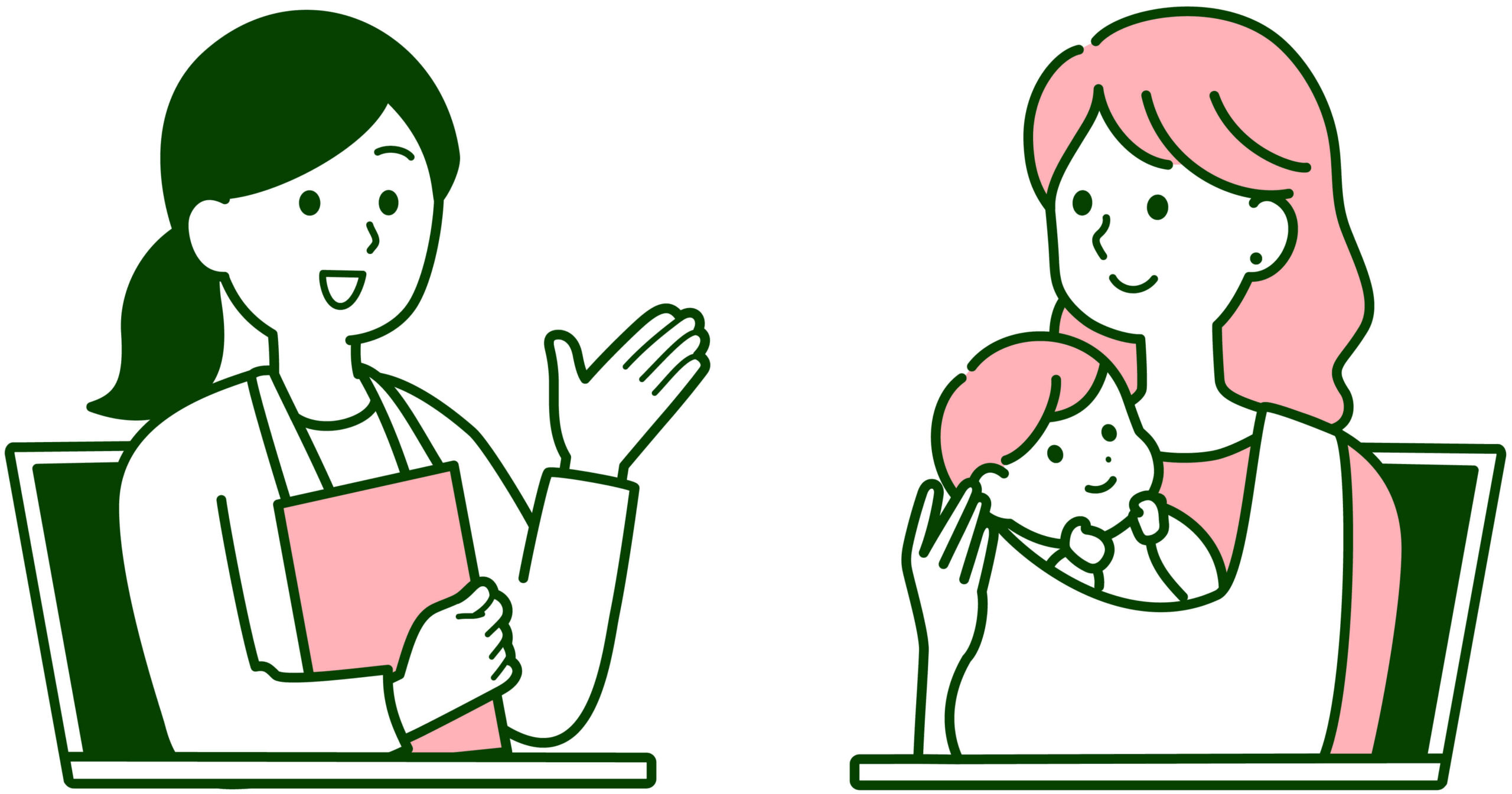
発達障がいのある子の子育てに悩んだら相談を。経験しているからこそ共感できる「ペアレントメンター」とは
発達障がいのある子の子育てに悩んだら相談を。経験しているからこそ共感できる「ペアレントメンター」とは
発達障がいのお子さまの子育ての悩みは「自分のところだけかもしれない」と思いがちで、なかなか周りに相談しにくいですね。まわりには共感してもらえそうにないと感じて、ひとり悩みを抱えていませんか?
子育てノイローゼになったり、子育てがツラくなったりする前に、「ペアレントメンター」を頼りましょう。ペアレントメンターの役割や特徴、活動、相談ができる場所をご紹介します。
ペアレントメンターの役割や特長は?
ペアレントメンターとは、発達障がいのお子さまの子育てを経験しており、相談支援機関により講習を受けた方のことです。ご家族の相談を受けるだけでなく、啓発イベントなどで講義をおこなったり、福祉施設の職員研修で保護者の気持ちをお伝えしたりしています。
ペアレントメンターはどのような講習を受けているのか、ペアレントメンターの役割や特徴について見ていきましょう。
ペアレントメンターは発達障がい児の子育て経験者かつ研修の受講者
ペアレントメンターは、発達障がい児の子育て経験があり、親の会などに入っていることがひとつの条件となっています。そして、地域ごとに開催されている「ペアレントメンター養成研修」を受講することで、ペアレントメンターとして活動できるようになります。
研修の内容は、
ペアレントメンターの目的や守秘義務などの倫理観
発達障がいについての基礎知識
その地域の発達障がい支援機関についての情報
相談支援の方法や相談のロールプレイ
などです。
発達障がいのお子さまをもつご家族の相談を受けたり、支援したりするために必要な知識と経験をしっかりもっているため、安心して頼ることができます。
共感的なサポートで孤独感をへらせる
ペアレントメンターは、すべてが不安な乳幼児期から、支援学級は何が違うのか・学校ではどのように対応してもらえるのかという就学に向けての相談や、友達との関係性や就労などの将来についての悩みなど、さまざまな相談を受けています。
医療機関などの専門家とは違い、子育ての悩みに本当の「わかる!」という共感をもらえたり、「本当にそういうことがあるよね」と経験者同士だからこそ、より共感し合えます。「誰にもわかってもらえない…」「こんなこと、周りに話せない」「こんな経験をしているのは自分だけかもしれない」という子育ての孤独感をへらせます。
さらに、実際に利用したことのある福祉サービスの情報や体験談も聞けるので、子育てのひとつの不安を解消できるでしょう。
ペアレントメンターに相談したいときは?
ひとりで抱え込まず、子育ての悩みをペアレントメンターに相談してみてはいかがでしょうか。
現在、ペアレント・メンター活動は、全国の自治体に広がるとともに、発達障がいだけではなく、他の障がいのサポートにも広まってきています。
ペアレントメンターに相談できる場所
ペアレントメンターへ相談できる場所は、一例として以下の機関があります。
市区町村の福祉課
発達障がい者支援センター
児童発達支援センター
発達障がい者親の会 など
※自治体によって名称が異なることがあります。
こども園や学校、障がい児通所施設での茶話会へペアレントメンターの派遣を行っている団体もあります。
ただ、地域によってはペアレントメンター事業がなかったり、メンターが在籍していなかったりする場合もあるので、市区町村の福祉課へお問い合わせください。
さまざまなペアレントメンターさんと話しましょう
経験者であり豊富な知識や情報を持っているペアレントメンターですが、医療機関などの専門家ではありません。発達障がいも人それぞれ個性があるため、ペアレントメンターのアドバイスがすべて自分の子どもにあてはまるとも限りません。
すべて正解だと思い込まず、さまざまなメンターさんとお話をしたり、ペアレントメンターからのアドバイスや情報を実際に自分で確かめてみることも大切です。
まとめ
発達障がいのある子の子育てについて、現在も将来も不安が大きいけれど、まわりに相談しにくいですね。子育てが本当にツラくなる前に、同じような悩みを抱えていたペアレントメンターに相談してみましょう。こんな時はどうしたらいいのかというアドバイスだけでなく、活用できる福祉サービスなどの情報も得られます。ペアレントメンターは守秘義務など相談支援の研修を受けているため、安心してご相談してみてはいかがでしょうか。
近くの児童発達支援事業所・放課後等デイサービスをお探しの方はこちら
参考
平成30年度障害者総合福祉推進事業 ペアレント・メンターガイドブック
ペアレント・メンターとは | 日本ペアレント・メンター研究会

【参加レポ】インクルーシブパレード「障がいがあってもなくても、友達になろう。」
【参加レポ】インクルーシブパレード「障がいがあってもなくても、友達になろう。」
みなさんこんにちは!ワンライフの町田です。
11月11日(土)インクルーシブパレードに参加してきました!
インクルーシブパレードとは?
インクルーシブパレードは障がいを持つ人々のためだけのイベントではなく、インクルーシブな社会づくりへのアンテナを立てる取り組みです。インクルーシブとは「包括的な」という意味があり、障がいの有無にかかわらず、みんなで社会を築いていこうという意味があります。
合言葉は「障がいがあってもなくても、友達になろう。」
障がいを持った人とそうではない人が、大声で笑いあって友達になっていく……
このインクルーシブパレードで、さまざまな人と触れ合い、協力することで、今まで感じたことがない何かに気づくことができると思います。日常や仕事、プライベートの関係性まで変化していく可能性をもっているイベントです。
今年は<みる>にフォーカス!
「見えない世界はどんな感じだろう」と考えたことはありますか?
目の見えない方々は目ではなく、目以外の感覚でたくさんのことを「みて」います。
今年のインクルーシブパレードは、「みる」がテーマでした。
目の見えない方々と同じように、目以外の感覚に注意して「みる」ブラインドサッカーやブラインドラグビー、伴走体験など、様々なブラインド体験会もイベント会場で開かれていました。
インクルーシブパレードで「仲間外れにしない、みんないっしょに」を感じられました。
私はADHDの特性があります。この関係で人込みや遠征が苦手なため、インクルーシブパレードのような大規模なイベントへの参加に緊張していました。けれど、凸凹村で知り合った方々や、当日初めましての方々もとても暖かく気さくに話しかけてくださり、肌で「インクルーシブ:仲間はずれにしない、みんないっしょに」を感じることができるとてもいい1日になりました!
凸凹村に興味を持ってくださった方、当日入村くださった方々も本当にありがとうございました。
色々な方の色々な意見や、課題に感じていることなども伺うことができ、新しい視点も得ることができました。
次回開催はみなさんぜひ一緒に参加しましょう!
世の中知らないことだらけ……でも外に出て色々な人と話せば、知らないことも知ることができるし、今まで気づけなかったことにも気づけますね。
みなさん、次回開催される時にはぜひ一緒に参加しましょう!
今回のイベントの写真や動画などは、
この後凸凹村内や凸凹村各SNSでも掲載予定ですので
気になる方はぜひ凸凹村へご参加、フォローください!
凸凹村
凸凹村 X(Twitter)
凸凹村 Instagram
凸凹村 TikTok
取材者:町田
取材協力:インクルーシブパレード
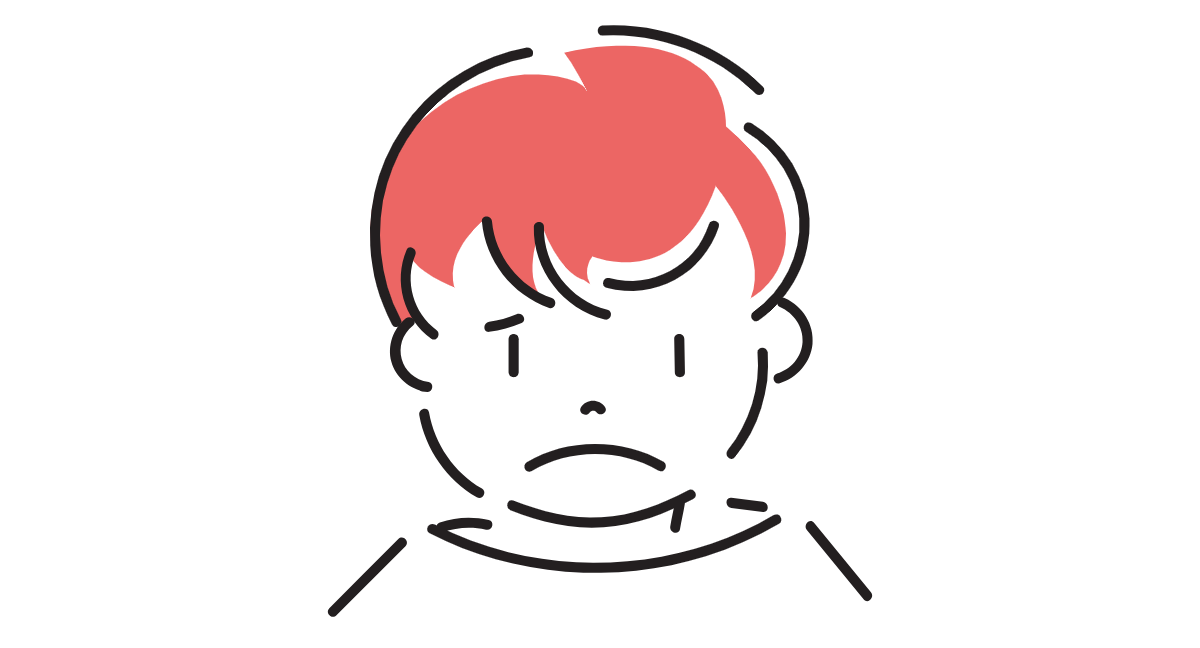
- コラム
ASD・ADHDの私から。「まずは行動してみよう」
初めまして。年齢は39。障がいはASD(自閉スペクトラム症)とADHD(注意欠陥多動性障害)です。
私は1984年2月28日にこの世に生を受けました。子供の頃、楽しかった記憶はありません。両親からの厳しすぎるしつけゆえに声優の夢を否定されたり、小中高のいじめ、今までたくさん辛かったことを乗り越えてきました。時には死を考えたりもしましたが、私にはゲームという友達がいたから踏ん張ってこれました。
けれど、ずっと親に「長男なんだから我慢しろ」と言い聞かせられ、我慢に我慢をかさね、忍耐に忍耐を重ねた結果、24歳の時、突然なにも手が付かなくなりました。仕事も行きたくない、ご飯を食べるのもめんどくさい、風呂もトイレも…。
そんなとき支えてくれたのはやっぱりゲームだったんですね。これさえあれば、とそんな気持ちになりました。その当時、ほぼ毎日24時間ほどゲームをしていたと思います。私は今、就労継続施設B型事業所ONEMGAMEでeスポーツに携わる仕事をしています。ここにこれたおかげで今、私は生きる活力を少しもらっていると思います。
障がいがあるからと、何もかもあきらめてしまっている人。私は障がいや家族や友達のせいにして動かなかった時もありましたが、満たされない日々でした。あのまま本当に何もしなかったら、このONEGAMEを知らないまま、いろんなことのせいにして毎日過ごすところでした。
だから、私は無理とかどうせ変われないと思っている人!まずは動いてみてほしいです。ちょっとでも自分の中で興味がある事があれば、積極的に!変わらないかもしれないけど動いてみる事が大事だと思ってます。私も動きだしてから、まわりの事が変わりました。ONEGAMEに通っていて、人間関係も変わりました。良い方向でよかったと思うのですが、悪い事もあるかもしれないです。けれど、動かないと本当に何も始まらないな、と今は感じてます。
面倒だと思うかもしれないけど、(私は思ったことがありました)まずは小さなことでも始めてみてほしいです!
\ みんなの障がい運営!障がいの悩みを共有したり解決し合えるコミュニティ「凸凹村」参加はこちら/
同じ障がいをもつ人と話せる安心コミュニティ「凸凹村」

【取材レポとインタビュー】埼玉県卓球バレー協会 取材レポと会長の山田幸司さんにインタビュー!
みなさんこんにちは!ワンライフの町田です。
11月9日(水)埼玉県卓球バレー協会さんの練習会にお邪魔してきました!
1つの卓球台を大人数で囲む姿は、見るだけでもワクワクしますね!
卓球バレーは障がいのある人、高齢者、子ども…誰もが一緒にできるスポーツ
卓球バレーは6:6で卓球台を囲んで椅子に座って、ピンポン球を3回以内でネットの下を通過させ相手に返すゲームです。バレーボールと卓球が組み合わさったようなスポーツです。
ピンポン球には鉛が入っていて「カラコロ」と音が鳴るので、視覚障がいがある方も一緒に卓球バレーを楽しむことができます!
写真だと伝わりづらいのですが、実際目の前で試合をみてビックリ!
球もみなさんの反応も試合の展開も早くて、気付いた時には点が入っています!!
町田も実際に体験させていただきましたが、凄い勢いで来る球になかなか反応できず、差し出している板に偶然当たって、やっと跳ね返せるという場面が多かったです。
この迫力と楽しさは体験してみないと伝わらない部分が大きいので、ぜひ!
気になりましたらお近くの卓球バレー協会にお問い合わせのうえ、参加してみてください!
卓球バレー協会にぜひお問い合わせください!
卓球バレー協会は各都道府県ごとに協会があります。とはいっても、活動人数が少なく、卓球バレー協会がない都道府県もあります。
今は卓球バレー協会がない都道府県にも、これから協会ができるよう凸凹村としても協力していきたいと思っていますので、もし卓球バレーに興味をもってくださった方は、ぜひ最寄りの卓球バレー協会にお問い合わせください。
埼玉県卓球バレー協会 代表理事の山田さんインタビュー
埼玉県卓球バレー協会 代表理事の山田さんにインタビューをさせていただきました!
Q1.埼玉県卓球バレー協会は主にどのような活動をしていますか?
埼玉県卓球バレー協会は卓球バレーのルールに基づいて、毎週水曜日13時~16時まで、春日部市中央公民館で主に練習をしております。
Q2.埼玉県卓球バレー協会の今後の課題と展望を教えてください。
コロナ禍により昨年度まで様々な事業を中止しており、今年度から各事業を開催し始めました。我々の一番の課題は、このコロナ禍で減少してしまった卓球バレーの会員を今年度から増やし、多くの方に体験してもらうということです。
Q3.今後のイベントや活動の予定はありますか?
今年度は以下の教室やイベント参加の予定があります。
県外の方でも参加できますので、皆様お誘いあわせのうえぜひご参加ください!
まずは卓球バレーに触れていただき、楽しさを感じてもらえたら嬉しいです。
■埼玉県卓球バレー協会 問い合わせ先
048-752-3476(埼玉県卓球バレー協会)
■12月10日(土)10時~15時:市民のつどい
■12月16日(土)14時~16時:障害者卓球バレー教室
■令和6年3月10日(日)10時~15時半:卓球バレー指導者・3級審判員養成講習会
今回の写真やインタビュー動画などは、この後凸凹村内や凸凹村各SNSでも掲載予定です!
気になる方はぜひ凸凹村へご参加、フォローください!
凸凹村
凸凹村 X(Twitter)
凸凹村 Instagram
凸凹村 TikTok
取材者:町田
取材協力:埼玉県卓球バレー協会
関連リンク:日本卓球バレー協会

リズムに合わせて楽しくこころも体も発達♪障がい児がリトミックをすると良いことは?
リズムに合わせて楽しくこころも体も発達♪障がい児がリトミックをすると良いことは?
保育園や幼稚園、学校、障がい者や高齢者施設など、様々な場所で取り入れられ、日本だけでなく世界でも広まっている「リトミック」。その目的や、期待できる効果、実際にどこで体験できるかについてご紹介します!
リトミックの目的とその効果
なんとなく音楽的なものというイメージを持っている方も多いと思いでしょう。リトミックは実際にどのような目的を持ってできたものなのか、その効果はどのようなものなのでしょうか。
リトミックとは音楽をつかった療育
リトミックはスイスの作曲家、音楽教師だったエミール・ジャック=ダルクローズが考案した教育法です。音楽に合わせて体を動かすことで、身体や音楽的な感覚だけでなく、集中力、想像力など、様々な発達を促すことを目的としています。
日本では大正14年に初めて小林宗作が幼稚園、学校でおこなったとされています。
リトミックの三本柱
リトミックは「リズム」「ソルフェージュ」「即興」の3つから構成されています。
「リズム」
音楽を聞いて音の強弱や高低などに合わせて体を動かすことで、聴覚や集中力、自発性、表現力などに働きかけたり、リズム感覚を身に着けるものです。
ゆっくりな音楽はゆっくり歩く、早い音楽は走る
楽しそうな音楽を聞いて自分の思う楽しい動きを表現する など
「ソルフェージュ」
ドレミの音階で歌うことで音の認知を身に着けるものです。すぐに難しい場合は「リズム」で身に着けた音楽と体の動きを合わせる感覚から練習できます。
ド・レ・ミの音の高低に合わせて、おなか・肩・頭と体の低い位置から高い位置を触ることで音階の感覚を身につけ、動きをつけなくても歌えるように練習する。
「即興」
見たものや音楽に合わせて即興で演奏したり動いたりと表現することで「リズム」「ソルフェージュ」で身に着けたことを発揮します。
人の動きに合わせて、打楽器を鳴らしたり、ピアノを弾く
動物をイメージして好きな楽器を鳴らすなど
この3つの柱を元に基本的な指導法はありますが、決められたものはなく、自由な表現を引き出す、様々なリトミックが展開されています。
リトミックの期待される効果
音を聴いたり、歌ったりという音楽的な能力はもちろん、レッスンの時間の間継続して音楽を聴くには集中力も必要です。また、音楽に合わせて色々な動きをするための筋肉の発達や、動きをイメージしたり表現するための想像力の向上も期待できます。
幼児期・児童期は、感情を表現すること、コントロールすることで情緒の安定につながります。集団でレッスンを受けることで、他の子の表現を感じること、集団でのルールを身に着けることで、社会性の発達を促すとされています。
発達には個人差があるように、効果にも個人差があります。すぐに効果が現れる子もいれば、少しずつゆっくりと現れてくる子もいます。焦らず、まずは音楽に親しみをもって、表現することを楽しむことが大切です。
子どもにリトミックを体験させてみたい!と思ったら
こどもが歌やダンスが好き!リトミックに興味がある!という方は、以下の場所で体験することができます。また、リトミックを実際に体験する際に気をつけたいことをご説明します。
リトミックはどこで体験できる?
〇福祉サービスを受けられる受給者証をお持ちの方
「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」などの療育機関でリトミックを活動に取り入れている所があります。見学や体験が可能なところも多いです。
また、満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までは、幼稚園・保育園と同じく基本的な利用料は無料です。(事業所によって、教材費やおやつ代などがかかる場合があります)お近くの児童発達支援事業所、放課後等デイサービスを調べてみましょう。
近くの児童発達支援事業所・放課後等デイサービスをお探しの方はこちら
〇福祉サービスを受けられる受給者証をお持ちでない方
リトミックのレッスンがある音楽教室では月謝はかかりますが、定期的に通うことができます。
子育て支援センターなど、地域でおこなっている教室やイベントもあります。
親子で通園できる児童発達支援事業所や、親子でレッスンをおこなっている音楽教室・イベントでは、一緒に楽しみながらお子さんの成長を見られる良い機会にもなるでしょう。
リトミックで気をつけたいこと
様々な面で発達を促す効果が期待されるリトミックですが、気をつけたいこともあります。それは、こどもが興味を持っているかどうか、楽しむことができているかどうかです。
興味があること、好きなことだと、子どもも集中しやすく、発達も期待できます。しかし好きではないことだと、集中が続かず、頑張ってやらなくてはいけない事になってしまうため、嫌いになったり苦手意識が生まれてしまうおそれがあります。
楽しいことや好きなことを通して、心も体も成長していけたらこどもにとっても嬉しいですよね。
まとめ
リトミックは音楽感覚や運動機能だけでなく、集中力・想像力・社会性など様々な面で発達を促す効果が期待されています。ダンスや歌が好きな子はもちろん、興味があまりなさそうな子も、体験してみると楽しい!と思うかもしれません。まずは体験してみてはいかがでしょうか。
参考
https://www.tatsuki.org/DoshishaThesis3/thesis/2005/05_ueda.pdf
リトミックの特徴とその理念についての一考察 ―リズム・ソルフェージュ・即興― 二見 美千代

子どもの不器用さが気になる。不器用なだけではない「発達性協調運動障がい」とは
子どもの不器用さが気になる。不器用なだけではない「発達性協調運動障がい」とは
よく転ぶ、ダンスや運動が苦手、ボタンかけがむずかしい、字をうまく書けない。不器用なだけだと、見落とされがちな「発達性協調運動障がい」。お子さんの様子を見ていて、気になることはありませんか?「発達性協調運動障がい」とは何か、どのような支援が必要かについてまとめました。
不器用さを理解するために「発達性協調運動障がい」を知ろう
「発達性協調運動障がい」はDevelopmental Coordination Disorderの略で「DCD」とも呼ばれます。DCDとはどのようなものか、定義やDCDの子の困り感について見ていきましょう。
「発達性協調運動障がい」とは?
「発達性協調運動障がい」(DCD)とは、脳機能の発達に偏りがあるために、日常生活に必要な動作や運動がむずかしくなる障がいです。
最新の精神疾患の国際的な診断基準「DSM-5-TR」によると、DCDの発生頻度は子どもの約5~8%。ADHD(注意欠如・多動性障がい)の発生頻度、約7.2%と同じぐらいです。さらにASD(自閉症スペクトラム障がい)の約1~2%よりも高く、決して珍しくはない、発達障がいのひとつです。
また、発達性協調運動障がいは、自閉スペクトラム症や注意欠如・多動症など、ほかの発達障がいと重複することも多いとされています。
発達性協調運動障がいの「協調」とは?
「協調」とは、
視知覚
触覚
固有覚(自分の体がどこにあるかなどを認識する感覚)
など、さまざまな感覚を、身体の動く速さや強さ、タイミング、正確さ、姿勢やバランスなどと微調整する脳の機能です。
ボールをキャッチするときが良い例です。ボールをキャッチするためにはボールを追う「目の運動」、ボールをキャッチできる位置に体を動かす「足の運動」、ボールを受けるための「腕や手の運動」と、複数の運動を同時にスムーズにおこなう必要があります。
何も考えずにできそうですが、ピアノを弾くときに左右の手で違う動きをするのは、人によってむずかしく感じますよね。
発達性協調運動障がいから起こる生きづらさ
不器用な子、運動が苦手な子という印象だけではありません。そう見られることで、運動面の問題だけでなく、同世代の子どもとの遊びについていけない、馬鹿にされてしまうといった社会的な困難も生まれます。
また、「なぜ私はいつもみんなみたいにできないんだろう」と自己肯定感の低下にもつながり、結果的に不登校などに発展するかもしれません。 大人になると、日常生活で体を大きく動かすことは少なくなりますが、ひげ剃りや化粧、料理や家事など、細かい協調運動が必要になります。作業ができないことによる生きづらさが続くと、うつ病・不安障がいなど精神障がいなどの二次障がいに繋がる可能性もあります。
「発達性協調運動障がい」の子への支援は?
不器用さを少しずつ緩和するためには早期発見、乳幼児期からの支援が効果的だと言われています。不器用な子どもへの支援は、どのようなものが必要でしょうか。
乳幼児期で気づいて二次障がいを予防する
発達性協調運動障がいの兆候は、早くに現れます。お子さんは、まわりより歩き始めや発語の遅れなどが目立っていませんでしたでしょうか。
小脳の発達が急成長する幼児期こそ、支援の効果があらわれやすいといわれています。この時期に苦手な運動をある程度できるようにしておくと、二次障がいを予防できる可能性が高まります。
スモールステップで自信を育てる
簡単にできそうなことができないと、「なんでそんなこともできないの」と周囲に言われてしまうかもしれません。努力してもできないことが多いと、苦手意識は大きくなるばかりです。
体を動かすことが好きな子は多いです。好きなことなのに苦手意識を持つようになってしまう前に、必要な支援を受けて好きなことを伸ばしてあげたいですね。
ただ、定型発達の子のように、お手本を見て真似したり理解したりすることは困難です。具体的に基本的なことから少しずつ「スモールステップ」で、成功体験を積み重ね、自信を育てていくことが大切です。
医療機関や療育機関で支援を受ける
不器用さや運動の苦手さが気になる場合は、乳幼児健診や地域の子育て支援センター、保健センターなどで相談ができますのでお問い合わせください。必要に応じて医療機関や療育機関の紹介をしてもらえることもあります。具体的な支援は、理学療法(PT)と作業療法(OT)があります。
療育センターや、作業療法士または理学療法士がいる小児専門の医療機関で、PTやOTを受けられます。受けられる回数や内容は、それぞれの医療機関によって異なります。
児童発達支援センターや民間の児童発達支援事業所、放課後等デイサービスでも、PTやOTを受けられる施設があります。また作業療法士、理学療法士がいない児童発達支援事業所でも、「粗大運動」や「微細運動」として、遊びの中で動作の練習をしているところもあります。一度見学をしてみると良いでしょう。
まとめ
「発達性協調運動障がい」は思った通りに身体をコントロールすることがむずかしい発達障がいの一つです。まずは本人の努力を認めて、少しでもできたら褒めてあげる。できなかったことは具体的にできる方法を一緒に考えてあげるなど、寄り添うことも大切です。苦手な動作をへらしてあげたい場合は、早期の支援が重要になるので、早めのうちにご相談から始めてみてはいかがでしょうか。
近くの障害福祉サービスをお探しの方はこちら
参考発達性協調運動障害(DCD) 見えているのに理解されにくい発達障害(1)“不器用”なのには理由がある - 記事 | NHK ハートネット発達性協調運動障害(DCD) 見えているのに理解されにくい発達障害 (2)支援のあり方 - 記事 | NHK ハートネット令和 4 年度障害者総合福祉推進事業 「協調運動の障害の早期の発見と適切な支援の普及のための調査」
松山 郁夫(2022)「発達性協調運動症のある幼児児童に対する捉え方と介入」九州生活福祉支援研究会研究論文集第 15 巻第 2 号

- 寄稿
【参加レポとインタビュー】第4回「みんなのバリアフリー運動会」!伊勢崎西部スポーツクラブ理事長、平林知巳さんにインタビュー!
みなさんこんにちは!ワンライフの町田です。10月22日(日)NPO法人伊勢崎西部スポーツクラブさんが主催の「みんなのバリアフリー運動会」にお邪魔してきました!
今回が第4回目の「みんなのバリアフリー運動会」は誰が何を担当するということを決めずに開催されます。そこには「誰かが困っていることに気づいて自ら動けるきっかけづくりにしてほしい」という気持ちが込められています。
「みんなのバリアフリー運動会」参加レポ!
ボランティアの学生もたくさん参加しており、当日は100人以上の人でにぎわっていました!
障がい物競争では、車椅子に乗って、マットレスを乗り越えるのですが多くの方がかなり苦戦していました…。
こんな小さな段差でも、車いすで乗り越えることはむずかしいです。
今回の体験会は、遊びを通して知ることができる、とても良い機会になっていると思いました。
道具の準備やお手伝いも、みんなが率先して動き、運動会が進行していて感動しました。
初めましての人とも、準備の協力や競技を通して自然と会話が生まれ、みなさん運動会をとっても楽しんでいましたよ!
伊勢崎西部スポーツクラブ理事長、平林知巳さんにインタビュー!
お話を伺ったのは、群馬県伊勢崎市の西部地区で活動する「伊勢崎西部スポーツクラブ」の代表、平林知巳さんです。2009年に総合型地域スポーツクラブ「伊勢崎西部スポーツクラブ」を設立し、12年にNPO法人化。「もっと気軽に Enjoy Sports!」をテーマに、多種目・他世代で、スポーツを通して地域の関わりを深めています。
Q1.伊勢崎西部スポーツクラブは主にどのような活動をしていますか?
主な種目はランニング、カヌー、ノルディックウォーキングの活動をしています。子ども向けには、かけっこ塾とタッチラグビーもやっています。公共施設を使った活動には筋トレやストレッチもあります。
スポーツが街に点在しスポーツがたくさん見えることで、みんなが元気に過ごせる街を目標にしているため、地域の公園や、サイクリングロード、川、公共施設で活動させていただいています。
Q2.伊勢崎西部スポーツクラブの今後の課題と展望を教えてください。
施設を所有しておらず、屋外での活動が多いため、天候の課題は切っても切れない課題です。またNPO法事のため、運営する側のスタッフはもちろん、こういったイベントや活動にもより多くの方に参加していただきたいと思っています!
Q3.今後のイベントや活動の予定はありますか?
今週金曜日が締め切りですが、11月19日(日)にさくらやまトレイルが行われます。初心者でも気軽に参加でき、冬桜と紅葉を同時に楽しめる大変人気のイベントです。残り枠が十数名ですので、気になる方は早めにチェックしてください!
12月17日(日)には三時間走(徒歩も可)があります。(前年の様子はこちら)
さらに今年度ボッチャ俱楽部も新しく発足しました!
初回は11月12日(日)、2回目は12月24日(日)と毎月1回の開催を予定しています。伊勢崎市外の方でも参加できますので、気になる方はぜひお問い合わせください。
体験会レポの写真や動画は凸凹村で掲載予定です!
さて、いかがでしたでしょうか?今回の運動会の様子や写真、インタビュー動画などは、このあと、凸凹村でも掲載予定です!気になる方はぜひ凸凹村へご参加ください!
取材:町田
取材ご協力:NPO法人伊勢崎西部スポーツクラブ様
NPO法人伊勢崎西部スポーツクラブ
DET群馬
社会福祉法人伊勢崎社会福祉協議会
\ みんなの障がいが運営!障がいの悩みを共有したり解決し合えるコミュニティ「凸凹村」参加はこちら/
※参加できるのは、「障がいをお持ちの方のみ」です。※
同じ障がいをもつ人と話せる安心コミュニティ「凸凹村」
凸凹村の公式SNSは、障がいをお持ちではない方もフォローいただけます!今回のような体験会レポや、障がいの方に役立つ情報をお届けしています。
ぜひチェックしてみてください!
twitter:https://twitter.com/dekobokomuraInstagram:https://www.instagram.com/dekobokomura/Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100092550507752TikTok:https://www.tiktok.com/@dekobokomura

- コラム
左手指全指機能全廃の私から。「片手で困ることはいくらでもある。けれど、」
私は生まれつき、左手指全指機能全廃という障がいを持っています。どういう障がいかというと、左肘から下の神経がほぼ全廃してしまい、左の手首を曲げたり、手を握ったり、物をつまんだりすることができません。なので、生まれた時からずっと右手を使って生活しています。
小さい頃は、生まれつきだったので片手しか使えなくても何も疑問に思うことなく過ごすことができました。けれど、大きくなるにつれて、できないことが多くなっていき、自分はみんなとちがうんだなぁ〜と思いはじめていきました。
ここで片手で苦労したことやできなかったことをいくつか紹介したいと思います。
一つ目は、重たい荷物の持ち運びです。片手が使えない分、みんなと同じように重たいものを運ぶことができませんでした。重たいものを運ぶ時、友達が代わりによく運んでくれましたが、その時僕は申し訳ない気持ちでいっぱいでした。
二つ目は、体育の授業です。僕は体を動かすことが好きだったので、体育の授業は好きでした。しかし、縄跳び、鉄棒、マット運動など片手でやるのは難しいものもありました。先生は、危ないから見学しておくだけでもいいよと声をかけてくれましたが、僕はやりたい気持ちもあったので、もどかしくなることが多かったです。
こんな感じで、片手で不自由なことは、多分いくらでも出てきます。その度に誰かに助けられたりしてきました。みんなに感謝している反面、申し訳ない気持ちや、できないけどやりたいという気持ちがありました。
そんな自分が嫌で、自分でできることは最大限、やれることはやろうと思いました。
なので、考えて、工夫し、努力することで、自分のやり方を見つけ、今では色々なことが片手でできるようになっています。左手指は狭いところの物をとるのに良いという利点も見つけました。これからも、障がいでできない、と決めつけることなく、色々片手でチャレンジしていきたいです。
\ みんなの障がい運営が企画!障がいの悩みを共有したり解決し合えるコミュニティ「凸凹村」参加はこちら/
同じ障がいをもつ人と話せる安心コミュニティ「凸凹村」

自己効力感を高めるクライミング。障がい者がおこなうメリットと方法。関東のイベントと施設をご紹介。
自己効力感を高めるクライミング。障がい者がおこなうメリットと方法や関東のイベントと施設をご紹介。
視覚障がいの方がおこなうクライミング「ブラインドクライミング」を知っていますか?目隠しをした状態でクライミングをし、ガイドの指示にそって登る方法です。クライミングには障がい者がおこなう上でメリットが多くあり、視覚障がい者だけでなく、幅広く、今注目されつつあります。障がい者がクライミングをおこなうメリットや方法、関東で障がい者クライミングができる施設やイベントをご紹介します。
障がい者がクライミングをおこなうメリットとは
クライミングは障がいの有無にかかわらず、みんな同じルールで、同じ方法で楽しむことができるスポーツです。バリアフリースポーツともいえるクライミング。障がい者がクライミングをおこなうメリットはつぎになります。
誰かと競うことなく自分のペースでできる
クライミングは、ほかのスポーツと違い、飛んでくるボールはなく、速さや運動神経を競うものでもありません。自分でスタートとゴールを決めることができ、誰かのペースに合わせる必要もなく、一点に集中することができます。
精神、身体に関わらず、障がいのある方はどうしても集団スポーツがむずかしいと感じるでしょう。発達障がいや精神障がいの方は、他人と合わせることに困難を感じると思います。
クライミングは他の人を気にすることなく、マイペースにゴールを目指すことができるので、一つのことに集中しがちな方にも最適といえるスポーツです。
障がいの有無に関わらず同じ課題に取り組める
手足をつかい、頂上に登るのに、障がい者のみのルールはありません。クライミングに挑戦する障がい者も健常者と同じ課題に取り組むことができます。
そのため、課題をクリアしたとき、「障がいに関係なく努力することができ、ほかの人と同じ成功体験ができた」という経験をもつことができます。この経験は自信につながり、人生のさまざまな場面で役立つはずです。
自己効力感を高める
自己効力感とは、「自分には目標を達成できる力がある」と信じられる状態のことをいいます。自己肯定感とは違います。自己肯定感はありのままの自分を受け入れられるチカラなので、「目標を達成できなくても自分は良いのだ」という感覚です。
自己肯定感だけでは不足です。人間は「できそうにない」と感じると行動しにくくなります。けれど、「自己効力感」があれば、なんでもチャレンジすることができます。そして新しいことをするのは、人との出会いや自己の成長につながりやすいので、「自己効力感」は障がいのある方こそ身につけたい大事な感覚です。
クライミングは自己効力感を高めると、研究結果でも明らかにされています。フランスの身体障がい者に向けた実験でも、コロンビア州で発達障がい児におこなわれた実験でも、自己効力感の向上が認められています。
参考:https://www.jarvi.org/pub/wp-content/uploads/2018/12/JJVR20130301-05.pdf
全身の運動能力やバランス力を向上することができる
クライミングのイメージは、壁にある物をつかんで登っていくので、握力や腕力などチカラが大事だとイメージされていますでしょうか。
クライミングは握力や腕力の強さよりも、体力に頼るところが大きいです。手だけではなく、足や全身を使って登るので、力の調整がむずかしかったり、弱かったりされる障がい者もおこなえる運動です。クライミングをして全身を鍛えることで、体全体や力のバランス力を整えることができるようになります。
障がい者がクライミングを始めるときの準備やその方法は?
障がいのあるご家族や友達と、クライミングしてみたいと思いましたでしょうか。まず何か道具が必要なのか、どのように始められるか、気になるところでしょう。障がいのある方と一緒に始めるとき、準備しておいた方が良いことや、実際の方法についてご説明します。
まずは室内でおこなうボルダリングから
クライミングにはロープを使いながら壁を登っていく、本格的な方法と、ロープを使わず2~5m程度の壁を登る方法があります。ロープを使わない、短い壁を登るのは「ボルダリング」といいます。
ボルダリングでは、厚いマットが敷かれており、安全対策がとられています。また2~5mなので、それほど高い目標ではなく、なんとかクリアできそうな、挑戦しやすい壁です。
室内でおこなうことができるので、天候に関係なく、いつでもおこなうことができるのもメリットです。初心者の方はボルダリングから始めて、登ることの楽しさを知りましょう。
ボルダリングをしに行くときの持ち物
ボルダリングは、ボルダリングができる専用の室内ジムがあります。登るためのシューズなど道具はありますが、ほとんどレンタルすることが可能です。通常の運動をするときと同じで、動きやすい服装と靴下を履いていくと良いでしょう。
視覚障がいや聴覚障がい、内部障がいなど、目に見えない障がいのある方は「障がい者マーク」のついたものなどわかりやすくしておくと、まわりの方にも気を遣うことができます。衝突事故などをふせぐことにも繋がります。
ボルダリングのルール
ボルダリングは登るコースごとにレベル分けされています。壁にある「特定の色や目印がついた出っ張り」をつかんで登っていく必要があります。それ以外は複雑なルールがないので、簡単なコースから始めましょう。
ほかにも同じコースを登っている方がいる場合は、登らない。登っている人の下に立たない。このように安全面で守らなくてはいけないルールはあるので、ジムを利用する際は注意点を確認しましょう。
【関東】障がい者向けのクライミングジム・イベント
クライミングが障がい者に広まりつつあるとはいえ、まだ一般的とはいえません。近くのボルダリングジムに行きたいと思われたときは、事前に電話で確認しましょう。安全面を考慮した上で、体の状態を聞かれることがあります。
ここでは、障がい者の方に向けた、関東圏にあるクライミングイベントや施設をご紹介します。
ケースケズ ロック クラフト
https://ksks-rock-craft.p-kit.com/
場所:〒365-0014 埼玉県鴻巣市屈巣3649 電話番号:090-6516-5162(9:00~19:00)
障がいのある方に向けて、完全予約、貸し切り制となっているジムです。家族だけで利用できるので、まわりの目を気にすることなく、ボルダリングを楽しむことができます。
クライミング ボルダリングジム HANN (ハン)
https://www.hann-hann2.com/
場所:〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山3718-1電話番号:0467-50-0576
場所;〒243-0804 神奈川県厚木市関口166-1電話番号:0464-04-0886
神奈川県寒川町、厚木の2店舗を展開しているボルダリングジム。初心者向け、上級者向けと分けてあり、ほかの人のペースを気にせずおこなうことができます。障がい者手帳があれば、障がい者割引を利用できます。
障がい者クライミングイベント。マンデーマジック
https://www.monkeymagic.or.jp/join#magic
マンデーマジックは、NPO法人モンキーマジックが主催する、クライミングイベントです。東京と横浜で毎月1回おこなわれています。
東京場所:NOBOROCK 高田馬場店 新宿区高田馬場4丁目9-9 早稲田13時ホールビル1F (高田馬場駅徒歩1分)
横浜場所:クライミングジム Rise 横浜市戸塚区上倉田町479-2 東横ビル上倉田B1 (JR戸塚駅東口から徒歩5分)
クライミングをしたことのある人ない人も、障害のある人も、障害のある人と関わったことのない人も、みんなでクライミングを楽しむことができるイベントです。
障がいや多様性の理解を目的としており、クライミングだけでなく、多様性についての講座もあります。クライミングを通して、人との関わりもしていきたいという方におすすめのイベントです。
まとめ
クライミングはマイペースにみんなと同じ課題に取り組み、成功体験を積むことができるので、自己効力感を高めることができます。もともと障がいのある方は困難を感じやすく、自己効力感を高めることがむずかしいでしょう。だからこそ、クライミングでの成功体験は大きく役に立ちます。障がい者向けに開かれているイベントもありますので、積極的にチャレンジしてみましょう。
近くの障害福祉サービスをお探しの方はこちら
参考
ハートネットTV フクチッチ(32)視覚障害 後編 | NHK ハートネットTV
NPO法人モンキーマジック
cococolor – Diversity is beautiful.| » 視覚障害者といっしょにフリークライミング。見えてきたことは?

- 寄稿
群馬県庁で開催。障がい者eスポーツ体験会【体験レポ】
「一般社団法人群馬県パラスポーツ協会」主催「障がい者eスポーツ体験会」に参加してきました!
みなさんこんにちは!10月9日(月祝)、「一般社団法人群馬県パラスポーツ協会」さんが「障がい者eスポーツ体験会」を開催していたので、お邪魔してきました!
「ぷよぷよ」や「鉄拳」「太鼓の達人」などのゲームを体験!
体験会では「ぷよぷよ」や「鉄拳」「太鼓の達人」などのゲームを体験することができます。
「ぷよぷよ」のブースでは、視線で操作できるコントローラーを展示していました!
私も操作してみました!落ちてくるぷよぷよを見ながら、動かしたい方向の矢印を見て操作する……目はもちろん、脳みそもフル回転です!慣れるまでは大変そうですが、操作に慣れたら、障がいのある方ができるゲームの幅が広がると感じました。
障害福祉施設の物販コーナーも魅力的!
障がい者eスポーツ体験会ですが、ゲームだけではなく、障害福祉施設の利用者さんがつくられたパン、焼き菓子やうどん、アート作品もたくさんならんでいました!
みんなの障がいの運営会社でもあり、群馬県で障害福祉施設を提供する株式会社ワンライフもeスポーツを推進しており、ひとつブースをお借りしていました!
「ONEFRAME」と「ONECODE」は、映像関係やプログラミングなどIT関係の就労継続支援事業所です!
次回開催された際には、みなさんぜひご来場ください!
eスポーツの技術が進歩して、どんどんできる幅が広がれば、eスポーツは本当に障がいの壁をなくすことができるコンテンツになります!そんな可能性をたくさん感じられた展示会でしたし、利用者さんがつくられたパンや創作アートはとても魅力的でした。eスポーツの可能性に興味がある方、障がいについてもっと知りたい方にはぜひ来場してほしいです!
今回の体験会の様子や写真は、この後、凸凹村でも掲載予定です。みなさんぜひ、凸凹村へご参加ください!
同じ障がいをもつ人と話せる安心コミュニティ「凸凹村」
取材:町田ご協力:一般社団法人群馬県パラスポーツ協会

クローズ就労で障がいがバレるのが怖い…そんな不安をなくせる、もう一つの選択肢。「セミオープン就労」とは?
クローズ就労で障がいがバレるのが怖い…そんな不安をなくせる、もう一つの選択肢。「セミオープン就労」とは?
障がいがバレる不安を感じながら、仕事を続けていくのはきつい。けれど、障がい者雇用で入社はしたくない。クローズ就労でバレたり、バレたときに不当な扱いを受けるのも避けたい。
人並みに仕事ができていると思う方や、とくに以前までは普通に働いており、前職の影響で障がい者になったという方は、オープンかクローズで働くか、とても大きな課題になっているでしょう。
そんな悩みを解消するひとつの方法に「セミオープン就労」があります。セミオープン就労とはなにか、メリットやデメリット、セミクローズ就労をする際に気を付けたいことなどを解説します。
セミオープン就労は一部に障がいを開示する働き方
セミオープン就労とは、一般枠に応募し、一部には障がいをオープンにして、一部には障がいを隠して働くという働き方です。法律的には問題ありません。業務に支障を出さない限りは、障がいを隠すかどうかは、プライバシーと同じ扱いになります。
セミオープン就労について最初は面接時に伝える
一番に障がいをオープンにする場は、面接時になります。障がいの特性と「セミオープン就労で働きたい」ことを伝えましょう。採用率が下がるのではないか、と思われるでしょうか。しかし、嘘があまり得意ではない方は、緊張や不安が面接官に伝わってしまう可能性もあります。また障がいを理由に断られる場合、配慮を得られない会社かもしれません。どうしても強い志望動機がある場合は、障がいと合わせて自分の職歴を示したり、できることをアピールしたりして、会社にとってメリットになる部分をしっかり伝えましょう。
直属の上司や仕事で関わる同僚だけに伝える
障がい者がクローズ就労で仕事をやめたり、障がいがバレたりするキッカケの多くは「体調の悪化」です。仕事に支障をきたしたり、自身の許容量を超えた仕事をさせられ、障がいの特性が強くなったり、体調が悪くなったりしないように、仕事に関係のある人にだけには伝えましょう。噂話などで、関係がない社員に広まる可能性もありますね。けれど、噂話は否定しても良いですし、噂話で待遇が変わることもありません。実務に集中して、仕事の成果を出すことが重要です。
伝える範囲は自分がどうしても配慮が必要な部分
面接官、直属の上司や同僚には、障がい者雇用とは違い、障がいについて何も知りません。そのため、障がいの伝え方はとても重要です。障がいの症状の中でも自分で対処することができないところと、どのようにすれば改善できるかを伝えましょう。平日に月1回の通院が必要であれば、通院しないわけにもいかないため、月1回は通院のため半休などいただきたいことを事前に伝えます。あとは自分ではどうしてもカバーできない症状や、困難な作業や働き方についてよく考え、相談してみましょう。
セミオープン就労から転職したくない。長く働くために気を付けることは?
一般枠で働きながら、最低限の配慮は受けられるセミオープン就労。メリットもありますが、デメリットも多くあります。障がいにたいして十分な配慮は受けられませんし、一般の人たちと同じように働くことが求められます。長く働き続けるためには、与えられた仕事をしっかりすること、自身の体調を崩さないことの両立が必要です。
自分の体調管理を徹底する
不規則な生活をしていると、体調が悪化し、障がいの症状も強くなるでしょう。自分の体調が良い睡眠時間を意識し、規則正しい生活を心がけましょう。毎日の体調や障がいの状態を記録して、どういったときに不調を起こしやすいのか、不規則な生活になるのかを把握しておくことも大切です。
残業が続くと症状が悪化する。作業量の限界がある。自分のできる仕事量を把握し、残業をへらすために効率化できる仕事はないかを考えたり、作業量をへらす工夫をします。どうしてもむずかしい場合は上司に相談しましょう。
切り替え方法やストレス発散方法を見つける
発達障がいの場合、ストレスを夜更かしして取り戻そうとする「リベンジ夜更かし」があります。このほかにも不安やストレスで寝られず、睡眠不足で仕事に支障が出るかもしれません。体調の悪化をふせぐために、ストレス発散方法を見つけたり、切り替えになる動作や物をもっておくと良いでしょう。
また、同じ悩みをもつ人同士で話し合ったり、同じくセミオープン就労している人はどのように働いているか聞いてみるのもひとつの手です。解決方法が得られなくても、同じ悩みを話すだけで、気が楽になるはずです。
「障がいをもち、同じように一般枠で頑張っている人と話したい。」そんな方に『凸凹村』をおすすめします。
『凸凹村』はみんなの障がい運営が開き、同じ障がい者が悩みを共有したり一緒に解決したりできるコミュニティです。匿名性の低いフェイスブックのコミュニティなので、安心して使うことができます。ぜひご参加ください。
同じ障がいをもつ人と話せる安心コミュニティ「凸凹村」
まとめ
一般枠で働きながら、障がいにたいして最低限の配慮を得られるセミオープン就労。面接時や仕事をするとき、会社にバレるのではないかという不安や悩みをなくすことができ、メリットが多いです。けれど、一般枠で働く同僚たちと同じ分の仕事をこなす必要があること、自身の障がいを悪化させないことを意識しないといけません。
体調不良を起こさないように体調の管理を徹底すること、働き方を工夫することを心がけ、どうしても対処できない部分は上司やまわりに相談しましょう。
参考
働く工夫 | 双極はたらくラボ | 双極性障害(躁うつ病)で働くヒントがみつかるWebメディア