NewsNewsみんなの障がいニュース
みんなの障がいニュースは、最新の障がいに関する話題や時事ニュースを、
コラム形式でわかりやすくお届けします。

【令和3年度報酬改定】地域定着支援
【令和3年度報酬改定】地域定着支援
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の地域定着支援の改定内容は、さらなる評価や加算の新設が主になります。
令和3年2月4日に発表された、障害福祉サービス等報酬改定の内容をまとめたので、ご参考ください。
地域定着支援の改定内容
地域定着支援の改定内容は以下になります。
・地域生活支援拠点の緊急時の対応をさらに評価
・日常生活支援情報提供加算の新設
・ピアサポート体制加算の新設
・居住支援法人などとの連携を評価
地域生活支援拠点の緊急時の対応をさらに評価
地域生活支援拠点等と指定されたサービス事業所が緊急時の対応をおこなった場合、「地域生活支援拠点等に係る加算」により評価されます。
緊急時対応加算、緊急時支援加算(Ⅰ)または緊急時支援費(Ⅰ)を算定すると、以下の単位がプラスされるようになります。
地域生活支援拠点等に係る加算・・・+50単位/回
日常生活支援情報提供加算の新設
日常生活支援情報提供加算は、利用者の同意を得たうえで、精神障がい者の安定した生活に必要な情報を精神病院などに提供したときに評価される加算です。
日常生活支援情報提供加算であたえられる単位数は以下です。
日常生活支援情報提供加算・・・100単位/回(月1回が限度)
ピアサポート体制加算の新設
ピアサポートは利用者の不安の解消などに効果があるとされています。そのため今回の改定ではピアサポートをすすめる動きが強くあり、「ピアサポート体制加算」が新設されました。
ピアサポート体制加算・・・100単位/月
以下の①~④が、ピアサポート体制加算の算定要件です。
①「障がい者ピアサポート研修(基礎研修・専門研修)」を修了した管理者またはピアサポーターと協働して支援をおこなう人が、常勤換算方法で0.5人以上いること。
※計画相談支援・障がい児相談支援・自立生活援助・地域移行支援・地域定着支援をおこなう事業所を併設しており、併設した事業所の職員を兼務している場合は、勤務先を含む業務時間の合計が0.5人以上であれば算定できます。
②研修を修了しているピアサポーターが、障がい者または障がい者であった、と都道府県や市町村が認めていること。
③ ①②の要件を満たしていることを公表していること。
④「障がい者ピアサポート研修(基礎研修・専門研修」を修了した管理者やピアサポーターが従業員にたいして、ピアサポートに関する研修を年1回以上、おこなっていること。
しかし、まだピアサポートは周知されていないため、令和6年度3月31日までは経過措置として算定要件が緩和されています。
「障がい者ピアサポート研修」ではなく、都道府県や指定都市、中核市が認めた研修を修了したピアサポーターを配置していれば、ピアサポート体制加算の要件を満たしている、と認められます。
地域定着支援サービスをお探しの方はこちらから
居住支援法人などと連携したときに評価
居住支援法人や居住支援協議会との連携をすすめるため、「居住支援連携体制加算」と「地域居住支援体制強化推進加算」が新設されました。
居住支援連携体制加算・・・35単位/日
地域居住支援体制強化推進加算・・・500単位/回(月1回が限度)
居住支援法人や居住支援協議会との連携体制をとり、連携体制を公表していること。そして月に1回以上、居住支援などについて情報共有をしている場合、居住支援連携体制加算があたえられます。
地域居住支援体制強化推進加算は、利用者の住居の確保や居住支援といった課題を報告するなど、居住支援体制を強化する取り組みをおこなうことが算定要件になります。
まとめ
地域定着支援の令和3年度障害福祉サービス等報酬改定は、さらなる評価や加算の新設が中心であり、支援体制を整えることを強く求められています。
このほか全サービスに係る報酬改定の内容は別記事にまとめているので、ご覧ください。
https://www.minnanosyougai.com/article1/%e3%80%90%e4%bb%a4%e5%92%8c3%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%a6%8f%e7%a5%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%80%91%e5%85%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93/
地域定着支援サービスをお探しの方はこちらから
<<参考>>
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(案)
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
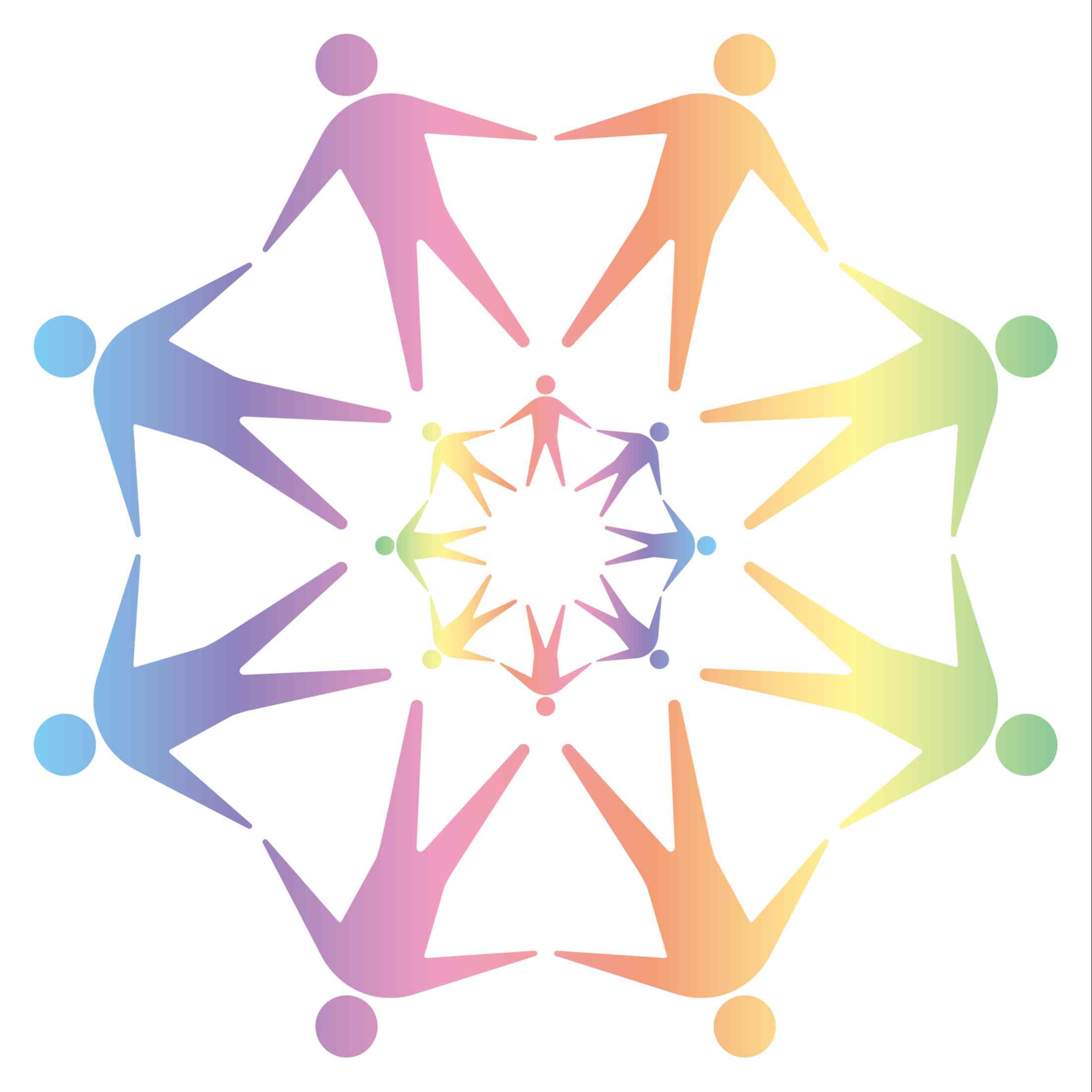
共生社会の実現とは?具体的に何をする?私たちにできることは
共生社会の実現とは?具体的に何をする?私たちにできることは
パラリンピックが掲げる「共生社会」の実現。共生社会とは何か、パラリンピックとの関係性を知っていますか?
「共生社会の実現」や、パラリンピックと共生社会の関係性、共生社会のために一人ひとりができることをご紹介します。
共生社会とは?
共生社会とは、性別、年齢や障がいなど、人それぞれの違いを自然に受け入れ、支えあい、互いに認めあう社会のこと。障がいのある人が受けてきた差別や虐待、隔離、特別なものとして見られるといった行為は、共生社会ではあってはいけません。
障がいがある人も基本的な人権をもっていると認め、「障がいだからできない」という状況をなくすことが、共生社会の考え方です。
パラリンピックと共生社会の関係性
パラリンピックでは「共生社会の実現」がよく訴えられていますね。共生社会とパラリンピックの関係性とはなんでしょうか。
まず大きな関係性は、パラリンピックのルールやスポーツの在り方です。たとえばオリンピックでは、選手が平等に競えるように、競技のルールが変更されます。選手たちはそのルールに合わせて、道具を変えたり、練習の実施方法を変えたりします。選手がルールに合わせるというカタチですね。
しかしパラリンピックでは、障がいに応じて用具の改良などが認められており、選手にルールや用具が合わせるカタチ。
選手にスポーツ側が合わせるカタチは、だれでもスポーツに参加しやすくなったり、健常者と障がい者が一緒にスポーツをおこなえるようにできます。
とくに、パラスポーツ独自競技のボッチャは、年齢、性別、運動能力、障がいの有無に関わらず、だれでも同じように競うことができます。そのため、社内研修や一般的なスポーツイベントにもボッチャが広まりつつあります。
おすすめ記事
パラリンピック独自の競技!ボッチャとは?試合方法・見どころ
「障がいだからできない」ことがなく、一人ひとりに合わせるという特徴が、パラリンピックと共生社会の重要な共通点です。
共生社会の実現とは
「共生社会の実現を目指す」という意見をよく情報媒体で見られるかもしれません。しかし、具体的にはどうしたらいいのか、どのようにすれば「実現」といえるのでしょうか。
「障がいだからできない」ことがなくなり、だれでも等しく生活できる社会は、「環境のバリアフリー」と「心のバリアフリー」をおこなうことで実現します。
環境のバリアフリー
環境のバリアとは、以下の3つのことを指します。
①物理的なバリア・・・狭い通路や段差など車いすだと通りにくいことなど
②制度のバリア・・・障がいがあるから特定の資格や免許を取得できないなど
③文化や情報面のバリア・・・点字や手話がない講演会、音声だけのアナウンスなど
環境のバリアフリーを実現するには、国や店舗、イベントの主催側が積極的に動く必要があります。
物理的なバリアフリーでは、1日平均3千人以上が利用する鉄道やバスなどでエレベーターやスロープの整備が重点的にすすめられ、2020年3月には全国約3600か所の鉄道駅のうち約92%に、車いすの移動を妨げる段差が取り除かれました。
さらにスマートフォンのGPS機能を使って、車いす使用者にバリアフリー状況を提供するアプリも登場しています。
制度や文化面などのバリアフリーでは、「インクルーシブ教育」が注目を集めています。
これまで特別支援級など、障がい者と健常者の子どもには教育に隔たりがありましたが、障がいのある子もない子も同じ場で学ぶことを「インクルーシブ教育」といいます。
子どものときから多様性にたいする感覚を学ぶことは、共生社会の実現においても重要です。
https://www.minnanosyougai.com/article1/%e5%85%b1%e7%94%9f%e7%a4%be%e4%bc%9a%e3%81%ae%e5%ae%9f%e7%8f%be%e3%81%ab%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%aa%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%96%e6%95%99%e8%82%b2%e3%81%a8%e3%81%af/
心のバリアフリー
「環境のバリアフリー」と同じぐらいに欠かせないのが「心のバリアフリー」です。
社会にはさまざまな人がいて、それぞれが「心のバリア」をもっています。心のバリアをなくすには、すべての人が積極的に互いを理解し、助け合う姿勢が求められます。
自分とはちがう体や心の特性、考え方をもつ人を一人ひとりが認め、お互いを分かり合うために話をしたり支え合ったりすることが「心のバリアフリー」です。
心のバリアフリーで重要なポイントは以下の3つです。
①環境や心のバリアを取り除くのは、社会の責任であると理解すること
②障がい者を差別しない
③自分とはちがう状況にある人ともコミュニケーションできる力を身につけることや、困り事や苦しみを理解する心をもつこと
障害福祉サービスをお探しの方はこちら
共生社会のために1人ひとりができること
共生社会のために一人ひとりが具体的にできることは、「心のバリアフリー」です。
すべての人が「心のバリアフリー」の意識をもって生活することで、共生社会の実現に近づきます。
それでは、心のバリアフリーを実現する具体的な行動を見ていきましょう。
障がいの理解
障がいについて知らないだけで、自分とはちがう体や行動に、理解できないと怒ったりしてしまうことがあります。
たとえば、障がい者のなかには細かな動作や読み書きができず、レジでの支払いに時間がかかる場合があります。障がいについて理解がないと、動作が遅いと腹が立つかもしれません。
しかしそれぞれに障がいに理解があれば、店員さんは、その人に合ったコミュニケーション方法ができます。障がい者の方も落ち着いて対応できるでしょう。後ろで待つ人も心の余裕が生まれます。そのため、一人ひとりが障がいを理解することが大切です。障がいについて知識を深めたり、障がいにたいして心の余裕をもつようにしましょう。
バリアフリー設備の意味や目的を理解する
多目的トイレや点字ブロックなどは、それを必要とする人のためにあります。自分には関係ないからといって、優先して使用したり、点字ブロックの上に物を置いたりしていませんか?
環境のバリアフリーをなくすためにあるものを理解して、必要なひとが気持ちよく使えるように配慮しましょう。
困っていそうな場面を見かけたら手伝う
道路の舗装、案内板の表示など、環境のバリアフリーはまだ完璧ではありません。障がい者もみんなと同じように安心して生活するには、人の助け(心のバリアフリー)が必要です。障がい者の方が困っている様子であれば、声をかけて手伝いましょう。
商品やサービスを提供するときは障がいのある利用者にも配慮を
商品やサービスを提供するときは、障がいのある利用者も使いやすいかどうかをイメージしましょう。だれでも利用できるようにするためにどんな配慮が必要なのか、意見を求めることが大切です。
障がいがあるからと決めつけない
障がいといっても多種多様です。障がいの程度や特徴によって、できることとできないことがあります。また、適切な支援があればできるようになることもあります。障がいがあるからと決めつけず、その人自身の個性や能力を活かす方法を考えましょう。
まとめ
共生社会の実現を目指すためには、環境のバリアフリーと心のバリアフリーが必要です。障がいや、障がい者の困り事への理解を深めたり、手助けをしたりするなど、一人ひとりが具体的に行動を起こすことで、共生社会は実現します。
障害福祉サービスをお探しの方はこちら
参考
共生社会の実現のために―内閣府
共生社会の実現に向けて 「心のバリアフリー」の基礎知識と取り組みの具体的事例
みんなで共生社会を目指すために 1 私たちが目指す共生社会
共生社会に向けた「インクルーシブ教育」って?
共生社会の形成に向けて:朝日新聞デジタル
「共生社会」へ、日本は変われるか :東京パラリンピック
パラスポーツから広がる共生社会 | TEAM BEYOND | TOKYO パラスポーツプロジェクト公式サイト
共生社会とは 障害・人種・性別、違い肯定: 日本経済新聞
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020_suishin_honbu/udsuisin/pdf/kyo09.pdf
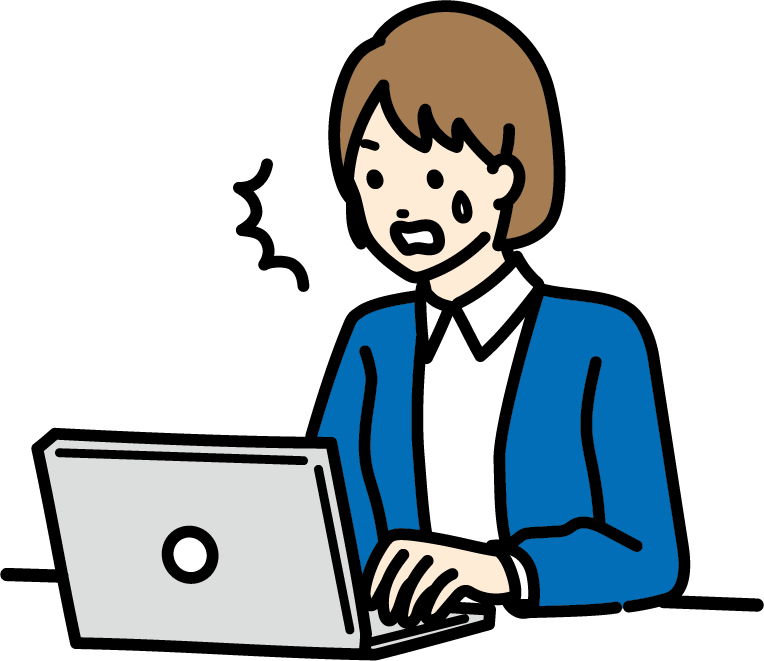
ADHDが急増中?ADHDかもしれない症候群とは?
ADHDが急増中?ADHDかもしれない症候群とは?
インターネットに載っているADHDチェックリストを見てみて、多くの方が当てはまると感じたのではないでしょうか。近年、発達障がい者が増加していることがわかっています。とくに増加率が著しいといわれているのがADHDです。さらに「ADHDかもしれない」と悩む大人もふえるようになってきました。ADHDかもしれないとネットの情報だけで決める危険性や、ADHD急増の原因、ADHDと健常者のちがいについてまとめます。
ADHDとは?
ADHDは脳機能の欠陥のひとつであり、生まれつき起こる障がい。多動性(落ち着きがない)や衝動性(思いつくと行動する)、注意欠陥性(注意力が低い)が行動にあらわれるのが特徴です。多動性・衝動性が目立つタイプと、注意欠陥性が目立つタイプがあります。
多動性や衝動性が目立つタイプ・カッとなって手が出やすい・落ち着くことができない・頭の中がいろいろな情報でいっぱい・順番を待てない
注意欠陥性が目立つタイプ・注意がそれやすい・ものをよく無くす・ミスが続く・締め切りを守れない・時間の約束にいつも遅れる・整理整頓が苦手
この二つのタイプのほかに、どちらの要素も持った中間のような方もいます。
ADHDは急増している?
文部科学省による平成25年度「通級による指導実施状況調査」によると、平成18年から、発達障がいをもつ子どもの数は著しく上がっています。とくに平成18年とその翌年で変化が大きいのはADHDですね。米国でも発達障がいをもつ子どもの増加が見られています。発達障がいと診断された3~17歳の子どもの割合は、2017年には17.8%(子どもたちの約6人に1人)になったという報告も。さらに近年、子どもだけでなく、「大人の発達障がい」という言葉も広まりつつあります。
発達障がい者向け障害福祉サービスをお探しの方はこちら
ADHDが急増している要因
発達障がいは生まれつきのものであり、急増したり、大人になってあらわれたりするのは不思議なことです。この原因は明らかになっていませんが、さまざまな説が挙げられています。
診断基準の変更
発達障がいを判断する診断基準は長い歴史のなかで繰り返し改訂されています。診断基準として使われていた「DSM-Ⅲ」は、落ち着きのない子ども(多動性)より、不注意が多い子ども(注意欠陥性)のほうがADHDの診断基準となっていました。
1994年に公表されたDSM-Ⅳでは、多動性、注意欠陥性のほかに、多動性と注意欠陥性の混合型が診断基準に加えられました。つぎに2013年に公表されたDSM-5(現在の診断基準)では、症状が現れる年齢の下限が緩められています。それまで「7歳以前」に障がいがあらわれた子どもが診断の対象でしたが、「12歳以前」に変更。障がいの範囲も広くなり、自閉症スペクトラムとの合併診断が認められ、ADHDと自閉症どちらの特徴ももつ方も診断できるようになりました。そして17歳以上は診断基準の項目がへらされ、大人もADHDの診断がつきやすくなっています。ADHDが急増しているというより、基準の変更で診断がつきやすくなり、ADHDの発見が急増したという見方です。
認知度の向上
「発達障がい」や「ADHD」という言葉が注目されはじめたのは、ここ10年ほどの話ですね。今や「発達障がい」と調べれば、インターネット上のどこでも「チェックリスト」が公開されています。相談窓口も見つかりやすく、子育て時の違和感や、社会で働いているときの違和感を解決しやすくなっています。さらに「発達障がい」だと発言をしてもいい空気ができてきていますね。それまで違和感があっても、自分がまわりに合わせるしかない、まわりに合わせられない自分がだめなんだ、と発達障がいの生きづらさを訴えられない方がたくさんいました。発達障がいの認知度が上がり、診断を受けやすくなったことが、ADHD急増の理由のひとつでしょう。
大人になってから気づく
子どもの頃は見過ごされてきた発達障がいが、大人になってから生きづらさとしてあらわれるケースがあります。子どもの頃は宿題を忘れても、集中できなくても、それだけでは大きな問題として取り上げられることはありません。しかし社会人になると、時間や納期を守れない、ミスが続く、仕事を続けられる集中力がないと、働いて生活していくことがむずかしくなります。「発達障がい」だと相談しやすくなった現代、生きづらさで診断を受ける大人が多くなり、ADHDが急増したといわれる理由になったと考えられます。
スマホが原因説も
ADHDや大人の発達障がいが増えた要因のひとつに、「スマホ利用者の増加」とする説も。スマホの画面ばかりに集中すると、自然と視野が狭くなりますよね。そのため健常者でも注意障がいが悪化するのではないか、という考えです。スマホが普及してから、寝る前にスマホを見てしまう方もいるのではないでしょうか。不規則な生活を過ごしていたり、良質な睡眠がとれていなかったりすると、日中に物忘れをしやすくなり、集中力を維持することがむずかしくなります。このような症状を、ADHDだと疑う方が多くなっているのかもしれません。
発達障がい者向け障害福祉施設を検索
ADHDとADHD疑いのちがいとは?
インターネット上に公開されているADHDチェックリストに「当てはまっている」と感じて、診断名をつけずに、自分はADHDかもしれないと思いこむ方もいます。よくADHDかもしれないと疑われるのは、うっかり屋の人や、活動的な人ですね。これらとADHDとの違いを確認しましょう。
ADHDとうっかり屋のちがい
うっかりがどのくらいの頻度で起こっているかによります。たまにうっかりミスをしてしまうのか、仕事する度にミスが起きてしまうのか。ADHDとうっかり屋の大きなちがいは、ミスをしたあとに対処できるかという点です。うっかり屋はミスをして叱られたあと、ミスをしない対処法を実践して、ミスの頻度をへらすことができます。ADHDは対処法を知って実践しても完全に抜けてしまいます。たとえば明日に締め切りが迫っていてメモやカレンダーに残し、通知をオンにしても忘れてしまったり、やっていない課題や仕事をなぜか「やった」と思ったりしてできません。
ADHDと多動性・衝動性のちがい
体を動かすことが好きで、じっと待っていることが苦手という特徴は、ADHDにも活動的な人にも当てはまっているように感じますね。活動的な人とADHDの大きなちがいは、ひとつのことを最後まで集中してやりきれるか。ADHDの場合、集中力が維持できず、興味があちこちに行くので、やりっぱなしが多いです。活動的でフットワークが軽い人はひとつのことを最後まで続けることができます。
ADHDかもしれない症候群の危険性
ADHDのチェックリストだけでADHDかもしれないと決めつけてしまう「ADHDかもしれない症候群」の大人もふえています。さらにADHDの診断基準が緩んだことで、ADHDだと過剰診断され、内服薬を渡されることも。ADHDの内服薬は副作用や依存性をともなうものもあり、ADHDでない方が服薬するのは危険です。もし本当はADHDでなかった場合、服薬で最初は効果があっても、どんどん効果が薄れていきます。しかし、その頃には服薬をやめることができず、効果がないまま処方を続けられるという事態に。そのためインターネット上のチェックリストで「ADHDかもしれない」と思ったときは、ます以下のことに留意して診断を受けてください。
まずは環境を見直してみよう
ADHDのような症状で悩み、仕事や生活ができない状態になっているなら、発達障がいを診療している医師に相談するべきです。しかし、ADHDの特徴はあるけれど生活できている場合は、まずは環境を整えてみましょう。不規則な生活を送っていると、日中のミスや集中できない時間はふえます。ミスの対処法を実施しないと同じミスを何度もくり返します。仕事や仕事のやり方が合っていないと、集中力を持続できません。そのため生活習慣を整える、仕事のやり方を変えるなど、環境を見直すことから始め、それでも改善しないときは医師に相談しましょう。
まとめ
ADHDが急増しているのは、時代の変化によるものです。診断基準の変更、発達障がいだと発言しやすい環境、スマホ利用者の増加などが要因として考えられています。こうした時代に合わせて、ADHDかもしれないと疑い、過剰診断される方もふえてきました。ADHDでない方が安易にADHDのための薬を服薬するのは危険です。ADHDかもしれない症状があったとしても生活ができている場合は、まず環境の見直しから始めてみてください。
発達障がい者向け障害福祉サービスをお探しの方はこちら
<<参考>>
ADHDの9割は誤診? 疑似ADHDとは | 横浜つづきクリニック|内視鏡内科 心療内科 内科
ADHDの人は増えている? 「診断」をひもとく:朝日新聞デジタル
発達障害かもしれない人と発達障害の違い|疾患について|名古屋市瑞穂区の心療内科・精神科あらたまこころのクリニック
大人の発達障害はなぜ増えている? どんな症状?――もややちゃんが脳内科医の先生に聞いてきた【Part1】 - Woman type[ウーマンタイプ] | 女の転職type
ADHDの人は増えている? 「診断」をひもとく:朝日新聞デジタル
10人に1人がADHD?日本で「発達障害児」が急増しているワケ | 富裕層向け資産防衛メディア | 幻冬舎ゴールドオンライン
https://www.congre.co.jp/jaslht2018/top/document.pdf
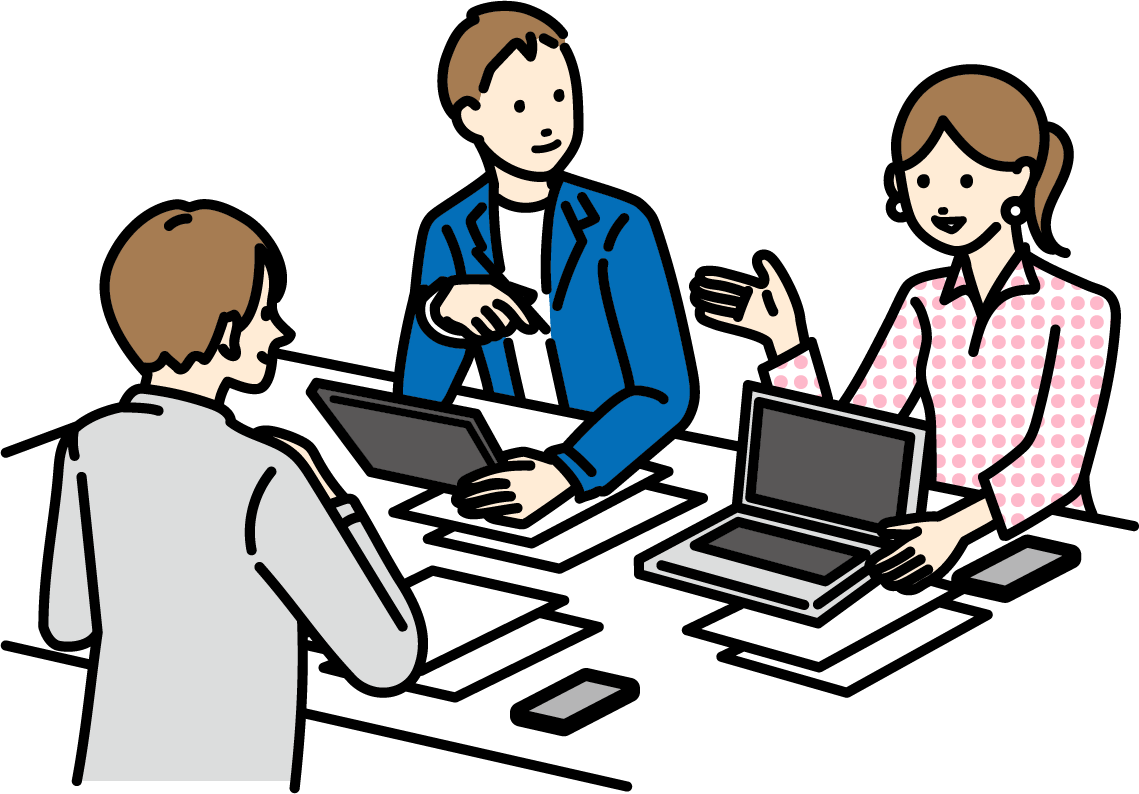
【令和3年度報酬改定】就労定着支援
【令和3年度報酬改定】就労定着支援
就労定着支援の令和3年度障害福祉報酬改定では、就労定着率が高い企業はさらに評価され、多岐にわたる支援活動をしやすくなります。
令和3年2月4日に発表された、令和3年度障害福祉報酬改定のおもな内容をまとめましたので、ご参考ください。
就労系に関する改定内容
就労系に関する改定内容をご説明いたします。
おもな改定内容は、以下の3点になります。
・新型コロナウィルスの影響をふまえた実績の算出
・在宅サービス利用の要件の見直し
・一般就労への移行を促進
新型コロナウィルスの影響をふまえた実績の算出
新型コロナウィルスの影響をふまえた実績の算出ができます。
令和3年度の報酬算定は、令和元年度または令和2年度の実績を用いなくてもよいとされます。
就労定着支援
次のいずれかの期間の実績で評価
(Ⅰ)平成30年度、令和元年度・令和2年度(3年間)
(Ⅱ)平成30年度及び令和元年度(2年間)
在宅でのサービス利用の要件の見直し
令和3年度から、在宅でのサービス利用要件が緩和されます。
緩和された利用要件は以下です。
利用者要件
在宅でのサービス利用を希望しており、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者。
事業所要件
・ 在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。
・1日2回の連絡、助言または進捗状況の確認、日報作成を行うこと。作業活動、訓練等の内容などに応じ、1日2回を超えた対応を行うこと。
・緊急時の対応ができること。
・疑義照会などに対し、随時、訪問や連絡等による必要な支援が提供できる体制を確保すること。(ここまで現行と同じ)
・事業所職員による訪問、利用者の通所または電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を1週間につき1回は行うこと。
・原則、月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問または利用者による通所により、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価などをすること。
・1週間に1回の評価が通所により行われ、あわせて、月1回の訓練目標にたいする達成度の評価なども行われた場合、月1回おこなう評価などによる通所に置き換えてもよい。
・在宅と通所による支援を組み合わせることも可能。
一般就労への移行を促進
一般就労への移行に更なる評価があたえられます。
また一般就労への移行や工賃の向上を目指すため、施設外就労加算を廃止・再編。
一般就労への移行実績が高い事業所や、高い工賃を実現する事業所、地域連携の取り組みへの評価に組み替えられます。
就労定着支援施設をお探しの方はこちらから
就労定着支援のおもな改定内容
就労定着支援の報酬改定のおもな内容は以下になります。
・基本報酬と報酬区分の見直し
・支給要件の見直し
・対面での支援の要件を緩和
・定着支援連携加算を新設
基本報酬と報酬区分の見直し
令和3年度報酬改定では、就労定着率が高い事業所は大幅に基本報酬が上がります。しかし就労定着率が3割未満にあたる事業所は161単位も下がることになり、運営が厳しくなるでしょう。
また就労定着支援の事業所の80%以上が、就労定着率8割以上を実現している、という現状があるため、就労定着率が8割以上からの区分が、細かく設定されるようになりました。
就労定着率が高かった事業所は大きな変化になりますね。
就労定着率
8割以上9割未満の事業所・・・58単位アップ
9割以上9割5分の事業所・・・70単位アップ
9割5分以上の事業所・・・234単位アップ
画像引用:https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000734439.pdf
就労定着支援施設をお探しの方はこちらから
支給要件の見直し
就労定着支援の支給要件は、「利用者との対面により月に1回以上の支援をおこなったとき」に支給されることとなっていました。
しかし令和3年度報酬改定では、どのような支援をしたかなどをまとめた「支援レポート」を作成し、本人や必要な関係者などに月に1回以上共有することが要件となります。
就労定着支援の活動は、利用者との対面だけではなく、さまざまなものがあります。対面以外の活動が正当に評価されることになりますね。
対面の要件を緩和
運営基準に規定されている「対面での支援」の「対面」の要件が緩和されます。
実際に対面することのほかに、テレビ電話などをICTを用いる方法も「対面」の範囲内となりました。
「定着支援連携促進加算」を新設
就労定着支援に関わる機関との連携をすすめるため、「企業連携等調整特別加算」がなくなり、「定着支援連携促進加算」が新設されます。
企業や地域障がい者職業センター、障がい者就業・生活支援センター、医療機関といった、関係機関を交えた会議を開き、連絡調整などをおこなったとき、以下の単位が加算されます。
定着支援連携促進加算・・・579単位(年4回が限度)
「企業連携等調整特別加算」では支援開始の1年目のみを評価するものでしたが、「定着支援連携促進加算」は最大3年間が対象となります。
まとめ
就労定着支援の令和3年度報酬改定では、就労定着率が高い事業所が十分に評価されることになります。また対面での支援以外のさまざまな活動も正しく評価されるので、ますます支援に力を入れることができます。事業所も利用者にとっても良い変化になるでしょう。
全サービスに関わる報酬改定の内容は別記事にまとめていますので、ご参考ください。
https://www.minnanosyougai.com/article1/%e3%80%90%e4%bb%a4%e5%92%8c3%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%a6%8f%e7%a5%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%80%91%e5%85%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93/
就労定着支援施設をお探しの方はこちらから
<<参考>>
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

【令和3年度報酬改定】計画相談支援・障がい児相談支援
【令和3年度報酬改定】計画相談支援・障がい児相談支援
計画相談支援・障がい児相談支援の経営状況は厳しいと指摘されています。そのため計画相談の令和3年度障害福祉サービス報酬改定は、基本報酬を上げたり、加算の要件を緩和したり、新たな評価をつくったりするなど、経営状況を助ける動きがあります。
令和3年度の障害福祉サービス報酬改定のおもな内容をまとめたので、ご参考ください。
計画相談支援・障がい児相談支援の改定内容
計画相談支援・障がい児相談支援の改定内容を以下にまとめました。
・基本報酬の見直し
・加算の見直し
・ピアサポート体制加算の新設
・計画決定月やモニタリング対象月以外の業務を評価
・他機関へのつなぎの支援をおこなったときに評価
・事務負担の軽減
・適切なモニタリング頻度の徹底
基本報酬の見直し
特定事業所加算は廃止され、「機能強化型サービス利用支援費」という基本報酬区分が新設されます。
機能強化型サービス利用支援費・機能強化型継続サービス利用支援費は、特定事業所加算と同じく段階ごとに評価するかたちです。
現行の特定事業所加算Ⅳの「常勤専従の相談支援員を2名以上配置する」という要件を緩和。そして「2人のうち1人以上が常勤専従であること」が算定要件となる「機能強化型サービス利用支援費Ⅳ」、「機能強化型継続サービス利用支援費Ⅳ」が設けられます。
機能強化ⅢやⅣを満たす事業所は基本報酬が大幅にアップします。
それぞれの単位と算定要件は以下になります。
①機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)・・・1864単位/月
特定事業所加算Ⅱの要件を満たすこと。
②機能強化型サービス利用支援費・・・1764単位/月
特定事業所加算Ⅲの要件を満たすこと。
③機能強化型サービス利用支援費・・・1672単位/月
特定事業所加算Ⅳの要件を満たすこと。
④機能強化型サービス利用支援(Ⅳ)・・・1622単位/月
専従の相談支援専門員を2名以上配置し、そのうち1名以上が常勤専従かつ相談支援従事者現任研修を修了していること。
現行の特定事業所加算Ⅰ・Ⅱのうち以下の要件を満たすこと。
⇒利用者に関する情報やサービス提供の留意事項の伝達などを目的とした会議を定期的に開催すること。
⇒24時間連絡体制を確保しつつ、必要に応じて利用者等の相談に対応す
る体制を整えていること
⇒基幹相談支援センターなどから支援が困難な事例を紹介された場合でも、計画相談支援などを提供すること。
⇒基幹相談支援センターなどが実施する事例検討会などに参加すること。
⇒ 指定特定相談支援事業所は、指定サービス利用支援または継続サービス利用支援を提供する件数が1月間に相談支援専門員1人当たり40件未満であること。
(指定障害児相談支援事業者の指定をあわせて受け、一体的に運営されている場合は、指定障害児相談支援の利用者を含む。)
さらに、常勤専従の相談支援専門員1名配置を必須としたうえで、
・地域生活支援拠点などを構成する、いくつかの指定特定相談支援事業所で人員配置要件が満たされていること
・24時間の連絡体制がしっかりできていること
以上ができていれば、複数の事業所で、機能強化型サービス利用支援費などの算定要件を満たすことができます。
加算の見直し
障害福祉サービスの利用申請から支給決定、利用開始までの期間内に一定の要件を満たした相談支援を提供した事業所への初回加算がアップ。
新規の計画を作成したときに初回加算が算定されていましたが、令和3年度報酬改定からは以下の要件を満たした月にも初回加算が算定されるようになります。
・指定計画相談支援の利用の契約をした月から、サービス等利用計画案を利用者に交付した月までの期間が3か月を超えたとき
・4か月目以降に、月に2回以上、利用者の家(障がい児の場合は居宅に限る)に訪問し、利用者や家族と面接をおこなったとき
上記の要件を満たした月は、その月分の初回加算に相当する額を加えられます。
また「主任相談支援専門員配置加算」が新しく設けられました。事業所に配置された主任相談支援専門員が、従業員へ研修を実施したとき、月に100単位あたえられます。
ピアサポート体制加算の新設
以下の①~④を満たしたとき、ピアサポート加算があたえられるようになります。
ピアサポート体制加算・・・100単位/月
①「障がい者ピアサポート研修(基礎研修・専門研修)」を修了した管理者またはピアサポーターと協働して支援をおこなう人が、常勤換算方法で0.5人以上いること。
(計画相談支援・障がい児相談支援・自立生活援助・地域移行支援・地域定着支援を併設しており、併設された事業所の職員を兼務しているときは、勤務先を含む業務時間の合計が0.5人以上であれば算定可能。)
②研修を修了したピアサポーターが、障がい者または障がい者であった、と市町村が認めていること。
③ ①②の要件を満たしていることを公表していること。
④「障がい者ピアサポート研修(基礎研修・専門研修」を修了した管理者などから、事業所のほか従業員へ、ピアサポートに関する研修を年1回以上、おこなっていること。
令和6年度3月31日までは、経過措置として算定要件が緩和されています。
「障がい者ピアサポート研修」でなくても、都道府県や市町村が認めた研修を受けたピアサポーターを配置していれば、要件を満たしている、と認められます。
全国の相談支援事業所を検索
計画決定月やモニタリング対象月以外の業務を評価
報酬改定から、「集中支援加算」が新設され、計画決定月やモニタリング対象月のほかの業務を評価されるようになります。
集中支援加算・・・300単位/月
以下の3つの要件を満たすと、「集中支援加算」があたえられます。
①障がい福祉サービスの利用者などの希望に応じて利用者の自宅に訪問し、利用者やその家族と月2回以上、面接をおこなったとき
②利用者、障がい福祉サービス事業所などが参加するサービス担当者会議を開いたとき
③病院や企業、保育所、特別支援学校や地方自治体からの希望に応じて、以上の期間が主催する会議へ参加したとき
適切なモニタリング頻度の徹底
利用者へ適切なモニタリングをするため、以下のとおりに対応することが求められます。
・利用者の個性もふまえてモニタリングの回数を決定することや、モニタリング期間の変更手続きを再度広く知らせること。
・利用者それぞれの状況によってはモニタリングの頻度をふやさなくてはいけないことを、例を示して説明すること。
・モニタリング対象月以外の相談支援業務は緊急的、臨時的な取り扱いだということや、たくさん算定が必要な利用者はモニタリングの頻度をあらためて検証しなければいけないことをはっきり示すこと。
他機関へつなぐ支援をおこなったときに評価
事業所が他機関へつなぐ支援をおこなったときに評価するため、居宅介護支援事業所等連携加算の見直しと、障がい児相談支援に「保育・教育等移行支援加算」がつくられました。
計画相談は「居宅介護支援事業所等連携加算」、障がい児相談は「保育・教育等移行連携支援加算」により評価されます。
また単位が変更され、新たな算定要件がつくられました。
・介護保険の居宅介護支援事業者などへの引継ぎ
・障がい福祉サービスの利用が終わり、保育所や特別支援学校、企業、障がい者就業・生活支援センターなどとの引継ぎ
これらに一定の期間がかかる場合、以下の要件を満たすと加算の対象になります。
①該当する月に2回以上、利用者の住む家に訪問し、利用者、家族と面接をおこなった場合
②他機関が主催する会議に参加し、利用者の支援内容を検討したとき
③他機関との連携をするときに、利用者の心身の状況などを文書により情報提供したとき
①②を満たした場合、居宅介護支援事業所等連携加算も、保育・教育等移行支援加算も、月に300単位あたえられることに。
③を満たした場合は、月に100単位あたえられます。
ただし算定回数は、障がい福祉サービス利用中は月に2回、利用終了後(6か月以内)は月1回が限度です。
事務負担の軽減
今回の改定では特定事業所加算が廃止され、基本報酬に組み込まれるので、事務負担が軽減されます。
さらに、加算の算定要件となる業務の挙証書類は、基準省令で定める記録(相談支援台帳など)に記載し、保管することで良しとされます。事務負担が大幅にへることが期待できますね。
まとめ
計画相談支援の令和3年度報酬改定では、基本報酬の向上や加算の新設、要件の緩和や事務負担の軽減など、事業所の運営を助けるような改定になりました。
また細かくしっかり評価されることで、利用者の相談支援の質の向上にもつながります。
このほか全サービスに関わる報酬改定の内容は別記事にまとめていますので、ご覧ください。
https://www.minnanosyougai.com/article1/%e3%80%90%e4%bb%a4%e5%92%8c3%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%a6%8f%e7%a5%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%80%91%e5%85%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93/
全国の相談支援事業所を検索
<<参考>>
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

【令和3年度報酬改定】行動援護
【令和3年度報酬改定】行動援護
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定では、行動援護の基本報酬の引き上げや加算の新設、サービス提供責任者の要件についてふれられています。
令和3年2月4日に発表された、行動援護の改定内容をまとめたので、ご参考ください。
行動援護の改定内容
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の行動援護の改定点は以下のとおりです。
・基本報酬の見直し
・サービス提供責任者の要件の経過措置を延長
・地域生活支援拠点等の緊急時の対応を評価
・身体拘束などの適正化
・福祉・介護職員等に関する加算の見直し
基本報酬の見直し
行動援護の経営実態を考慮して、行動援護サービス費が以下のように引き上げられます。
所要時間
見直し前
見直し後
30分未満
255単位
258単位
30分~1時間
403単位
407単位
1時間~1時間半
587単位
592単位
1時間半~2時間
735単位
741単位
2時間~2時間半
884単位
891単位
2時間半~3時間
1032単位
1040単位
3時間~3時間半
1182単位
1191単位
3時間半~4時間
1330単位
1340単位
4時間~4時間半
1480単位
1491単位
4時間半~5時間
1628単位
1641単位
5時間~5時間半
1777単位
1791単位
5時間半~6時間
1925単位
1940単位
6時間~6時間半
2075単位
2091単位
6時間半~7時間
2223単位
2240単位
7時間~7時間半
2373単位
2391単位
7時間半以上
2520単位
2540単位
サービス提供責任者の要件の経過措置を延長
介護福祉士や社会福祉士および介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2第2号の指定を受けた学校、または養成施設で1月以上、必要な知識および技能を習得した介護福祉士などを「行動援護従業者養成研修課程修了者」とみなす経過措置が、令和5年度末まで延長されます。
経過措置の延長の背景には、人材の確保がむずかしいことや、従業者の約2割が経過措置対象者であり、そのうち約1割が実務研修課程の修了予定がないことがあります。
行動援護サービスをお探しの方はこちらから
地域生活支援拠点等の緊急時の対応を評価
「地域生活支援拠点等に係る加算」が新設されました。
市町村に地域生活支援拠点等と認められたサービス事業所が緊急時の対応をおこない、緊急時対応加算、緊急時支援加算(Ⅰ)または緊急時支援費(Ⅰ)を算定すると、以下の単位が加えられます。
地域生活支援拠点等に係る加算・・・+50単位/回
身体拘束などの適正化
運営基準に、身体拘束に関する要件が新設されます。
①身体拘束をおこなうときは、必要な事項を記録すること。
②身体拘束の適正化のための対策検討委員会を開き、委員会の検討結果を従業員へ徹底周知すること。
③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
④身体拘束等の適正化のための研修を従業員へ定期的におこなうこと。
①は令和3年度から義務化、②~④は1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化されます。
また令和5年4月からは運営基準の①~④を満たしていない訪問系サービス事業所には「身体拘束廃止未実施減算」が適用されます。以下のとおり、基本報酬が1日ごとに減算されてしまいます。
身体拘束廃止未実施減算・・・5単位/日
福祉・介護職員処遇改善加算・処遇改善特別加算の見直し
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)と、福祉・介護職員処遇改善特別加算は1年間の経過措置を設け、廃止されます。
また加算率の算定方法は、障害福祉サービス等経営実態調査にある従業者数や報酬請求事業所数を用いて、加算率が見直されます。
類似する複数のサービスはグループ分けし、加算率が決められます。
行動援護の加算率は以下の通りに見直されました。
(Ⅰ)所定単位数× 23.9%
(Ⅱ)所定単位数× 17.5%
(Ⅲ)所定単位数× 9.7%
職場環境要件も見直されました。職場環境等要件に定められている取り組みは、当該年度に実施することを求められます。
なお、継続して処遇改善加算を取得している事業所は、当該年度に実施できない正当な理由があれば、特別に、前年度の取り組み実績で要件を満たすことができます。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールが緩和されます。
より柔軟な配分をできるようにするため、経験・技能のある障害福祉人材は、ほかの障害福祉人材の平均引き上げ額の「2倍以上とすること」としているルールを、「より高くすること」に。
また福祉・介護職員等処遇改善加算と同じく、類似している複数のサービスはグループ分けして加算率が設定されます。
同行援護の福祉・介護職員等特定処遇改善加算の加算率は、以下のとおりに見直されました。
(Ⅰ)所定単位数× 7.0%
(Ⅱ)所定単位数× 5.5%
まとめ
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の行動援護の大きな改定は、基本報酬の引き上げや、サービス提供責任者要件の経過措置の延長などです。
このほか全サービスに関わる報酬改定の内容は別記事にまとめたので、ご参考ください。
行動援護サービスをお探しの方はこちらから
https://www.minnanosyougai.com/article1/%e3%80%90%e4%bb%a4%e5%92%8c3%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%a6%8f%e7%a5%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%80%91%e5%85%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93/
<<参考>>
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

【令和3年度報酬改定】就労継続支援A型
【令和3年度報酬改定】就労継続支援A型
令和3年2月4日、障害福祉サービス報酬改定の概要が発表されました。
就労継続支援A型は新しいスコア制が導入され、より質の高いサービスが求められることに。
令和3年度の報酬改定の、就労継続支援A型の内容をまとめたので、ご参考ください。
就労系に関する改定内容
就労継続支援A型にかかわらず、就労系全体に関する改定内容をご説明いたします。
改定内容は、以下の3点になります。
・新型コロナウィルスの影響をふまえた実績の算出
・在宅サービス利用の要件の見直し
・一般就労への移行を促進
新型コロナウィルスの影響をふまえた実績の算出
新型コロナウィルスの影響をふまえた実績の算出が可能になりました。
令和3年度の報酬算定は、令和元年度または令和2年度の実績を用いなくてもよいとされます。
就労継続支援A型の場合
スコア方式の項目のうち、「1日の平均労働時間」については、次のいずれかの年度の実績で評価
(Ⅰ)平成30年度
(Ⅱ)令和元年度
(Ⅲ)令和2年度
※ 「生産活動収支の状況」については、前年度を「令和元年度」に置き換えた実績で評価することも可(その場合、前々年度は「平成30年度」を用いる)
※ それ以外の項目は、令和2年度実績で評価
在宅でのサービス利用の要件の見直し
令和3年度から、在宅でのサービス利用要件が緩和されます。
緩和された利用要件は以下です。
利用者要件
在宅でのサービス利用を希望しており、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者。
事業所要件
・ 在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。
・1日2回の連絡、助言または進捗状況の確認、日報作成を行うこと。作業
活動、訓練等の内容などに応じ、1日2回を超えた対応を行うこと。
・緊急時の対応ができること。
・疑義照会等に対し、随時、訪問や連絡等による必要な支援が提供できる
体制を確保すること。(ここまで現行と同じ)
・事業所職員による訪問、利用者の通所または電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を1週間につき1回は行うこと。
・原則、月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問、または利用者による通所により、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価などを行うこと。
・1週間に1回の評価が通所により行われ、あわせて、月1回の訓練目標にたいする達成度の評価なども行われた場合、月1回おこなう評価などによる通所に置き換えてもよい。
・在宅と通所による支援を組み合わせることも可能。
一般就労への移行を促進
一般就労への移行に更なる評価があたえられ、就労継続支援から就労移行支援への移行については「就労移行連携加算」が新しく設けられました。
就労移行連携加算・・・ 1,000単位
①就労継続支援A型を受けたあとに、就労移行支援の支給決定を受けた者がいたとき、支給の申請の日までに、就労移行支援事業者との連絡調整や、相談援助などをおこなうこと。
②申請をおこなうとき、就労継続支援A型の支援の状況などを文書により相談支援事業者にたいして提供すること。
①②の条件を満たしているとき、1回に限り、所定単位数が加算されます。
一般就労への移行や工賃の向上を目指すため、施設外就労加算を廃止・再編。一般就労への移行実績が高い事業所や、高い工賃を実現する事業所、地域連携の取り組みへの評価に組み替えられます。
そして一般就労への移行促進を見込んで、就労継続支援の福祉専門職員配置等加算における有資格者に「作業療法士」が新たに追加されます。
就労継続支援A型の改定内容
就労継続支援A型のおもな改定内容は以下のとおりです。
・基本報酬の算定方法の見直し
・身体拘束などの適正化
・医療連携体制加算の見直し
・福祉・介護職員等に関する加算の見直し
基本報酬の算定方法の見直し
就労継続支援A型事業所の重要な改定は、算定方法が大きく変わることです。
これまで就労継続支援A型の報酬は「1日の平均労働時間」で算出していましたが、令和3年度の報酬改定からは、以下の5つの項目から、スコア方式により報酬が決まります。
①労働時間
②生産活動
③多様な働き方
④支援力向上
⑤地域連携活動
画像引用:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
そしてスコア方式による評価内容を、1年に1回以上、ホームページなどインターネットや、そのほかの方法をつかってを公表することが義務付けられます。
スコア方式による評価内容を未公表とした場合は、所定単位数の15%が減算されます。
就労継続支援A型施設をお探しの方はこちらから
身体拘束の適正化
事業の運営基準に、身体拘束に関する要件が追加されます。
①身体拘束をおこなうときは、その態様や時間、利用者の心身の状況、やむを得ない理由、そのほか必要な事項を記録すること。
②身体拘束の適正化のための対策検討委員会を開き、委員会の検討結果を徹底して従業員へ周知すること。
③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
④従業者へ、身体拘束等の適正化のための研修を定期的におこなうこと。
②~④は1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化されます。
①の運営基準を満たしていない事業所は「身体拘束廃止未実施減算」が適用され、基本報酬が減算されます。
②~④は令和5年4月以降から、身体拘束廃止未実施減算の要件に加えられます。
身体拘束廃止未実施減算・・・5単位/日
医療連携体制加算の見直し
医療連携体制加算の報酬単位は、医療的ケアがあるかどうか等で区分されるようになります。また、原則、利用者を診察している主治医から個別に受けるものを「医師からの指示」とすることが決められます。
看護職員が看護する利用者
単位数
医療連携体制加算(Ⅰ)
32単位
医療連携体制加算(Ⅱ)
63単位
医療連携体制加算(Ⅲ)
125単位
医療連携体制加算(Ⅳ)
1人
800単位
2人
500単位
3人以上8人以下
400単位
医療連携体制加算(Ⅴ)
500単位
医療連携体制加算(Ⅵ)
100単位
福祉・介護職員処遇改善加算・処遇改善特別加算の見直し
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)と、福祉・介護職員処遇改善特別加算は廃止されます。
(令和3年3月末時点で同加算が算定されている障害福祉サービス等事業所は、1年間の経過措置を設けられます。)
また加算率の算定方法は、障害福祉サービス等経営実態調査にある従業者数や報酬請求事業所数を用いて、加算率が算定されることになります。類似する複数のサービスはグループ分けして、加算率を算定。
就労継続支援A型の加算率は以下の通りです。
(Ⅰ)所定単位数× 5.7%
(Ⅱ)所定単位数× 4.1%
(Ⅲ)所定単位数× 2.3%
※指定障害者支援施設の場合
(Ⅰ)所定単位数× 6.4%
(Ⅱ)所定単位数× 4.7%
(Ⅲ)所定単位数× 2.6%
(Ⅳ)(Ⅲ)の90/100
(Ⅴ)(Ⅲ)の80/100
職場環境要件も変更されました。職場環境の改善につながる取り組みは、当該年度に実施することを求められます。ただし、継続して処遇改善加算を取得している事業所は、当該年度に実施できない正当な理由がある場合、例外的に前年度の取り組み実績で要件を満たすことができます。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールが、より柔軟な配分をできるように見直されました。
「経験・技能のある障害福祉人材」は「ほかの障害福祉人材」の「2倍以上とすること」としているルールが、「より高くすること」に変わります。
また福祉・介護職員等処遇改善加算と同じく、類似している複数のサービスはグループ分けし、以下のように加算率が設定されました。
(Ⅰ)所定単位数× 1.7%
(Ⅱ)所定単位数× 1.5%
指定障害者支援施設の場合は、(1月につき+ 所定単位数× 1.8%)が加算率になります。
まとめ
就労継続支援A型の令和3年度報酬改定では、サービスの質の高い事業所が正当に評価され、報酬の向上が期待できます。
またスコア方式の公表を義務化することで、事業所はさらにサービスを充実させる努力ができ、障がい者もより満足できるような事業所をえらべるようになるでしょう。
全サービスに関わる報酬改定の内容は別記事にまとめていますので、ご覧ください。
https://www.minnanosyougai.com/article1/%e3%80%90%e4%bb%a4%e5%92%8c3%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%a6%8f%e7%a5%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%80%91%e5%85%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93/
就労継続支援A型施設をお探しの方はこちらから
<<参考>>
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
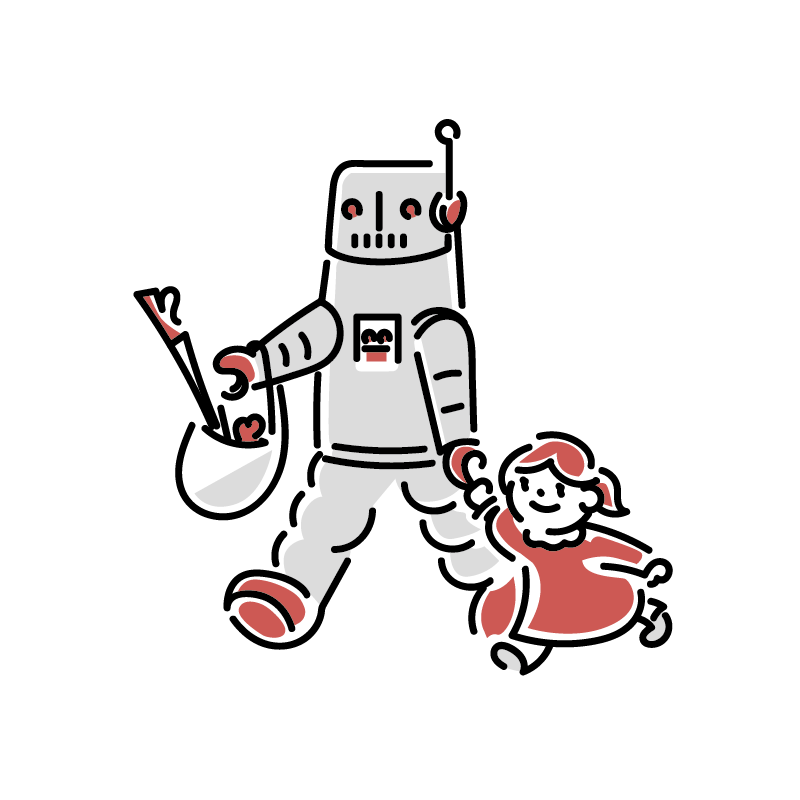
「OriHime」「Gita」障がい者の生活を変えるロボットまとめ
「OriHime」「Gita」障がい者の生活を変えるロボットまとめ
ロボット技術は介護者の負担をへらしたり、障がい者の生活を助けてくれます。さらに最近では、ロボット技術を活用して、寝たきりの人も働いて社会と交流ができるなど、さまざまな期待が高まる技術です。
現在、ロボット技術は障がい者の生活のあらゆる分野で導入されつつあります。
・移動支援
・食事支援
・入浴介助支援
・コミュニケーション支援
・就労支援
障がい者の生活や支援者を助けるロボット技術を、各分野ごとにご紹介しましょう。
移動支援ロボット
障がい者の移動支援に関わるロボットは、体に装着して正しい歩行をアシストするものや、自動的に追尾して荷物を運ぶものがあります。
HAL®自立支援用下肢タイプPro
https://www.cyberdyne.jp/products/fl05.html
茨城県にあるCYBERDYNE株式会社が製作する、装着型の歩行サポート機器です。下肢が動かしづらくなった人の歩行をアシストします。人が体を動かそうとするときに流れる微弱な信号を感知して機器が動くので、思い通りの歩行を可能にします。
キャリーロボット「Gita」
https://shop.mygita.com/
アメリカの企業Piaggio Fast Forwardが開発したキャリーロボット「Gita(ジーター)」。Gitaの中には荷物が入れられるようになっており、操作をしなくても自動的に持ち主の後ろをついていきます。
1度の充電で、約18キログラムの荷物を、約32キロメートル以上運ぶことが可能。身体が不自由な人も付き添いなしで買い物を楽しんだり、介助者の負担をへらしたりすることができます。
障害福祉サービスをお探しの方はこちら
食事支援に関わるロボット
手を使わなくても料理を自動で口元まで運んでくれるロボットも開発されています。完全な自立型ではありませんが、非常に簡単な操作でロボットを動かすことができ、障がい者も介助者なしで食事を楽しめるようになります。
マイスプーン
画像引用:News:セコムが日本初の食事支援ロボット「マイスプーン」を発表
https://www.secom.co.jp/personal/medical/myspoon.html
マイスプーンは、セコム株式会社が2002年に開発した、日本初の食事支援ロボット。B4サイズのコンパクト設計。食事を4つの区切りがあるトレイに盛り付け、あとはレバーやボタンを押すと、ロボットが付属のスプーンやフォークで料理をすくい上げて口元まで運びます。 スプーンは口元の前で停止するので、安全性にも配慮されています。
Obi
画像引用:料理を自動で口元まで運んでくれる食事介助ロボット「Obi」 - GIGAZINE
https://meetobi.com/
Obiはアメリカの企業Desin、LLCが開発した食事支援ロボットです。
ボタンやスイッチを押したり、息をふきかけたり、簡単な操作でアームを動かすことができます。四つに区切られたトレイは、食器洗浄機、電子レンジ、冷蔵・冷凍に対応。
アームは人間の手のように滑らかに動き、あらゆる形状の食べ物をすくって口元に運べます。価格は約45万円。日本への発送も可能です。
入浴介助支援ロボット
障がい者の入浴介助支援ロボットは、浴槽への出入りをサポートするものから、体を洗う機能まで実装されたロボットが開発されています。入浴の介助作業は体力がとても必要なので、ロボットが普及すると介護者の多くの負担をへらせます。
WLC:wellsリフトキャリー
画像引用:介護・自立支援設備「wells」
https://kaigoshien.com/index.html
積水テクノホーム株式会社が製作した「WLC:wellsリフトキャリー」は、浴槽への出入りと、脱衣所から浴室への出入りの動作をサポートします。
ボタンを押すだけで座面が昇降し、乗り換えることなく、浴槽に安全な姿勢で浸かることができます。そのため1人でも安心して入浴を楽しむことが可能になります。
アラエル
画像引用:アラエル | 酒井医療株式会社
https://www.sakaimed.co.jp/bath/sitting-bathing/araeru/
「アラエル」は、酒井医療が開発したシャワーロボットです。移動用の車いすをそのままドームの中に入れると、合計22基もついたシャワーノズルが全身をくまなく洗ってくれます。ウルトラファインバブルというマイクロ単位の泡を放出するので、汚れをしっかり落とし、肌のうるおいを保つ効果も。
操作は簡単で、「おまかせ洗身」ボタンをひとつ押すだけ。予洗いから洗い流しまで自動でおこないます。ドームの中は上から確認できるようになっているので、見守る介助者も安心です。
希望の条件を選んで障害福祉施設を検索
排泄支援ロボット
排泄支援ロボットには、排泄のタイミングを予測して知らせるタイプと、排泄物の処理をおこなうタイプが開発されています。
DFree(ディーフリー)
画像引用:DFree - 排泄予測デバイス/Toilet Timing Predicting Device
https://dfree.biz/
DFreeは、トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社が開発した、排泄を予測して知らせるロボット。下腹部に装着し、体内の動きを予知して、排尿のタイミングをスマートフォンに通知してくれます。
装着者は失禁などで不安になることはなく、出かけられるようになりますし、介助者も適切にトイレに誘導できるので、介助者の負担もへらせます。
水洗ポータブルトイレ キュレット
画像引用:キューレット 介護ロボット(排泄支援)水洗ポータブルトイレ
https://www.aronkasei.co.jp/sinjigyo/portable-toilet/
アロン化成株式会社が開発した「キュレット」は、排泄物を自動で処理してくれます。排泄物を直接下水道に流したり、密閉容器に溜めたりできるので、部屋のニオイが気になりにくくなります。また水道や床、壁の穴あけ工事は不要。重量も軽く、マンションにも設置できる設計です。
コミュニケーション・就労支援ロボット
ロボットは生活そのものだけではなく、障がい者に交流の場を提供したり、就労の可能性まで広げます。2021年8月には、障がい者が「分身ロボット」を操作して運営するカフェが話題になりました。
OriHime
画像引用:【追加募集】「分身ロボットカフェ DAWN ver.β」常設実験店、共に新しい働き方を開拓するOriHimeパイロットの追加募集を開始! | OryLab(オリィ研究所)テクノロジーの力で「不可能を可能に変えていく」
https://orihime.orylab.com/
オリィ研究所が開発したOriHime(オリヒメ)は、遠隔操作ができ、自由に動かせるロボットです。身振り手振りを操作できるので、人がその場にいるかのように感情表現を示せます。コミュニケーションに加えて、全身120㎝の体長で一定の動作ができるタイプも。
また視線やスイッチ1つで操作する機能も搭載。合成音声は本人に近いものを再現。寝たきりや重度障がい者の方も分身ロボットを通して、周囲と交流をしたり、就労したりと、さまざまな可能性が期待できるロボット技術です。
まとめ
ロボットは障がい者の生活だけではなく、コミュニケーションから就労の場まで、さまざまな可能性を広げてくれます。もっとロボット市場が盛り上がり、導入しやすい価格になると、障がい者の生活が大きく変化するでしょう。
障害福祉サービスをお探しの方はこちら
参考
後ろを付いてくる荷物運びロボット…競合は宅配ロボットではなく配車サービス | Business Insider Japan
障害分野におけるロボット等の導入促進に向けた調査研究事業 調査結果報告書
東京都障害者事例集.indd
日本橋にオープン、分身ロボットカフェの4つの魅力
障害者・高齢者を支援するロボット開発の現状と今後の展望

【令和3年度報酬改定】就労継続支援B型
【令和3年度報酬改定】就労継続支援B型
令和3年度の報酬改定における、就労継続支援B型の改定内容をまとめました。
就労継続支援B型の改定内容は、工賃の向上、障がい者の社会進出を目指すものとなっています。就労継続支援B型を運営されている事業所様はぜひご参考ください。
就労系に関する改定内容
就労継続支援B型ふくめ、就労系全体に関する主な改定内容をご説明いたします。
主な改定内容は、以下の3点になります。
・新型コロナウィルスの影響をふまえた実績の算出
・在宅サービス利用の要件の見直し
・一般就労への移行を促進
新型コロナウィルスの影響をふまえた実績の算出
令和3年度は、新型コロナウィルスの影響をふまえた実績の算出ができます。令和3年度の報酬算定は、令和元年度または令和2年度の実績を用いなくてもよいとされます。
就労継続支援B型の場合
※平均工賃月額に応じた報酬体系では、次のいずれかの年度の実績で評価
(Ⅰ)平成30年度
(Ⅱ)令和元年度
(Ⅲ)令和2年
在宅でのサービス利用の要件の見直し
令和3年度から、在宅でのサービス利用要件が緩和されます。
緩和された利用要件は以下です。
利用者要件
在宅でのサービス利用を希望しており、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者。
事業所要件
・ 在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。
・1日2回の連絡、助言または進捗状況の確認、日報作成を行うこと。作業活動、訓練等の内容などに応じ、1日2回を超えた対応を行うこと。
・緊急時の対応ができること。
・疑義照会等に対し、随時、訪問や連絡等による必要な支援が提供できる体制を確保すること。(ここまで現行と同じ)
・事業所職員による訪問、利用者の通所または電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を1週間につき1回は行うこと。
・原則、月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問または利用者による通所により、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価などをすること。
・1週間に1回の評価が通所により行われ、あわせて、月1回の訓練目標にたいする達成度の評価なども行われた場合、月1回おこなう評価などによる通所に置き換えてもよい。
・在宅と通所による支援を組み合わせることも可能。
一般就労への移行を促進
一般就労への移行に更なる評価があたえられます。就労継続支援から就労移行支援への移行については「就労移行連携加算」が新しく設けられました。
就労移行連携加算・・・ 1,000単位
①就労継続支援A型を受けたあとに、就労移行支援の支給決定を受けた者がいたとき、支給の申請の日までに、就労移行支援事業者との連絡調整や、相談援助などをおこなうこと。
②申請をおこなうとき、就労継続支援A型の支援の状況などを文書により相談支援事業者にたいして提供すること。
①②の条件を満たしているとき、1回に限り、所定単位数が加算されます。
一般就労への移行や工賃の向上を目指すため、施設外就労加算を廃止・再編。一般就労への移行実績が高い事業所や、高い工賃を実現する事業所、地域連携の取り組みへの評価に組み替えられます。そして一般就労への移行促進を見込んで、就労継続支援の福祉専門職員配置等加算における有資格者に「作業療法士」が新たに追加されます。
就労継続支援B型施設をお探しの方はこちらから
就労継続支援B型の報酬改定のおもな内容
・基本報酬の報酬体系を8段階へ
・「利用者の就労や生産活動などへの参加等」をもって一律評価する体系を新設
・「地域協働加算」と「ピアサポート実施加算」を新設
・身体拘束などの適正化
・医療連携体制加算の見直し
・福祉・介護職員等に関する加算の見直し
基本報酬の報酬体系を8段階へ
平均工賃月額が2万円未満の事業所が8割ある現状から、平均工賃月額に応じて支払われる基本報酬がより細かく区分されることになりました。
「5千円未満」の項目がなくなり、最低「1万円未満」という項目に。そして平均工賃金額が0.5万円ごとに、基本報酬の単位が決められます。
引用:【資料1】令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
また基本報酬はそれぞれ上がっており、たとえば平均工賃金額が1.5万円~2万円の事業所は、589単位→611単位に。22単位変わると大きなちがいですね。
高い工賃を支払う事業所には、さらに評価が上げられます。
「利用者の就労や生産活動などへの参加等」をもって一律評価する体系を新設
利用者の就労や生産活動などへの参加を支援した事業所を一律に評価する体系が新しく設けられました。
定員20人以下であり、従業員を7.5:1で配置した事業所は、556単位/日があたえられます。
「地域協働加算」と「ピアサポート実施加算」を新設
地域と連携した活動や、障がい者の就労・地域生活を支援した事業所にたいして、「地域協働加算」と「ピアサポート実施加算」の2つの加算が新設されます。
地域協働加算 ・・・30単位/日
利用者にたいして、地域や関係者と連携して支援(生産活動収入があるもの)をおこなうこと。さらに、その活動内容をインターネットなどを利用して公表した事業所に、支援を受けた利用者の数に応じて、1日につき30単位が加算されます。
ピアサポート実施加算 ・・・100単位/月
利用者にたいして、一定の支援体制のもと、就労や生産活動への参加などに関するピアサポートを実施した事業所へ、ピアサポートを受けた利用者の数に応じて、月単位で100単位加算されます。
(支援体制は、「障がい者ピアサポート研修」を修了した障がい者と管理者を配置すること。そして「障がい者ピアサポート研修」を修了した障がい者や管理者から、障がい者に関する研修が年に1回以上おこなわれていることが必須です。
なお、令和6年3月31日までは、都道府県や指定都市、中核市が上記の研修に準ずると認めた研修でも可、といった経過措置が設けられます。)
就労継続支援B型施設をお探しの方はこちらから
身体拘束などの適正化
事業の運営基準に、身体拘束に関する要件が追加されます。
①身体拘束をおこなうときは、必要な事項を記録すること。
②身体拘束の適正化のための対策検討委員会を開き、委員会の検討結果を徹底して従業員へ周知すること。
③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
④従業者へ、身体拘束等の適正化のための研修を定期的におこなうこと。
②~④は1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化されます。
①の運営基準を満たしていない事業所は「身体拘束廃止未実施減算」が適用され、基本報酬が減算されます。
②~④は令和5年4月以降から、身体拘束廃止未実施減算の要件に加えられます。
身体拘束廃止未実施減算・・・5単位/日
医療連携体制加算の見直し
医療連携体制加算の報酬単位は、医療的ケアがあるかどうか等で区分されるようになります。また、原則、利用者を診察している主治医から個別に受けるものを「医師からの指示」とすることが決められます。
看護職員が看護する利用者
単位数
医療連携体制加算(Ⅰ)
32単位
医療連携体制加算(Ⅱ)
63単位
医療連携体制加算(Ⅲ)
125単位
医療連携体制加算(Ⅳ)
1人
800単位
2人
500単位
3人以上8人以下
400単位
医療連携体制加算(Ⅴ)
500単位
医療連携体制加算(Ⅵ)
100単位
福祉・介護職員処遇改善加算・処遇改善特別加算の見直し
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)と、福祉・介護職員処遇改善特別加算は廃止されます。
(令和3年3月末時点で同加算が算定されている障害福祉サービス等事業所は、1年間の経過措置を設けられます。)
また加算率の算定方法は、障害福祉サービス等経営実態調査にある従業者数や報酬請求事業所数を用いて、加算率が算定されることに。
類似する複数のサービスはグループ分けして、以下の通りに加算率が算定されます。
(Ⅰ)所定単位数× 5.4%
(Ⅱ)所定単位数× 4.0%
(Ⅲ)所定単位数× 2.2%
※指定障害者支援施設の場合
(Ⅰ)所定単位数× 6.7%
(Ⅱ)所定単位数× 4.7%
(Ⅲ)所定単位数× 2.6%
(Ⅳ)(Ⅲ)の90/100
(Ⅴ)(Ⅲ)の80/100
職場環境要件も変更されました。職場環境の改善につながる取り組みは、当該年度に実施することを求められます。
ただし、継続して処遇改善加算を取得している事業所は、当該年度に実施できない正当な理由がある場合、例外的に前年度の取り組み実績で要件を満たすことができます。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールについて、より柔軟な配分をできるようにするため、「経験・技能のある障害福祉人材」は「ほかの障害福祉人材」の「2倍以上とすること」としているルールを、「より高くすること」に見直されます。
また福祉・介護職員等処遇改善加算と同じく、類似している複数のサービスはグループ分けして、加算率が設定されます。
(Ⅰ)所定単位数× 1.7%
(Ⅱ)所定単位数× 1.5%
指定障害者支援施設の加算率は、「所定単位数× 1.8%」です。
まとめ
就労継続支援B型の令和3年度報酬改定では、これまで工賃を比較的高めに設定していた事業所が正しく評価され、障がい者が働くために、給与や環境をもっと良くすることができるようになります。この報酬改定を機にサービスの向上を目指しましょう。
また全サービスに関わる報酬改定の内容は別記事にまとめていますので、ご参考ください。
https://www.minnanosyougai.com/article1/%e3%80%90%e4%bb%a4%e5%92%8c3%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%a6%8f%e7%a5%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%80%91%e5%85%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93/
就労継続支援B型施設をお探しの方はこちらから
<<参考>>
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
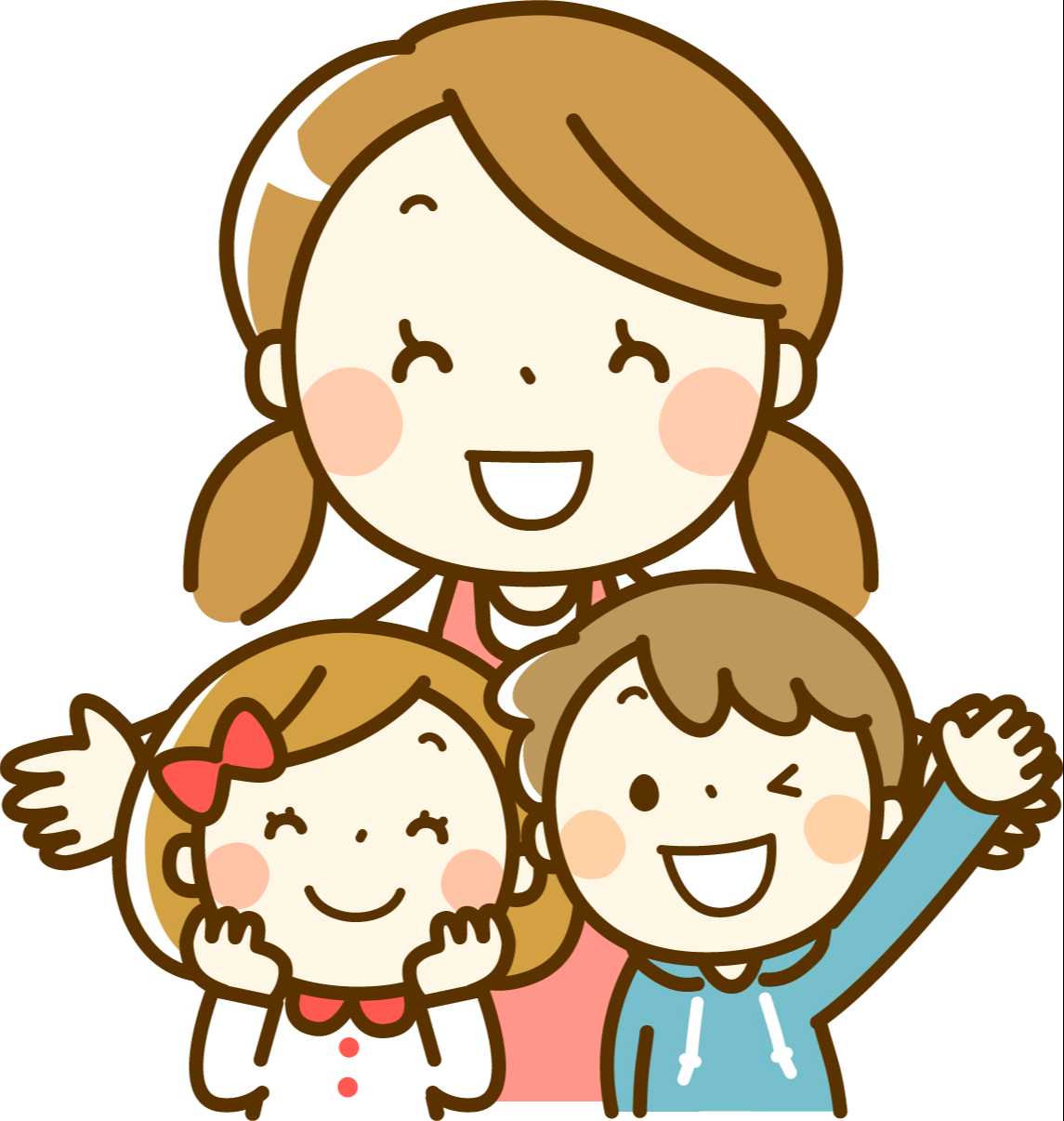
【令和3年度報酬改定】放課後等デイサービス
【令和3年度報酬改定】放課後等デイサービス
放課後等デイサービスの令和3年度障害福祉報酬改定では、区分制が廃止され、加算が多く新設されるなど、よりサービスの専門性を高めることが求められます。
令和3年2月4日に発表された、報酬改定のおもな内容をまとめたので、ご参考ください。
放課後等デイサービスのおもな改定内容
今回の改定で変更されていない点は除き、令和3年度報酬改定の内容をご説明いたします。
放課後等デイサービスのおもな改定内容は以下になります。
・「医療的ケア児の支援」の支援を充実
・基本報酬・加算の大きな見直し
・医療連携体制加算の見直し
・30分以下のサービスの報酬の見直し
・専門的支援加算の対象に「5年以上児童福祉事業に従事した保育士」を追加
・従業者要件に「障害福祉サービス経験者」を廃止
・家族支援の評価を充実
・身体拘束の適正化
・福祉・介護職員等に関する加算の見直し
「医療的ケア児の支援」を充実
令和3年度の報酬改定から、動ける医療的ケア児にたいして、一般の子どもたちとは別に、基本報酬が設定されるようになります。
また、動ける医療的ケア児を対象とするスコア制が導入されました。
引用:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な内容
新スコア3点以上の児童 …3:1
新スコア16~31点以下の児童 …2:1
新スコア32点以上の児童 …1:1
以上のように、ケアに必要な看護職員の数を配置した場合に応じて金額が給付されます。
さらに、この制度にあわせて看護職員加配加算の要件も緩和されました。おもに重症心身障がい児が通う事業所は、人数による加算ではなくなり、「その事業所の医療的ケア児の合計点数が40点以上」の場合に加算されることに。これにより、少数の医療的ケア児をサポートしていた施設も加算があたえられるようになりますね。
基本報酬・加算の大きな見直し
引用:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
現行の2区分制が廃止され、基本報酬が見直されます。
加算は①児童指導員等加配加算、②個別サポート加算Ⅰ、③個別サポート加算Ⅱ、④専門的支援加算の4つになります。
児童指導員等加配加算
理学療法士や児童指導員などの専門職に、「手話通訳士」「手話通訳者」が追加されます。
個別サポート加算Ⅰ
重度および行動上の課題のある、ケアニーズの高い児童への支援を評価する加算です。ケアニーズの高い児童の判断には、指標該当児の判定スコアを用いる方向です。
個別サポート加算Ⅱ
虐待(ネグレクトなど)を受けた児童へ、公的機関や医師と連携して支援した場合に評価される加算です。虐待児童が在籍している人数に応じて加算されます。
専門的支援加算
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、国リハ視覚障害学科履修者など専門の資格者を常勤として1以上配置したときに評価されます。
また専門的支援加算の対象に、「5年以上児童福祉事業に従事した保育士や保育指導員」が追加されます。
医療連携体制加算の見直し
医療連携体制加算の算定要件や報酬が見直されました。
医療連携体制加算の報酬単位は、医療的ケアがあるかどうか等で区分されるようになります。また、原則、利用者を診察している主治医から個別に受けるものを「医師からの指示」とすることが決められます。
看護職員が看護する人数
単位数
医療連携体制加算(Ⅰ)
32単位
医療連携体制加算(Ⅱ)
63単位
医療連携体制加算(Ⅲ)
125単位
医療連携体制加算(Ⅳ)
1人
800単位
2人
500単位
3人以上8人以下
400単位
医療連携体制加算(Ⅴ)
(4時間以上)
1人
1600単位
2人
960単位
3人以上8人以下
800単位
医療連携体制加算(Ⅵ)
500単位
医療連携体制加算(Ⅶ)
100単位
30分以下のサービスの報酬について
基本的に、30分以下といった短時間のサービスは基本報酬や加算として算定されません。
しかし放課後等デイサービス計画にしたがって、少しずつ在所する時間をふやしていく必要がある、と市町村が認めた児童は、短時間のサービスも基本報酬や加算に含めてもよいとされます。また児童が体調不良などで、結果的にサービスが30分以下となったときの加算が新設されました。
欠席時対応加算Ⅱ・・・94単位/回
従業者要件の見直し
基本報酬の人員の要件から、「障害福祉サービス経験者」が廃止されます。
2021年3月までに開所した事業所は2年間の経過措置をとられますが、2021年4月から開所する事業所は、「障害福祉サービス経験者」は基準人員として認められません。保育士・児童指導員のみ、人員基準として認められます。
放課後等デイサービスをお探しの方はこちらから
家庭支援の評価を充実
訪問支援特別加算を家庭連携加算に統合し、要件が見直されました。
事業所内相談支援加算については、個別の相談援助だけでなく、グループでの面談も加算の対象になります。
家庭連携加算(月4回が限度)
1時間未満・・・187単位/回
1時間以上・・・280単位/回
事業所相談支援加算(Ⅰ・Ⅱそれぞれ月1回が限度)
加算Ⅰ(個別)・・・100単位/回
加算Ⅱ(グループ)・・・80単位/回
身体拘束の適正化
事業の運営基準に、身体拘束に関する要件(以下の②~④)が追加されます。
①身体拘束をおこなうときは、その態様や時間、利用者の心身の状況、やむを得ない理由、そのほか必要な事項を記録すること。(現行のまま)
②身体拘束の適正化のための対策検討委員会を開き、委員会の検討結果を徹底して従業員へ周知すること。
③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
④従業者へ、身体拘束等の適正化のための研修を定期的におこなうこと。
②~④は1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化されます。
①の運営基準を満たしていない事業所は「身体拘束廃止未実施減算」が適用され、基本報酬が減算されます。
②~④は令和5年4月以降から、身体拘束廃止未実施減算の要件に加えられます。
身体拘束廃止未実施減算・・・5単位/日
福祉・介護職員処遇改善加算・処遇改善特別加算の見直し
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)と、福祉・介護職員処遇改善特別加算は廃止されます。
(令和3年3月末時点で同加算が算定されている障害福祉サービス等事業所は、1年間の経過措置を設けられます。)
また加算率の算定方法は、障害福祉サービス等経営実態調査にある従業者数や報酬請求事業所数を用いて、加算率が算定されることになります。
類似する複数のサービスはグループ分けして加算率が算定されます。
(Ⅰ)所定単位数× 8.6%
(Ⅱ)所定単位数× 6.1%
(Ⅲ)所定単位数× 3.4%
職場環境要件も変更されました。職場環境の改善につながる取り組みは、当該年度に実施することを求められます。ただし、継続して処遇改善加算を取得している事業所は、当該年度に実施できない正当な理由がある場合、例外的に前年度の取り組み実績で要件を満たすことができます。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールが、より柔軟な配分をできるようにするため、見直されました。
「経験・技能のある障害福祉人材」は「ほかの障害福祉人材」の「2倍以上とすること」としているルールが、「より高くすること」に変わります。
また福祉・介護職員等処遇改善加算と同じく、類似している複数のサービスはグループ分けし、加算率を設定。放課後等デイサービスの加算率は以下になります。
(Ⅰ)所定単位数× 1.3%
(Ⅱ)所定単位数× 1.0%
まとめ
令和3年度障害福祉報酬改定では、放課後等デイサービスの基本報酬や加算などが大きく見直されました。とくに区分制の廃止は大きな変化です。
令和3年度4月1日までに、新しい重要事項説明書や契約書を用意し、利用者と再締結をしたり、新しい計画書や届け出を作成したりと、事務的な準備が必要になりますね。
このほか全サービスに関わる報酬改定の内容は別記事にまとめたので、ご覧ください。
https://www.minnanosyougai.com/article1/%e3%80%90%e4%bb%a4%e5%92%8c3%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%a6%8f%e7%a5%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%80%91%e5%85%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93/
放課後等デイサービスをお探しの方はこちらから
<<参考>>
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

【令和3年度報酬改定】児童発達支援
【令和3年度報酬改定】児童発達支援
令和3年度の障害福祉報酬改定は、児童発達支援事業所に専門的なサービスを求める動きとなっています。
令和3年度2月4日に発表された、児童発達支援にかかわる報酬改定の内容をまとめました。
児童発達支援事業所のおもな改定内容
児童発達支援事業所のおもな改定内容は以下のとおりです。
・「医療的ケア児の支援」の支援を充実
・加算の見直し
・専門的支援加算の対象に「5年以上児童福祉事業に従事した保育士・児童指導員」を追加
・従業者要件に「障害福祉サービス経験者」を廃止
・家族支援の評価を充実
・身体拘束の適正化
・福祉・介護職員等に関する加算の見直し
「医療的ケア児の支援」を充実
2021年の報酬改定から、動ける医療的ケア児にたいして、一般の子どもたちと別に、基本報酬が設定されるようになります。また、動ける医療的ケア児にスコア制が導入されました。
引用:https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000653734.pdf
新スコア3点以上の児童 …3:1
新スコア16~31点以下の児童 …2:1
新スコア32点以上の児童 …1:1
以上のように、ケアに必要な看護職員の数を配置した場合に応じて、金額が給付されます。この制度にあわせて、看護職員加配加算の要件も緩和されます。おもに重症心身障がい児が通う事業所は、人数による加算ではなくなり、「その事業所の医療的ケア児の合計点数が40点以上」の場合に加算されることになりました。これにより、ごく少数の医療的ケア児をケアしていた施設も、加算があたえられるようになります。
加算の見直し
児童指導員等加配加算Ⅱが廃止され、①児童指導員等加配加算、②個別サポート加算Ⅰ、③個別サポート加算Ⅱ、④専門的支援加算の4つになります。
引用:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
児童指導員等加配加算
理学療法士や児童指導員などの専門職に、「手話通訳士」および「手話通訳者」が追加されます。
個別サポート加算Ⅰ
重度および行動上の課題のある、ケアニーズの高い児童への支援にたいする報酬加算。ケアニーズの高い児童の判断基準は、5領域11項目の調査を用いる方向です。
個別サポート加算Ⅱ
虐待(ネグレクトなど)を受けた児童への支援にたいする報酬加算。虐待児童が在籍している人数に応じて加算。
専門的支援加算
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、国リハ視覚障害学科履修者など専門の資格者を常勤として1以上配置したときに評価。
また専門的支援加算に、「5年以上児童福祉事業に従事した保育士・児童指導員」が追加されます。
医療連携体制加算の見直し
医療連携体制加算の算定要件や報酬が大きく見直されました。
医療連携体制加算の報酬単位は、医療的ケアがあるかどうか等で区分されるようになります。また原則、利用者を診察している主治医から個別に受けるものを「医師からの指示」とすることを明確にしなくてはいけません。
児童発達支援は、月当たりの利用者数が一定数以上の場合、医療的ケア児の基本報酬を算定します。
看護職員が看護する利用者
単位数
医療連携体制加算(Ⅰ)
32単位
医療連携体制加算(Ⅱ)
63単位
医療連携体制加算(Ⅲ)
125単位
医療連携体制加算(Ⅳ)
1人
800単位
2人
500単位
3人以上8人以下
400単位
医療連携体制加算(Ⅴ)
(4時間以上)
1人
1600単位
2人
960単位
3人以上8人以下
800単位
医療連携体制加算(Ⅵ)
500単位
医療連携体制加算(Ⅶ)
100単位
従業者要件の見直し
基本報酬の人員の要件から、「障害福祉サービス経験者」が廃止されます。
2021年3月までに開所した事業所は2年間の経過措置をとられますが、2021年4月から開所する事業所は、「障害福祉サービス経験者」が基準人員として認められません。保育士・児童指導員のみが人員基準として認められます。
家庭支援の評価を充実
訪問支援特別加算を家庭連携加算に統合するうえ、要件が見直されました。
事業所内相談支援加算については、個別の相談援助だけでなく、グループでの面談も加算の対象になります。
家庭連携加算(月4回が限度)
1時間未満・・・1回につき187単位
1時間以上・・・1回につき280単位
事業所相談支援加算(Ⅰ・Ⅱそれぞれ月1回が限度)
加算Ⅰ(個別)・・・1回につき100単位
加算Ⅱ(グループ)・・・1回につき80単位
児童発達支援サービスをお探しの方はこちらから
身体拘束などの適正化
事業の運営基準に、身体拘束に関する要件が追加されます。
①身体拘束をおこなうときは、必要な事項を記録すること。
②身体拘束の適正化のための対策検討委員会を開き、委員会の検討結果を徹底して従業員へ周知すること。
③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
④従業者へ、身体拘束等の適正化のための研修を定期的におこなうこと。
②~④は1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化されます。
①の運営基準を満たしていない事業所は「身体拘束廃止未実施減算」が適用され、基本報酬が減算されます。
②~④は令和5年4月以降から、身体拘束廃止未実施減算の要件に加えられます。
身体拘束廃止未実施減算・・・5単位/日
福祉・介護職員処遇改善加算・処遇改善特別加算の見直し
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)と、福祉・介護職員処遇改善特別加算は廃止されます。
令和3年3月末時点で同加算が算定されている障害福祉サービス等事業所は、1年間の経過措置を設けられます。
また加算率の算定方法は、障害福祉サービス等経営実態調査にある従業者数や報酬請求事業所数を用いて、加算率が算定されることに。
類似する複数のサービスはグループ分けして加算率が算定されます。
(Ⅰ)所定単位数× 8.1%
(Ⅱ)所定単位数× 5.9%
(Ⅲ)所定単位数× 3.3%
職場環境要件も変更されました。職場環境を整えるための取り組みは、当該年度に実施することを求められます。ただし、継続して処遇改善加算を取得している事業所は、当該年度に実施できない正当な理由がある場合、例外的に前年度の取り組み実績で要件を満たすことができます。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し
引用:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールについて、より柔軟な配分をできるようにするため、「経験・技能のある障害福祉人材」は「ほかの障害福祉人材」の「2倍以上とすること」としているルールを、「より高くすること」に見直されます。
また福祉・介護職員等処遇改善加算と同じく、類似している複数のサービスはグループ分けし、以下の通りに加算率が決められました。
(Ⅰ)所定単位数× 1.3%
(Ⅱ)所定単位数× 1.0%
まとめ
2021年の報酬改定では、医療的ケア児やケアニーズの高い児童の支援が重視されたり、児童指導員等加配加算に「手話通訳士」が追加されたりするなど、サービスの専門性を高めることが求められています。
児童福祉事業を5年以上経験している保育士や専門職を雇い、サービスの専門性を高める、人事的な対策が必要でしょう。
全サービスに共通する報酬改定の内容は、別記事にまとめているのでご参考ください。
https://www.minnanosyougai.com/article1/%e3%80%90%e4%bb%a4%e5%92%8c3%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%a6%8f%e7%a5%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%80%91%e5%85%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93/
児童発達支援サービスをお探しの方はこちらから
<<参考>>
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

【令和3年度報酬改定】就労移行支援
【令和3年度報酬改定】就労移行支援
令和3年度障害福祉報酬改定では、就労定着率が高い就労移行支援事業所は基本報酬が上がったり、就労定着率を決める期間が約半年から約1年半に変わったりするなど、事業所がより良いサービスを提供できるように改定されています。
令和3年2月4日に発表された、就労移行支援の令和3年度報酬改定のおもな内容をまとめました。
就労系に関する改定内容
就労系全体に関する改定内容をご説明いたします。
改定内容は以下のとおりです。
・新型コロナウィルスの影響をふまえた実績の算出
・在宅サービス利用の要件の見直し
・一般就労への移行を促進
新型コロナウィルスの影響をふまえた実績の算出
新型コロナウィルスの影響をふまえた実績の算出ができます。令和3年度の報酬算定は、令和元年度または令和2年度の実績を用いなくてもよいとされます。
就労移行支援
次のいずれか2カ年度間の実績で評価
(Ⅰ)令和元年度及び令和2年度
(Ⅱ)平成30年度及び令和元年度
在宅でのサービス利用の要件の見直し
令和3年度から、在宅でのサービス利用要件が緩和されます。
利用者要件
在宅でのサービス利用を希望しており、在宅でのサービス利用による支援効果があると市町村が認めた利用者。
事業所要件
・ 在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。
・1日2回の連絡、助言または進捗状況の確認、日報作成を行うこと。作業活動、訓練等の内容などに応じ、1日2回を超えた対応を行うこと。
・緊急時の対応ができること。
・疑義照会等に対し、随時、訪問や連絡等による必要な支援が提供できる体制を確保すること。(ここまで現行と同じ)
・事業所職員による訪問、利用者の通所または電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を1週間につき1回は行うこと。
・原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問または利用者による通所により、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価などをすること。
・1週間に1回の評価が通所により行われ、あわせて、月1回の訓練目標にたいする達成度の評価なども行われた場合、月1回おこなう評価などによる通所に置き換えてもよい。
・在宅と通所による支援を組み合わせることも可能。
一般就労への移行を促進
一般就労への移行に更なる評価があたえられます。また一般就労への移行や工賃の向上を目指すため、施設外就労加算を廃止・再編。一般就労への移行実績が高い事業所や、高い工賃を実現する事業所、地域連携の取り組みへの評価に組み替えられます。
就労移行支援の改定内容
就労移行支援の改定内容は以下になります。
・基本報酬の見直し
・就労定着率の算出方法を変更
・支援計画会議実施加算を新設
・医療連携体制加算の見直し
・就労移行支援員の人員基準を緩和
・身体拘束などの適正化
・福祉・介護職員等に関する加算の見直し
基本報酬の見直し
就労定着率が低い事業所は基本報酬が下がり、就労定着率が高い事業所はさらに評価が上がる、というかたちになっています。就労定着率の向上を目指して、より励むことが求められています。
画像:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
就労定着率の算出方法を変更
基本報酬の区分にかかわる就労定着率。改定前は、「前年度の利用定員÷前年度就労を継続している人の数」と算出していましたが、改定後は2年間に引き延ばされ、「前年度と前々年度の利用定員÷前年度と前々年度、就労を継続している人数」に変更されます。就労定着率が決まる期間が、半年から1年半に伸びることになるので、余裕が出てきますね。
支援計画会議実施加算の新設
地域のノウハウを活用し、アセスメントの質を高めるため、「支援計画会議実施加算」が新設されました。
施設利用者の就労移行支援計画の作成や見直しのとき、外部の関係者を交えた会議をおこない、関係者の専門的な意見を求め、就労移行支援計画の作成や見直しをしたとき、1か月に1回(年4回が限度)、「支援計画会議実施加算」があたえられます。
支援計画会議実施加算・・・583単位
就労移行支援施設をお探しの方はこちらから
医療連携体制加算の見直し
医療連携体制加算の報酬単位は、医療的ケアがあるかどうか等で区分されるようになります。また、原則、利用者を診察している主治医から個別に受けるものを「医師からの指示」とすることが決められます。
看護職員が看護する利用者
単位数
医療連携体制加算(Ⅰ)
32単位
医療連携体制加算(Ⅱ)
63単位
医療連携体制加算(Ⅲ)
125単位
医療連携体制加算(Ⅳ)
1人
800単位
2人
500単位
3人以上8人以下
400単位
医療連携体制加算(Ⅴ)
500単位
医療連携体制加算(Ⅵ)
100単位
就労移行支援員の人員基準を緩和
現行では、常勤換算方法で「利用者の数÷15」をした数以上を配置し、うち1人以上は常勤でなければいけない、としていました。この「うち1人以上は常勤でなければいけない」という条件がなくなります。
身体拘束の適正化
事業の運営基準に、身体拘束に関する要件が追加されます。
①身体拘束をおこなうときは、その態様や時間、利用者の心身の状況、やむを得ない理由、そのほか必要な事項を記録すること。
②身体拘束の適正化のための対策検討委員会を開き、委員会の検討結果を徹底して従業員へ周知すること。
③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
④従業者へ、身体拘束等の適正化のための研修を定期的におこなうこと。
②~④は1年間の準備期間を設け、令和4年度から義務化されます。
①の運営基準を満たしていない事業所は「身体拘束廃止未実施減算」が適用され、基本報酬が減算されます。
②~④は令和5年4月以降から、身体拘束廃止未実施減算の要件に加えられます。
身体拘束廃止未実施減算・・・5単位/日
福祉・介護職員処遇改善加算・処遇改善特別加算の見直し
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)と、福祉・介護職員処遇改善特別加算は、1年間の経過措置を設けて廃止されます。
また加算率の算定方法は、障害福祉サービス等経営実態調査にある従業者数や報酬請求事業所数を用いて、加算率が算定されることになります。類似する複数のサービスはグループ分けし、加算率が算定されます。
就労移行支援の加算率は以下のように見直されました。
(Ⅰ)所定単位数× 6.4%
(Ⅱ)所定単位数× 4.7%
(Ⅲ)所定単位数× 2.6%
※指定障害者支援施設の場合
(Ⅰ)所定単位数× 6.4%
(Ⅱ)所定単位数× 4.9%
(Ⅲ)所定単位数× 2.7%
(Ⅳ)(Ⅲ)の90/100
(Ⅴ)(Ⅲ)の80/100
職場環境要件も変更されました。職場環境の改善につながる取り組みは、当該年度に実施することを求められます。ただし、継続して処遇改善加算を取得している事業所は、当該年度に実施できない正当な理由がある場合、例外的に前年度の取り組み実績で要件を満たすことができます。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールが変更されます。「経験・技能のある障害福祉人材」は「ほかの障害福祉人材」の「2倍以上とすること」としているルールを、「より高くすること」に見直されました。
また福祉・介護職員等処遇改善加算と同じく、類似している複数のサービスはグループ分けし、加算率が設定されます。
(Ⅰ)所定単位数× 1.7%
(Ⅱ)所定単位数× 1.5%
指定障害者支援施設の場合は、(1月につき +所定単位数×1.8)が加算率になります。
まとめ
就労移行支援の令和3年度障害福祉報酬改定では、就労定着率の高い事業所はさらに評価されます。また、就労定着率が決まる期間が半年から約1年半と伸ばされたので、事業所は余裕をもって障がい者をサポートできるようになります。
このほか全サービスに関わる報酬改定の内容は別記事にまとめたので、ご参考ください。
https://www.minnanosyougai.com/article1/%e3%80%90%e4%bb%a4%e5%92%8c3%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%a6%8f%e7%a5%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e5%a0%b1%e9%85%ac%e6%94%b9%e5%ae%9a%e3%80%91%e5%85%a8%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93/
就労移行支援施設をお探しの方はこちらから
<<参考>>
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容