NewsNewsみんなの障がいニュース
みんなの障がいニュースは、最新の障がいに関する話題や時事ニュースを、
コラム形式でわかりやすくお届けします。
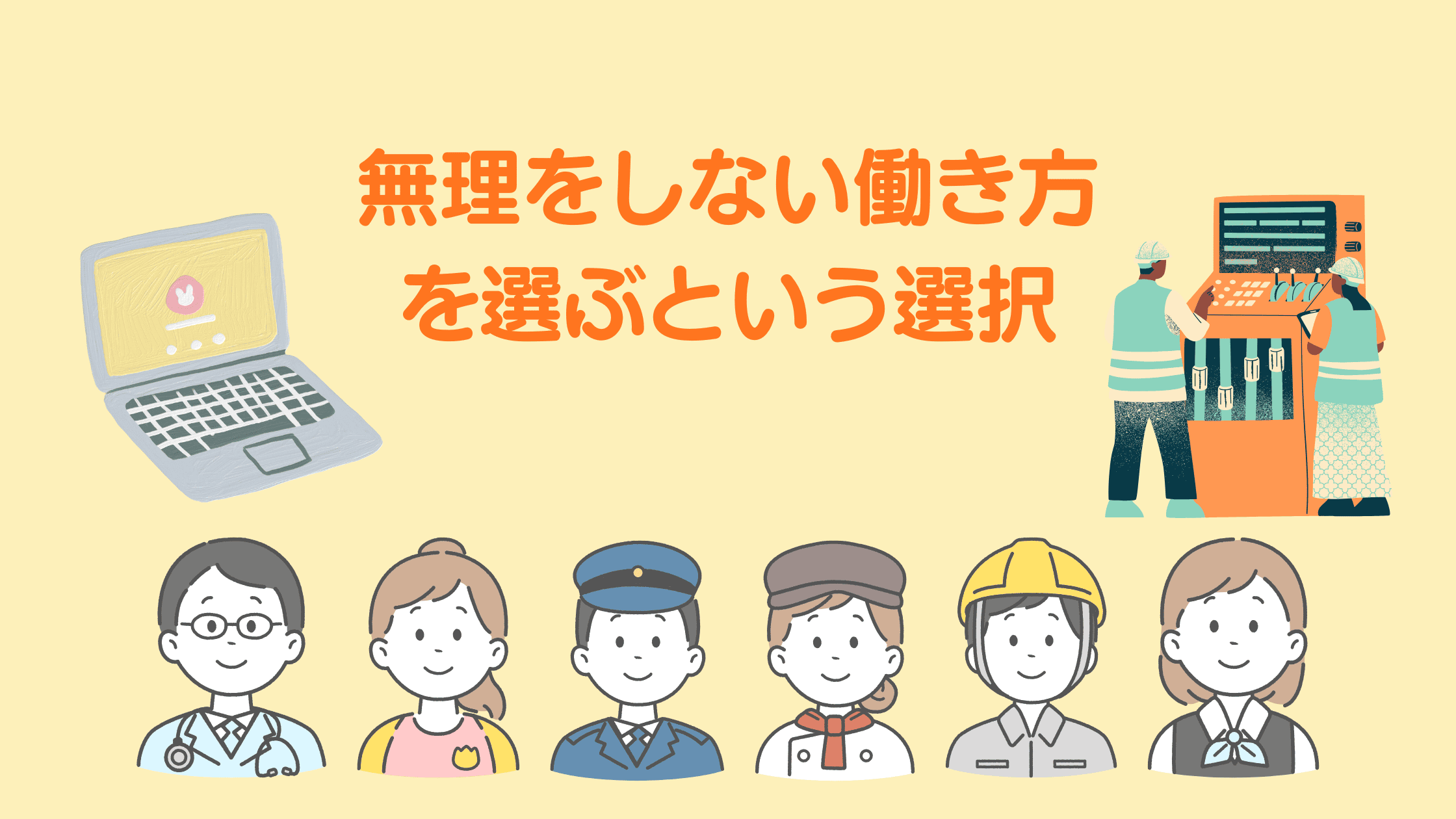
- 精神障がい
- 仕事
無理をしない働き方を選ぶという選択
「働かなきゃいけないのは分かっているけれど、正直しんどい」「仕事のことを考えるだけで、気持ちが重くなる」
精神障がいがある人にとって、仕事は生活の手段であると同時に、こころの負担になりやすいものでもあります。この記事では、「頑張れる仕事」を探すのではなく、こころを削られにくい仕事の考え方を軸に、障がいのある人が無理をしない働き方を選ぶヒントをお伝えします。
「こころの負担が少ない仕事」とは何か
仕事の大変さは、人によって違う
一般的に「楽そう」「安定している」と言われる仕事でも、障がいの特性によっては大きなストレスになることがあります。一方で、周囲が大変だと思う仕事でも、本人にとっては心地よく続けられる場合もあります。
大切なのは、仕事内容そのものよりも、環境や関わり方が自分に合っているかどうかです。
こころの負担になりやすい要素
精神障がいのある人が仕事で消耗しやすいのは、能力不足ではなく、次のような要素が重なったときです。
・人間関係のストレスが強い・常に急かされる、臨機応変さを求められる・評価基準が曖昧・体調や気分の波を考慮されない
これらが少ない仕事ほど、こころの負担は軽くなりやすいと言えます。
精神障がいのある人が「楽に感じやすい」仕事の共通点
人との距離が調整しやすい
常に誰かと会話し続ける仕事は、精神的な疲労が溜まりやすくなります。一方で、一人作業が多い、会話が業務連絡中心の仕事は、気持ちを消耗しにくい傾向があります。
在宅ワークや、黙々と進める作業が向いている人も多いです。
作業内容がある程度決まっている
毎日違う判断を求められる仕事よりも、手順が決まっている仕事のほうが安心感を持って取り組めます。「何をすればいいか分かっている」という状態は、こころを安定させる大きな要因です。
成果が目に見えやすい
自分のやったことが形として残る仕事は、達成感を得やすく、自己否定に陥りにくくなります。小さな成功体験が積み重なることで、「働いても大丈夫かもしれない」という感覚が育っていきます。
こころの負担が少ないと感じやすい仕事の例
パソコン作業・データ入力
納期や量の調整がしやすく、対人関係が比較的少ない仕事です。在宅で行える場合もあり、体調に合わせて働き方を調整しやすいのが特徴です。
清掃・軽作業
決まった作業を繰り返す仕事は、考えすぎずに済みます。人とのやりとりが最低限で済む点も、こころの負担を軽くしてくれます。
文章・創作系の仕事
自分のペースで進められる仕事は、気分の波がある人に向いています。完璧を求めすぎず、「できるときにできる分だけ」という関わり方が可能です。
※大切なのは職種名ではなく、「その仕事をどんな環境で、どんな条件で行うか」です。
無理をしないために大切な考え方
「できるかどうか」より「続けられるか」
一時的に頑張れる仕事より、長く続けられる仕事のほうが、結果的に生活とこころを守ってくれます。
「週5フルタイムでなければ意味がない」という考え方から、一度距離を取ってみてもいいのです。
調子が悪くなる前提で考える
障がいがある人の多くは、体調や気分に波があります。だからこそ、「調子が悪い日でも続けられるか」を基準に仕事を考えることが重要です。
休める、相談できる、量を調整できる。その余白があるかどうかが、働き続けられるかを左右します。
「働けない自分」を責めなくていい
仕事が合わない=あなたがダメではない
仕事を続けられなかった経験があると、「自分は社会不適合なんじゃないか」と感じてしまうことがあります。
でもそれは、仕事と特性の相性が合わなかっただけかもしれません。
立ち止まるのも選択のひとつ
今は働く余裕がない、という時期があっても大丈夫です。休むことは逃げではなく、回復のための行動です。
まとめ:こころを守れる働き方は、ちゃんとある
障がいがあるからといって、一生しんどい働き方を選ばなければならないわけではありません。
・こころの負担が少ない環境・自分のペースを尊重できる仕事・「できない日」があっても許される余白
そうした条件がそろうだけで、働くことは少しずつ「怖いもの」から「現実的な選択」に変わっていきます。
あなたが守るべき一番大切なものは、成果でも評価でもなく、あなた自身のこころです。
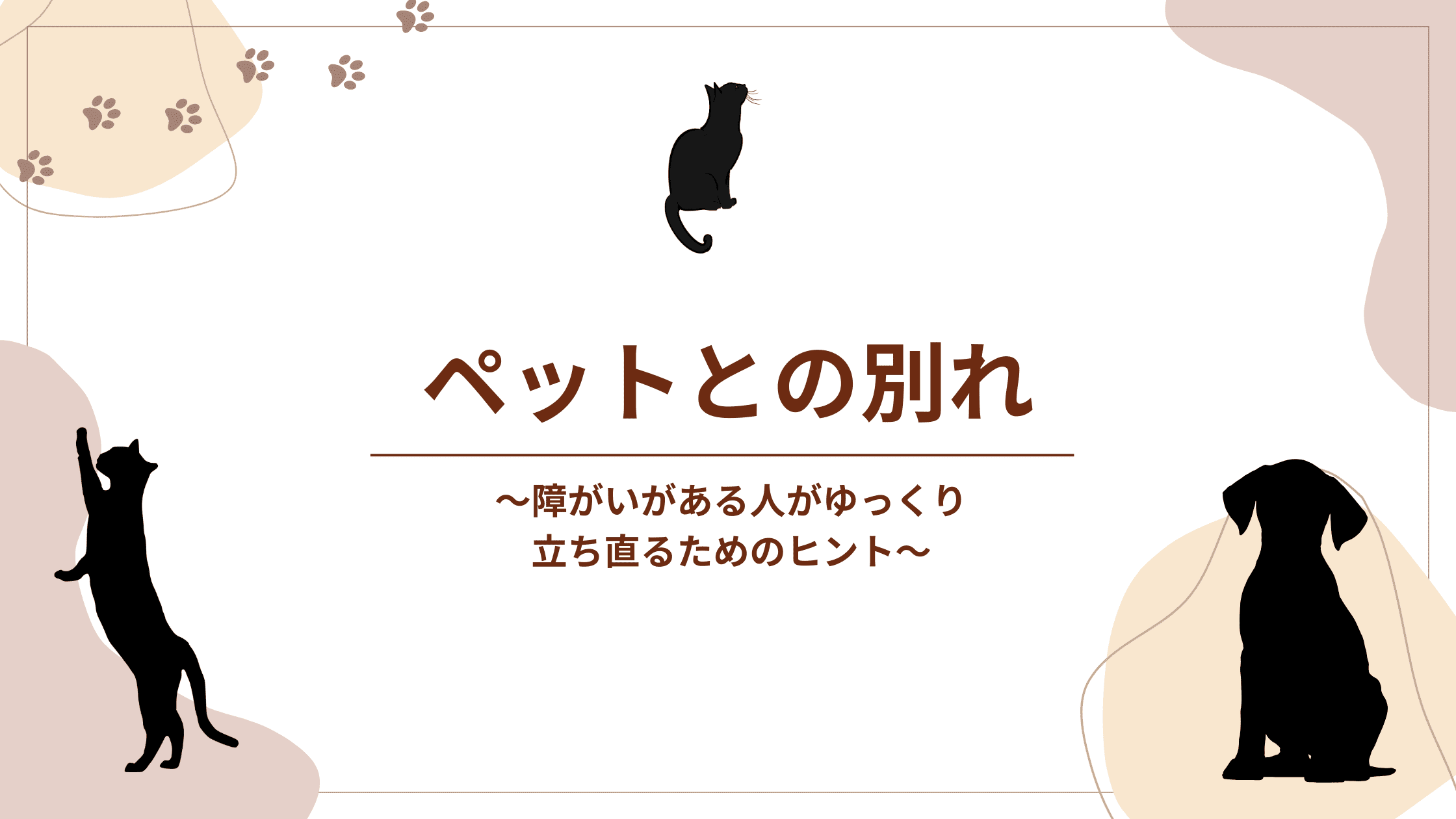
- ペット
- 精神障がい
- 発達障がい
- 感覚過敏
ペットとの別れ~障がいがある人がゆっくり立ち直るためのヒント~
ペットとの別れは誰にとってもつらい出来事です。けれど、障がいがある人にとってその喪失は周囲が想像する以上に深く、長く心に影を落とすことがあります。
「たかがペットでしょ」「また飼えばいいじゃない」
そんな言葉に、さらに傷ついてしまった経験がある人もいるかもしれません。この記事では、ペットとの別れがなぜこれほど苦しくなるのか、そして障がいがある人がその悲しみとどう向き合えばいいのかを、無理に前向きにならなくてもいい視点で整理していきます。
ペットは「家族」以上の存在
自分を支えてくれた存在
障がいがある人にとって、ペットは単なる癒しではありません。毎日の生活リズムを整えてくれたり、外に出るきっかけになってくれたり、言葉がなくてもそばにいてくれる存在です。
体調が悪い日も、気分が落ち込んだ日も、「何も説明しなくていい相手」として寄り添ってくれた――そんな関係性だった人も多いでしょう。
「役割」をくれていた存在
ペットの世話をすることは、「自分が生きる理由」「自分が必要とされている感覚」につながることがあります。
特に、仕事や社会参加が制限されがちな状況では、ペットとの関係が自己肯定感を支える大切な柱になっていたケースも少なくありません。
その存在を失うことは心の支えと日常の一部を同時に失うことでもあるのです。
障がいがあるからこそ、喪失が大きくなる理由
感覚や感情の受け取り方が強い
発達障がいや精神障がいのある人の中には、感情や感覚を人一倍強く受け取る特性を持つ人もいます。
その分、愛情も深く、別れの痛みも鋭く、長く残りやすいのです。
「いつまでも引きずっている自分がおかしいのでは」と感じる必要はありません。それは特性の問題であって、弱さではありません。
支えが一気に失われる感覚
人間関係が限られている場合、ペットが“最も安定した関係”だったという人もいます。
その存在を失うと孤独感や不安感が一気に押し寄せ、体調や症状が悪化することもあります。
これは珍しいことではなく、多くの当事者が経験している反応です。
「早く立ち直らなくていい」という考え方
悲しみの長さに正解はない
ペットロスに「これくらいで立ち直るべき」という基準はありません。数か月、あるいは数年たっても、ふと涙が出ることもあります。
それは、きちんと愛していた証拠です。
無理に気持ちを切り替えようとすると、かえって心の回復が遅れることもあります。
比較しなくていい
周りの人が「もう元気そう」に見えても、自分は自分のペースで大丈夫です。
障がいの特性や生活環境が違えば、回復の仕方も当然違ってきます。
ペットとの別れを少しずつ受け止めるために
「いない現実」に慣れる時間をつくる
いきなり生活を元に戻そうとしなくて構いません。写真を見る、名前を呼んでしまう、夢に出てくる――それらは自然な過程です。
「思い出してはいけない」と抑え込むより、思い出しても大丈夫な時間を自分に許してあげてください。
誰かに話せなくてもいい
無理に人に説明しなくてもいいです。ノートに書く、スマホのメモに気持ちを残すだけでも心は少し整理されます。
言葉にならない悲しみも、形にしようとしなくていい悲しみも、確かに存在します。
「次を考えられない自分」を責めないで
また飼う・飼わないは自由
「またペットを飼えばいい」と言われることがありますが、それを決めるのはあなた自身です。
二度と同じ思いをしたくないと感じるのも、またいつか迎えたいと思うのも、どちらも間違いではありません。
今は“何もしない”選択もある
悲しみの中では、何かを決める力そのものが弱くなります。だからこそ、今は決めなくていいという選択も大切です。
まとめ:その悲しみは、あなたが生きてきた証
ペットとの別れがつらいのは、それだけ深くつながっていたから。
障がいがあるからこそ、その存在がどれほど大きかったかをあなたは知っています。
泣いてもいい。立ち止まってもいい。時間がかかってもいい。
その悲しみは、あなたが誰かを大切にできた証です。そして、その優しさは、決して失われるものではありません。
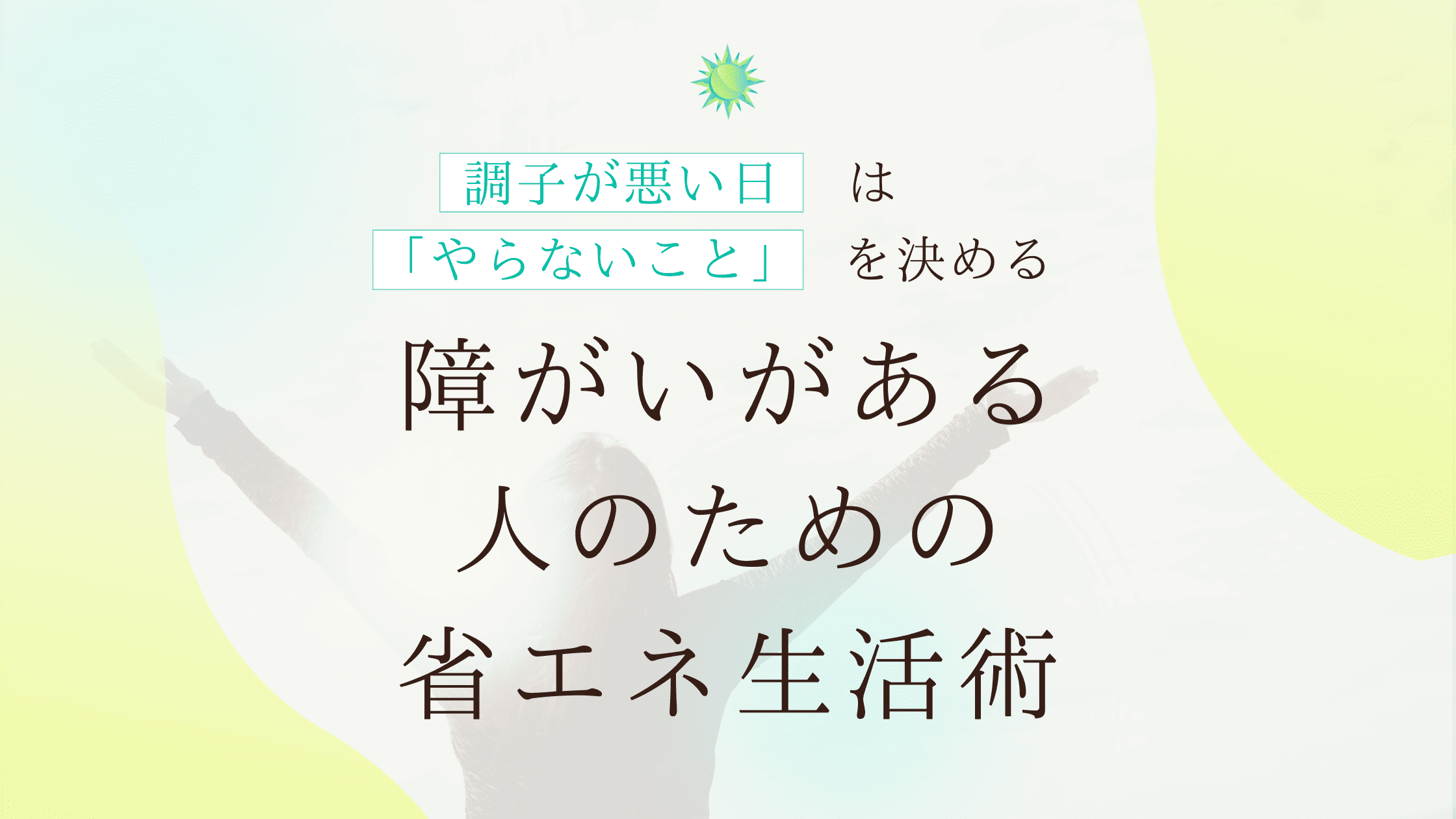
- 冬
- 生活
- 精神障がい
- 発達障がい
障がいがある人のための省エネ生活術
「今日は何もできなかった」そう感じる日が続くと、自分を責めてしまうことはありませんか。
特に冬は、寒さや日照時間の短さ、体調の変化が重なり、障がいがある人にとって心身のエネルギーが大きく削られやすい季節です。そんな時に役立つ考え方があります。それが「やることリスト」ではなく「やらないことリスト」です。
この記事では、調子が悪い日に無理をしないための「省エネ生活術」を、障がい特性に配慮しながら紹介します。
なぜ「やることリスト」がつらくなるのか
調子がいい前提で作られている
一般的なToDoリストは、「今日もある程度元気に動ける」ことを前提に作られています。しかし、発達障がいや精神障がい、慢性疾患などがある人は、日によってエネルギー量が大きく変わることが珍しくありません。
調子が落ちている日に、元気な日の基準で作ったリストを見ると「できない自分」だけが強調されてしまいます。
できなかった項目が自己否定につながる
ToDoが消えない、終わらない。それが積み重なると、「怠けている」「ダメな人間だ」という思考に結びつきやすくなります。
本当は体や脳が休息を必要としているだけなのに、心だけが追い詰められてしまうのです。
「やらないこと」を決めるという発想
エネルギーを守るための選択
「やらないこと」を決めるのは、諦めではありません。それは自分のエネルギーを守るための戦略です。
限られた体力や集中力を、最低限必要なことにだけ使う。それが結果的に、回復を早めることにもつながります。
頑張らないためのルールを持つ
調子が悪い日は、その場の気分で判断すると「少しだけなら…」と無理を重ねがちです。あらかじめ「やらないこと」を決めておくことで、迷いや自己交渉を減らすことができます。
障がいがある人が冬に消耗しやすい理由
感覚・自律神経への影響
寒さや気圧の変化、日照時間の短さは、自律神経のバランスを崩しやすくします。発達障がいの感覚過敏や、精神障がいの気分変動が強く出る人も少なくありません。
これは気合や根性でどうにかなるものではなく、身体的な反応です。
社会のペースと合わなくなる
年度末に向かって社会全体が慌ただしくなる2月は、「周りは動いているのに自分は動けない」という感覚を抱きやすい時期でもあります。
そのギャップが、さらに疲労感を強めてしまうのです。
「やらないことリスト」の具体的な考え方
調子が悪い日の基準を決める
まずは「今日は省エネモードに入る」という基準を自分なりに決めておきます。たとえば、朝起きた時点で強い倦怠感がある、頭がぼんやりする、感情が不安定など。
基準があることで「今日はやらない日」と判断しやすくなります。
生活編:やらなくていいことを明確にする
調子が悪い日は、掃除や料理、完璧な身支度を手放しても構いません。レトルトや宅配、最低限の清潔さで十分です。
「ちゃんとやらない」を選ぶことが、回復への近道になることもあります。
人間関係編:無理な対応を減らす
返信を急がない、会話を最小限にする、予定をキャンセルする。これらも立派なセルフケアです。
相手に説明できない日があっても問題ありません。自分の調子を最優先していいのです。
「やらない」を決めると、実は回復が早い
無理を減らすと反動も減る
調子が悪い日に無理をすると、その後に大きな反動が来ることがあります。数日、あるいは数週間動けなくなるケースも珍しくありません。
最初から省エネで過ごすことで、結果的に生活全体が安定しやすくなります。
自己肯定感を下げにくくなる
「今日はやらないと決めたからOK」そう思えるだけで、できなかった自分を責める回数が減ります。
これはメンタルヘルスの観点からも重要なポイントです。
周囲との関係で気をつけたいこと
すべてを理解してもらう必要はない
家族や職場に「今日は何もできない理由」を完璧に説明しようとすると、それ自体が負担になります。必要最低限の共有で十分です。
理解されないことがあっても、自分の選択が間違っているわけではありません。
支援制度や相談先も選択肢に
調子の波が大きい場合、医療機関や支援機関に相談することも一つの方法です。「頑張り方」を増やすのではなく、「休み方」を一緒に考えてもらう視点が大切です。
参考リンク:国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所「こころの情報サイト」https://kokoro.ncnp.go.jp/
NHK ONE(こころ・脳・神経)https://www.web.nhk/tv/dk/editorial-tep-kenko-Y5BQSMXNYK
まとめ:やらないことは、生きるための知恵
調子が悪い日は、「何をするか」より「何をしないか」が重要になります。やらないことを決めるのは、甘えではなく、生き延びるための工夫です。
冬は誰でも消耗しやすい季節。障がいがある人なら、なおさらです。
できない日があっても大丈夫。省エネで過ごす選択は、あなたの人生を長く、安定させる力になります。
今日は、やらないことを一つ決めてみませんか。
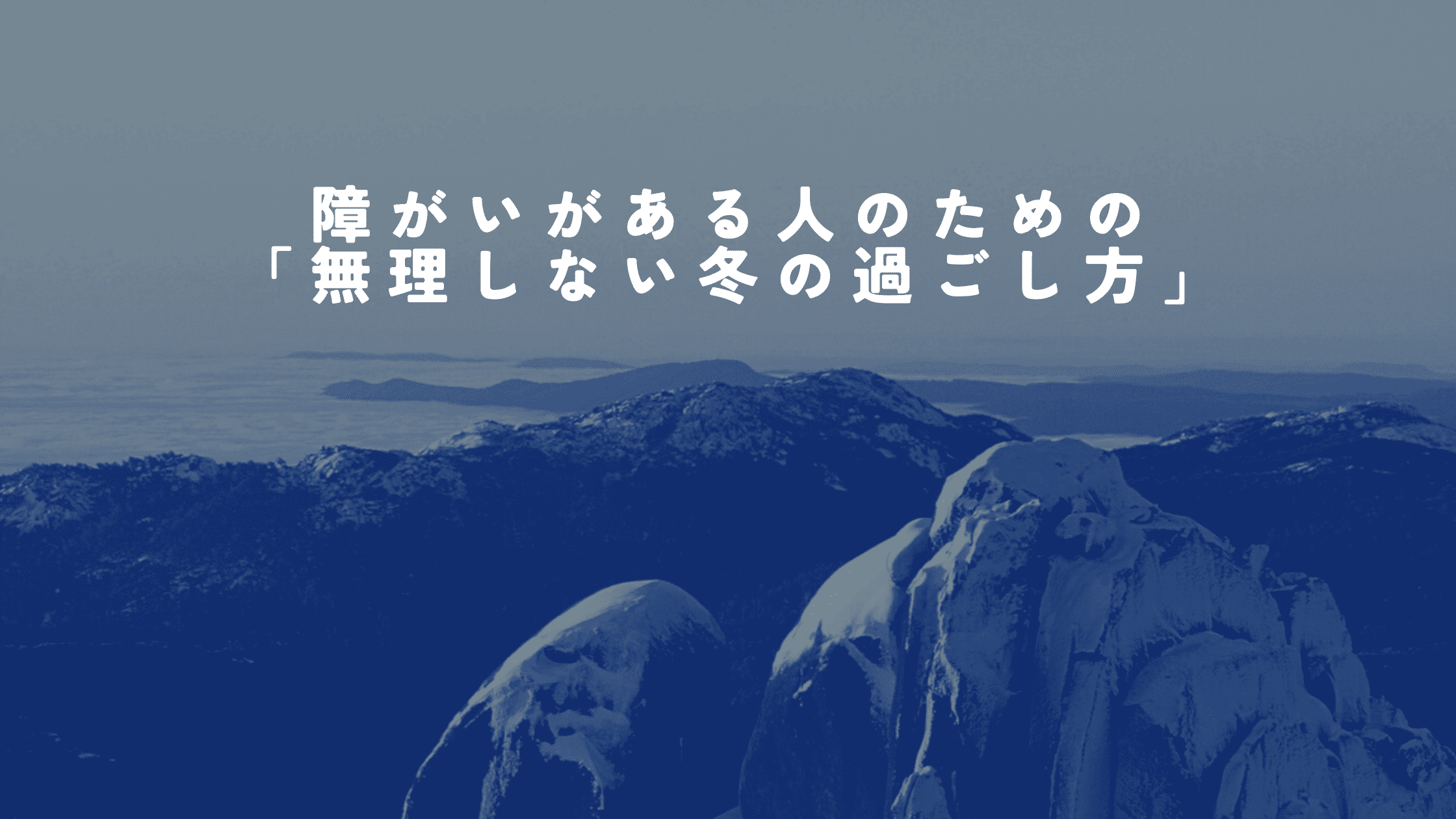
- 冬
- 精神障がい
- 身体障がい
- 発達障がい
- 感覚過敏
- 知的障がい
障がいがある人のための「無理しない冬の過ごし方」
2月は一年の中でも、心と体の調子を崩しやすい時期です。寒さがピークを迎え、日照時間も短く、年末年始の疲れが表に出てくる頃でもあります。
障がいがある人にとって、この時期は「いつも以上にしんどい」と感じやすい季節ではないでしょうか。
この記事では、2月に調子を崩しやすい理由を整理しながら、無理をせず、自分を守りながら冬を乗り切るための考え方や工夫をお伝えします。「頑張る」ではなく、「楽になる」ための視点を大切にしています。
なぜ2月はつらくなりやすいのか
寒さが体に与える影響
寒さは、筋肉のこわばりや血流の低下を招きやすく、痛みや疲労感を強める原因になります。肢体不自由、慢性疾患、感覚過敏などがある人にとっては、冷えそのものが大きなストレスになります。
また、寒さによって体を動かす機会が減ると、体力低下や睡眠リズムの乱れにつながり、結果として不調が長引くことも少なくありません。
日照時間の短さと気分の落ち込み
2月は日照時間が短く、気分を安定させるホルモンが分泌されにくい時期です。そのため、理由ははっきりしないけれど気分が落ち込む、やる気が出ないと感じる人も多くなります。
精神障がい、発達障がい、双極性障がいなどがある場合、こうした季節要因の影響をより強く受けることがあります。
年始の反動が出やすい時期
「今年こそは頑張ろう」と立てた目標が、2月になるとうまくいかなくなり、自分を責めてしまうこともあります。しかし、これは珍しいことではありません。むしろ、多くの人が同じようにペースを崩しやすい時期なのです。
2月は「調子が落ちてもいい月」と考える
無理を前提にしない考え方
2月を「通常運転の月」と考えると、どうしても自分に厳しくなりがちです。ですが、この時期は調子が落ちやすいことを前提に、最初からハードルを下げておくことが大切です。
予定を詰めすぎない、できることを減らす、休む時間を最初から組み込む。これは怠けではなく、体調管理の一部です。
「できない自分」を責めない
寒さや不調で思うように動けない日があっても、それは能力や努力の問題ではありません。環境の影響を受けているだけです。
「今日はできなかった」ではなく、「今日は体を守れた」と捉え直すだけで、気持ちは少し楽になります。
無理しない冬の過ごし方のヒント
体を冷やさない工夫
完璧な防寒を目指す必要はありません。首、手首、足首など、冷えやすい部分を重点的に温めるだけでも体への負担は変わります。
自分に合った室温や服装を見つけることも大切です。他人の基準ではなく、「自分が楽かどうか」を判断軸にしましょう。
エネルギー配分を意識する
2月は一日の中で使えるエネルギー量が少ないと考えて行動すると、消耗を防ぎやすくなります。
午前中は休養中心、午後に一つだけ用事を入れるなど、あらかじめ余白を持たせたスケジュールがおすすめです。
休むことを予定に入れる
「何もしない時間」は後回しにされがちですが、意識的に確保することが重要です。休息は気分や体調を回復させるための必要な行動です。
周囲との関わり方で自分を守る
つらさを説明できなくてもいい
調子が悪い理由を言葉で説明できないこともあります。その場合、「体調が不安定なので、今はペースを落としています」と伝えるだけで十分です。
詳しい説明をしない選択も、自分を守る立派な方法です。
比較しない距離感を持つ
周囲が元気に見える2月ほど、自分との差に落ち込むことがあります。しかし、見えているのは一部分にすぎません。
人と比べるよりも、「昨日の自分より少し楽かどうか」を基準にしてみてください。
まとめ:春に向かうための準備としての2月
2月は、何かを大きく前進させる月である必要はありません。むしろ、春に向けて体と心を整えるための準備期間と考えると、気持ちが軽くなります。
調子が悪い日が続いても、それはずっと続くものではありません。季節は必ず移り変わります。今は「耐える」のではなく、「守る」ことを優先してみてください。
寒さがつらい2月を、少しでも穏やかに過ごせますように。
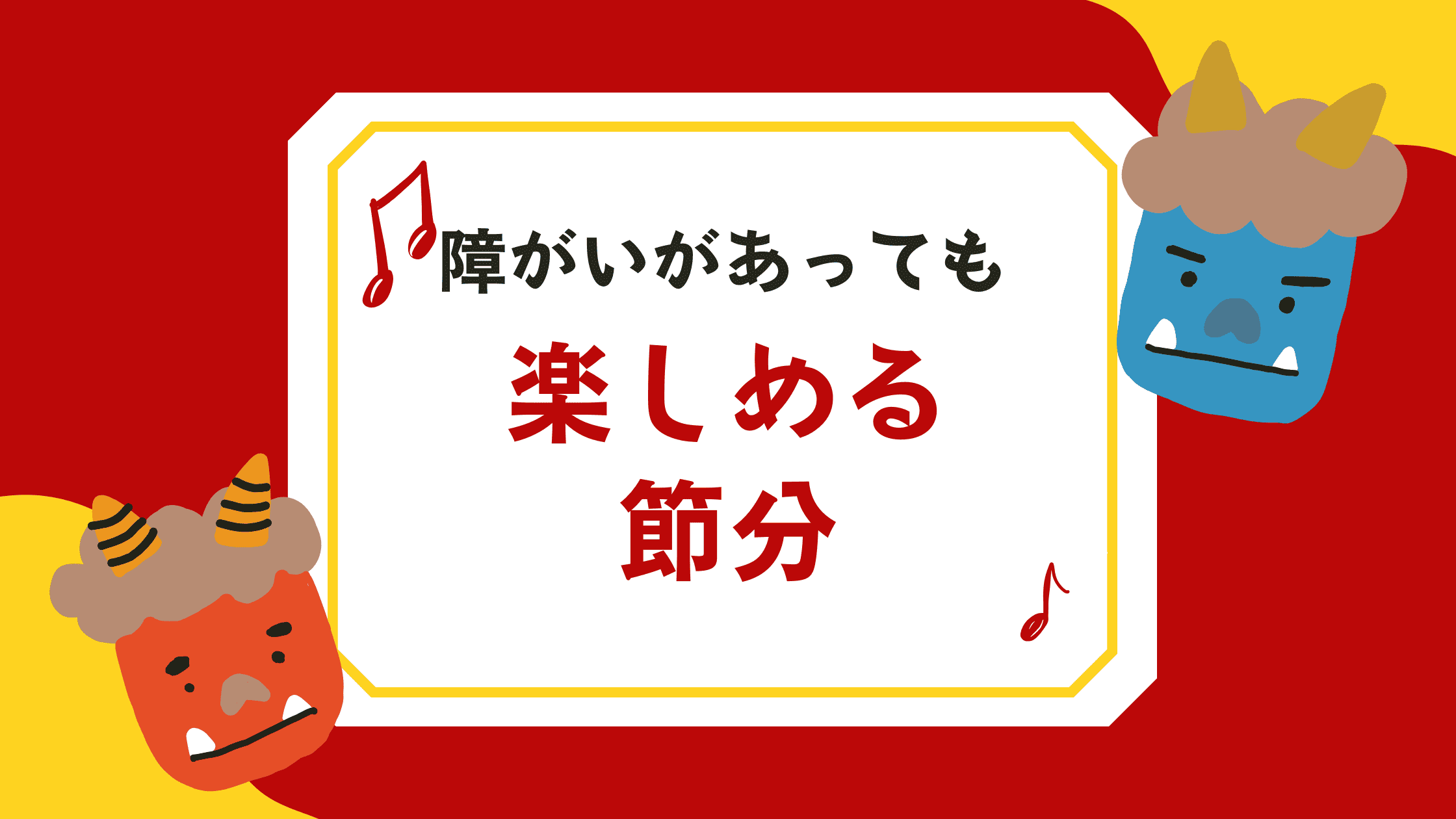
- イベント
- 精神障がい
- 身体障がい
- 発達障がい
- 感覚過敏
- 知的障がい
障がいがあっても楽しめる節分
節分といえば「豆まき」が定番ですが、すべての人にとってそれが楽しいとは限りません。
大きな音、突然の動き、豆を投げる行為そのものが、身体的・感覚的な負担になることもあります。特に、発達障がい、感覚過敏、身体障がい、精神障がいがある方にとっては、「楽しむ行事」のはずが、いつの間にか我慢の時間になってしまうことも少なくありません。
でも、節分は豆をまかなければ成立しない行事ではありません。大切なのは「季節の節目を感じること」と「無病息災や福を願う気持ち」です。
この記事では、豆をまかなくても、投げなくても、音を出さなくても楽しめる室内向けの節分アクティビティを、障がいへの配慮とともに紹介します。
節分は「投げる行事」じゃなくていい
本来の節分の意味を知る
節分はもともと、季節の変わり目に邪気を払い、新しい季節を穏やかに迎えるための行事です。鬼は「悪者」ではなく、災いや不調の象徴として描かれてきました。
つまり、豆を投げること自体が目的なのではなく、「整える」「切り替える」ことが本質なのです。
そのため、体を動かすのが難しい人や、刺激に弱い人が無理をする必要はありません。
室内で安心して楽しめる節分アクティビティ
新聞紙ボールで「やさしい節分」
硬い豆の代わりに、新聞紙や広告紙を丸めたボールを使う方法です。当たっても痛くなく、誤飲の心配もありません。
鬼のイラストを箱や壁に貼り、そこに向かって「えい」と投げるだけでも、節分らしい雰囲気は十分に味わえます。
投げるのが難しい場合は、転がす、置く、近づけるだけでもOKです。
投げない節分「ボックス鬼退治」
投げる動作そのものが負担になる場合は、入れるだけの節分がおすすめです。
鬼の顔を描いた箱や紙袋を用意し、そこにボールや紙玉をそっと入れていく遊びです。
この方法なら・力が弱い・腕が動かしにくい・座ったまま過ごしたい
といった人でも無理なく参加できます。
見るだけ・触るだけでも立派な参加
「参加=動くこと」ではありません。
鬼の飾りを一緒に眺める節分の絵本を読む福豆を数える
こうした関わり方も、立派な節分の楽しみ方です。
特に感覚過敏がある方にとっては、安心できる距離感を保つことが何より大切です。
感覚過敏がある人への配慮ポイント
音・光・人の動きに注意する
節分は、「鬼は外!」という大きな声や、一斉に動く場面が多くなりがちです。
室内で行う場合は・声を出さない・静かなBGMにする・少人数で行う
などの工夫が安心につながります。
「怖くない鬼」を選ぶ
鬼の面や衣装が怖く感じられる人もいます。その場合は・かわいいイラスト・キャラクター風の鬼・鬼を使わない節分
といった選択肢も十分ありです。
節分に「鬼がいなければいけない」決まりはありません。
食べる節分も立派な楽しみ方
豆をまかずに「福豆を味わう」
豆を投げる代わりに年の数の福豆をゆっくり味わうだけでも節分です。
硬い豆が不安な場合は・きなこ・柔らかい大豆製品・豆菓子
などに置き換えても問題ありません。
恵方巻きを無理なく楽しむ
恵方巻きも太い一本を丸かじりしなければならないわけではありません。
食べやすいサイズに切る具材を減らす巻かずに「恵方丼」にする
など、体調や嚥下に配慮した形で楽しめます。
家族・支援者と一緒に楽しむために
「みんな同じ」にしなくてもいい
誰かが豆を投げて、誰かは見るだけ。誰かは食べるだけ。
それで構いません。
節分は競争でもテストでもなく、一緒に季節を感じる時間です。
まとめ:節分は、やさしくていい
節分は、元気に豆を投げられる人だけの行事ではありません。
投げなくても叫ばなくても鬼がいなくても
福はちゃんとやってきます。
障がいがあっても、自分のペースで、安心できる形で、節分を楽しんでいいのです。
今年の節分は、「無理しない」「怖くない」「疲れない」そんなやさしい節分にしてみませんか。
参考リンク
・農林水産省「節分の日に豆をまくのは、どうしてですか。」https://www.maff.go.jp/j/heya/sodan/2001/01.html
・こども向け節分遊びアイデアhttps://hoiku-is.jp/article/detail/1436/
・YouTube:やさしい節分遊びhttps://www.youtube.com/results?search_query=節分+室内+遊び
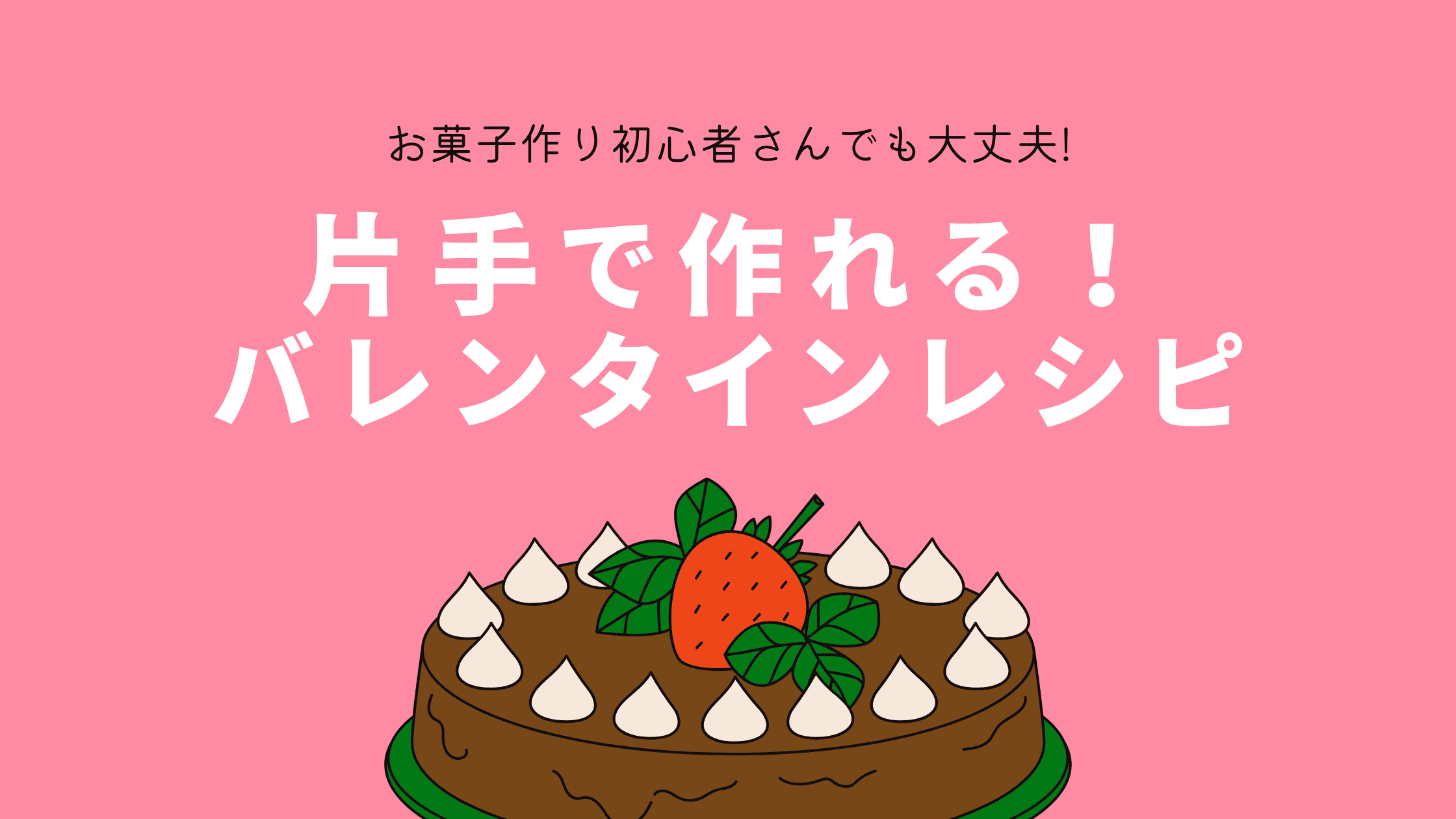
- バレンタイン
- 身体障がい
- 料理
片手で作れる!バレンタインレシピ
バレンタインと聞くと「手の込んだお菓子を作らなきゃ」「失敗できない」というプレッシャーを感じる人も少なくありません。特に、片手しか使えない状況や、調理動作に不安がある場合、ハードルはさらに高く感じられるでしょう。
しかし、バレンタインで一番大切なのは完成度の高さではなく、「あなたを想って作った」という気持ちそのものです。実は、工程を工夫すれば、片手でも十分に作れるレシピはたくさんあります。
この記事では、片手調理でも無理なく作れて、見た目も味も満足感のあるバレンタインレシピを紹介します。調理のコツや考え方も含めて解説しますので、「作れそう」と思える感覚を大切にしながら読み進めてみてください。
片手調理でもお菓子作りはできる
「両手前提」の思い込みを外す
お菓子作りは両手を使うもの、というイメージを持つ人は多いかもしれません。しかし、実際の工程を一つひとつ分解してみると、片手でも代替できる作業は意外と多くあります。
混ぜる、注ぐ、押し固めるといった動作は、道具や容器を工夫することで片手でも十分対応可能です。大切なのは、「どうやったらできるか」という視点で工程を組み直すことです。
道具選びが難易度を下げる
片手調理では、道具が作業のしやすさを大きく左右します。滑り止め付きのボウル、シリコン製の型、軽量で安定感のあるゴムベラなどは、片手作業の強い味方です。
また、電子レンジを活用することで、火を使わず安全に調理できる点も重要なポイントになります。
レシピ1:混ぜて固めるだけ「チョコレートバー」
シンプルだから失敗しにくい
溶かしたチョコレートに具材を混ぜて固めるだけのチョコレートバーは、片手調理に非常に向いています。工程が少なく、力もあまり必要ありません。
耐熱容器に板チョコを割り入れ、電子レンジで加熱します。溶けたら、ナッツやドライフルーツ、コーンフレークなどを加えて混ぜ、型に流して冷やすだけです。
見た目のアレンジで特別感を出す
仕上げにホワイトチョコを少量かけたり、表面に具材を並べたりするだけで、ぐっとバレンタインらしい見た目になります。型はシリコン製を選ぶと、片手でも取り出しやすくなります。
https://youtu.be/nf1XGnEZ2vY?si=lhrg_5VfKeVi-Vxx
レシピ2:火を使わない「マグカップブラウニー」
電子レンジで完結する安心感
マグカップブラウニーは、材料を入れて混ぜ、電子レンジで加熱するだけのレシピです。ボウルや泡立て器を使わず、洗い物が少ないのも大きなメリットです。
マグカップにホットケーキミックス、ココアパウダー、砂糖、牛乳、油を入れ、ゴムベラやスプーンで混ぜます。片手でも混ぜやすいよう、深さと安定感のあるマグを選びましょう。
「作りすぎない」ことも優しさ
一人分ずつ作れるため、量の調整がしやすい点も魅力です。無理にたくさん作らず、「今できる分だけ」で十分です。
参考リンク:クックパッド 3分で完成!簡単マグカップブラウニー♪
レシピ3:混ぜて乗せて焼くだけ「簡単フロランタン」
成形いらずで手が疲れない
市販のビスケットに、混ぜた材料を載せ焼くだけのフロランタンは成形の難しさがありません。
混ぜて乗せて焼くだけなので、片手で簡単に作ることができます。
チョコを重ねてバレンタイン仕様に
焼きあがったフロランタンの上にチョコレートをかけて冷やし固めれば、見た目も華やかなスイーツになります。工程が単純なので、途中で疲れてしまっても中断しやすいのも特徴です。
参考リンク:クックパッド 市販のビスケットで♩簡単フロランタン
片手調理をラクにする考え方
「段取り」を最優先にする
片手調理では、作り始める前の準備が非常に重要です。材料をすべて計量し、使う順番に並べておくだけで、作業の負担は大きく減ります。
完璧を目指さない
形が少し崩れても、焼き色にムラがあっても問題ありません。バレンタインのお菓子は評価されるための作品ではなく、気持ちを伝える手段です。
障がいや不安があっても、作ることに価値がある
「作れた経験」が自信につながる
片手でお菓子を作れたという経験は、結果以上に大きな意味を持ちます。「できた」という感覚は、次の挑戦への土台になります。
誰かに頼るのも立派な選択
途中の工程だけ手伝ってもらう、材料の買い出しをお願いするなど、誰かの手を借りることも決して悪いことではありません。一緒に作る時間そのものが、バレンタインの思い出になります。
まとめ:形が少し悪くても気持ちはしっかり伝わる
片手で作れるバレンタインレシピは、「無理をしない工夫」の積み重ねです。特別な技術や高価な道具がなくても、工程をシンプルにすれば、十分にお菓子作りは楽しめます。
大切なのは、誰かを想って行動したという事実です。完成度よりも、その過程と気持ちを大切にしてください。
今年のバレンタインが、あなたにとってもやさしい時間になりますように。
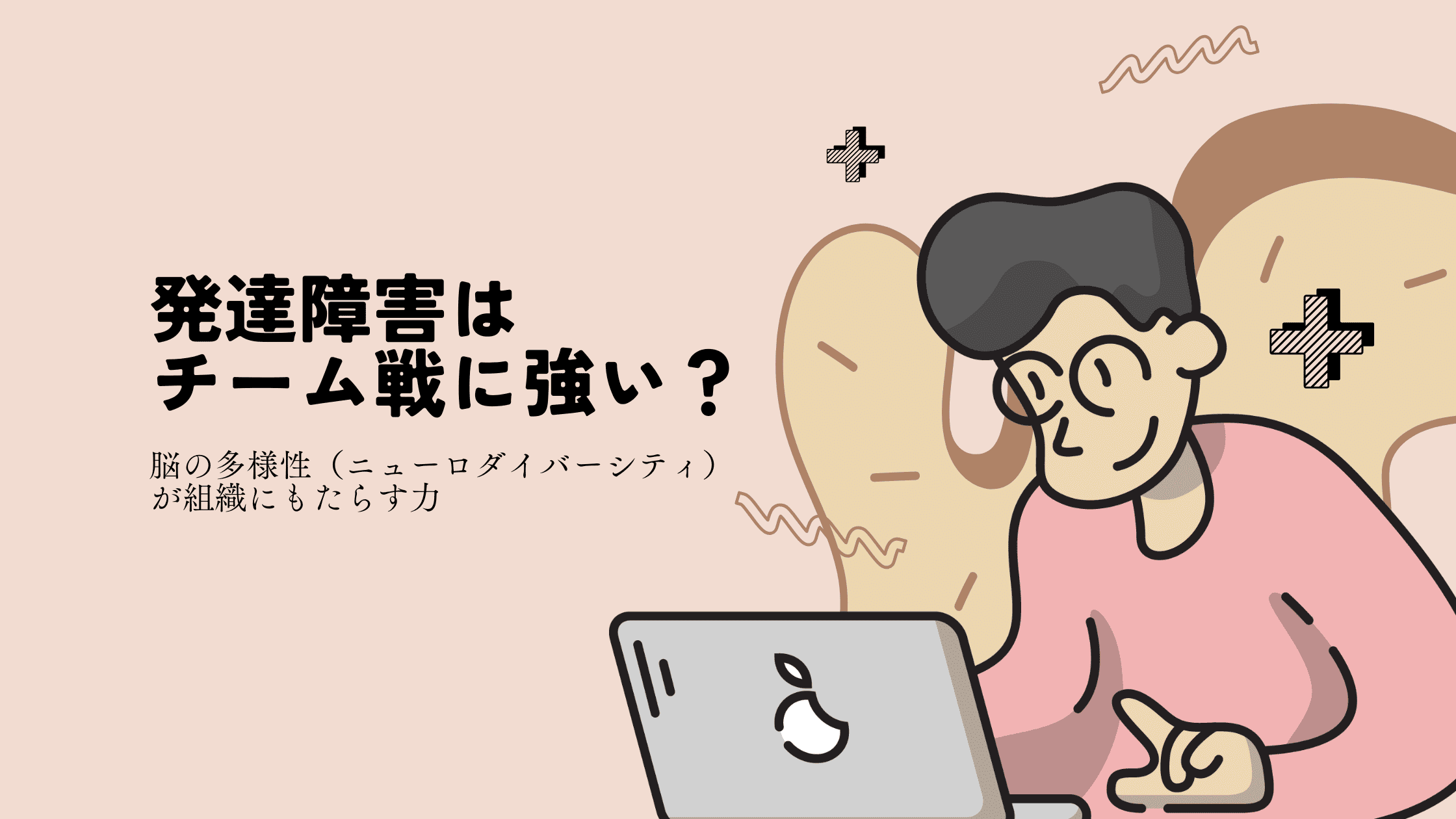
- 発達障がい
- 仕事
発達障害はチーム戦に強い?脳の多様性(ニューロダイバーシティ)が組織にもたらす力
従来の「定型発達が標準」という前提だけではなく、「脳の多様性(≒認知の多様性)=Neurodiversity(ニューロダイバーシティ)」を社会や職場に受け入れようという考え方が広がっています。
特に日本でも、この考え方を取り入れる企業や組織、研究が増えてきています。たとえば「日本橋ニューロダイバーシティプロジェクト」の調査では、オフィスワーカーの約5%が発達障害の特性を持つ可能性があると報告されています。
多様な脳が混ざることで、チームにどんな強みが生まれるのか――。
この記事では、凸凹脳(神経多様性)がチームに与えるポジティブな効果、注意すべきこと、そしてその活かし方を見ていきます。
ニューロダイバーシティとは?
神経多様性という考え方
「ニューロダイバーシティ(Neurodiversity)」は、脳や神経の働きの違いを、欠陥や劣ったものとしてではなく“個性”や“多様性”として捉える考え方です。
発達障害(ASD、ADHD、学習障害など)を持つ人だけでなく、すべての人の脳・神経の違いが尊重されるべきだ、という理念から生まれました。
参考リンク:Neurodiversity
この考え方は、社会だけでなく、企業や組織の人材戦略としても注目されています。多様な「考え方」「感じ方」「得意不得意」が混ざることで、従来の画一的価値観では生まれなかったアイデアや創造性が発揮される――そんな可能性があるのです。
参考リンク:経済産業省 ニューロダイバーシティの推進について
「凸凹脳」は珍しくない
こういった凸凹脳は「発達障害者」「特別な能力を持つ人」のみ、というわけではありません。前述の調査でも示されるように、オフィスワーカーの中に「発達特性を持つ可能性のある人」が一定割合で存在し、一般的な多様性のひとつと考えられています。
参考リンク:日本橋ニューロダイバーシティプロジェクト 「職場における脳・神経の多様性に関する意識調査」の結果について
つまり、あなたのチームやクラス、サークルにも既に「凸凹脳」がいるかもしれない――。それを「弱み」ではなく「違い」「個性」として捉えること自体が、変化の第一歩と言えるでしょう。
なぜ「発達障害 × チーム」は“強み”になり得るのか?
多様な認知スタイルが創造性を生む
異なる認知スタイルを持つ人たちが集まると、同じ課題に対して多角的な視点が出やすくなります。
たとえば、ある人が細かい部分に気づき、別の人が全体像を考え、また別の人がユニークな発想を出す――。こうした多様性は、マンネリ化した思考や一方向のアイデアに偏らず、チーム全体の“創造力の底上げ”につながります。
実際、日本の企業でもニューロダイバーシティを採り入れることで、組織の活力やイノベーションの可能性を見直す動きが強まっています。
視野の広さと柔軟な対応力
凸凹脳の人は、「普通とは違う」やり方や感覚を持つことが多く、それは新しい対応・代替案を考えるうえで力になります。
既存の枠にとらわれない思考ができる人は、予期せぬトラブルや変化にも柔軟に対応でき、チームの安定性や強さにつながることがあるのです。
強みを引き出すマネジメントとの相性の良さ
もちろん多様性には壁が現れることもあります。
しかし、適切な理解と配慮(コミュニケーションの柔軟性、働き方の調整、役割の明確化など)があれば、凸凹脳の強みは十分発揮されます。
こうした「認知的多様性を尊重するマネジメント」は、現代の多様な価値観や働き方の中で、むしろ合理的かつ必要なアプローチだと、多くの専門家が指摘しています。
参考リンク:JMAソリューション (日本能率協会)ニューロダイバーシティの考え方と実践
実際の職場でどう活かす?発達障害を強みに変えるチームづくり
まずは「認めること」から:神経の多様性を理解する環境づくり
チームや職場として最初にできるのは、「発達障害や認知特性は個性である」「みんな違って当然」という共通認識を持つこと。
たとえば、勉強会やミーティングで「ニューロダイバーシティとは何か」を共有したり、意見を言いやすい雰囲気を作ることが第一歩です。
日本でも、この考え方を取り入れた企業が増えており、「発達障害を強みにする人材戦略」は徐々に広がっています。
参考リンク:大人の発達障害ナビ ニューロダイバーシティ 脳の多様性を考えてみよう
適材適所を意識する配置と役割分担
例えば、細やかなチェックやルーチンワークを得意とする人、アイデア出しや発想に強い人、全体の流れを見るのが得意な人――。
特性によって得意分野は変わるので、役割を固定せず、その人の特性に応じて柔軟に配置するのが理想です。
ある会社の例では、発達特性を持つ人をテスターや検証作業担当に配して、高い成果を出しているという報告があります。
コミュニケーションとサポート体制の工夫
認知の特性ゆえに、コミュニケーションで困ることがあるかもしれません。だからこそ、
指示や依頼は「文章+口頭」でわかりやすく
やることを見える化(ToDo管理やチェックリスト)
無理のないスケジュール設定と休憩の確保
など、サポート体制を整えることで、多様な人が力を発揮しやすくなります。
こうした取り組みは「合理的配慮」「インクルージョン」の一部として、多くの企業が採用し始めています。
発達障害 × チームのメリットと注意点
メリット:創造性・柔軟性・多角的思考
多様な脳が混ざることで、同じ課題に対して複数のアプローチが出やすくなります。これにより、問題解決の幅が広がり、イノベーションが生まれやすくなります。
たとえば、最近の記事でも「発達障害のある人はイノベーションと相性が良い」とする分析があります。
参考リンク:Forbes JAPAN 日本で10人に1人。なぜ発達障害のある人はイノベーションと相性がいいのか
注意点:誤解・摩擦・情報処理のズレ
一方で、認知の違いが “ズレ” を生み、誤解やコミュニケーションの齟齬、チーム内での摩擦につながることもあります。多様性そのものが「両刃の剣」になり得るからです。
実際、国際研究でも「多様性があるだけでは効果が出ず、心理的安全性(その違いを認める土壌)が重要だ」と報告されています。
そのため、チームとして「多様性を活かすルールづくり」や「心理的安全な場の確保」が不可欠です。
日本で広がる「ニューロダイバーシティ」
実践と動き
日本でも近年、ニューロダイバーシティの受け入れ・推進に前向きな企業や団体が増えています。
たとえば「Neurodiversity at Work」を掲げるコンサルティングや講座、社員の受け入れ事例の公開などが進んでいます。
また、社会全体としても「脳や神経の多様性は当然の変異」という見方が少しずつ広がりを見せており、障害者雇用に限らず、通常の職場や組織でも、凸凹脳を含む多様な人材をどう活かすかが問われています。
参考リンク:朝日新聞 ニューロダイバーシティとは? 発達障害との関係や具体例、批判と今後のあり方を解説
「発達障害 × チーム」をうまく回すための実践ポイント
少し手間かもしれませんが、次のような取り組みが有効です。
チーム全体で「認知の多様性とは何か」を学ぶ機会をつくる
個々の特性や働き方の好みを共有する
仕事の割り振り・環境を柔軟にする(役割分担、タスク管理、休憩・休息の確保)
コミュニケーションやフィードバックの方法を明文化する(口頭+文章など)
チームメンバーの「違い」を尊重する姿勢を持つ
こうした取り組みは、決して「特別扱い」ではなく、チームの当たり前の土台として機能します。
まとめ : “発達障害× 多様性” は、チームの資産になる
従来、「定型発達が基準」とされてきた社会では、脳の多様性は見落とされがちでした。しかし、今は「違いこそが力になる」という価値観が広がり、「凸凹脳を含めた多様性」がチームの強みに変わりつつあります。
もしあなたが、発達特性や神経の違いを持っていて、「自分のせいで迷惑をかけているかも…」と感じていたら。それは“弱み”ではなく、“このチームに必要な個性”かもしれません。
チームには様々な人がいて当然。その多様性を大切にすることで、チームはもっと強く、豊かになります。
凸凹脳がもたらす多様性を、あなたも、あなたのまわりも、強みに変えてみませんか?
🔗 参考リンク・動画
「あなたの“特性”はチームの“強み”になる」 — 発達特性をチームの資産とする実践的コラム 株式会社rewrite(リライトキャンパス浜松駅南)
日本橋ニューロダイバーシティプロジェクト 「職場における脳・神経の多様性に関する意識調査」の結果について 武田薬品工業
「ニューロダイバーシティを解説」精神科医がこころの病気を解説するCh
https://www.youtube.com/watch?v=wxpnnF8NP8s
「ニューロダイバーシティ/脳と神経の多様性」について質問ある?| Tech Support | WIRED Japan
https://www.youtube.com/watch?v=emGLAuD_fL0
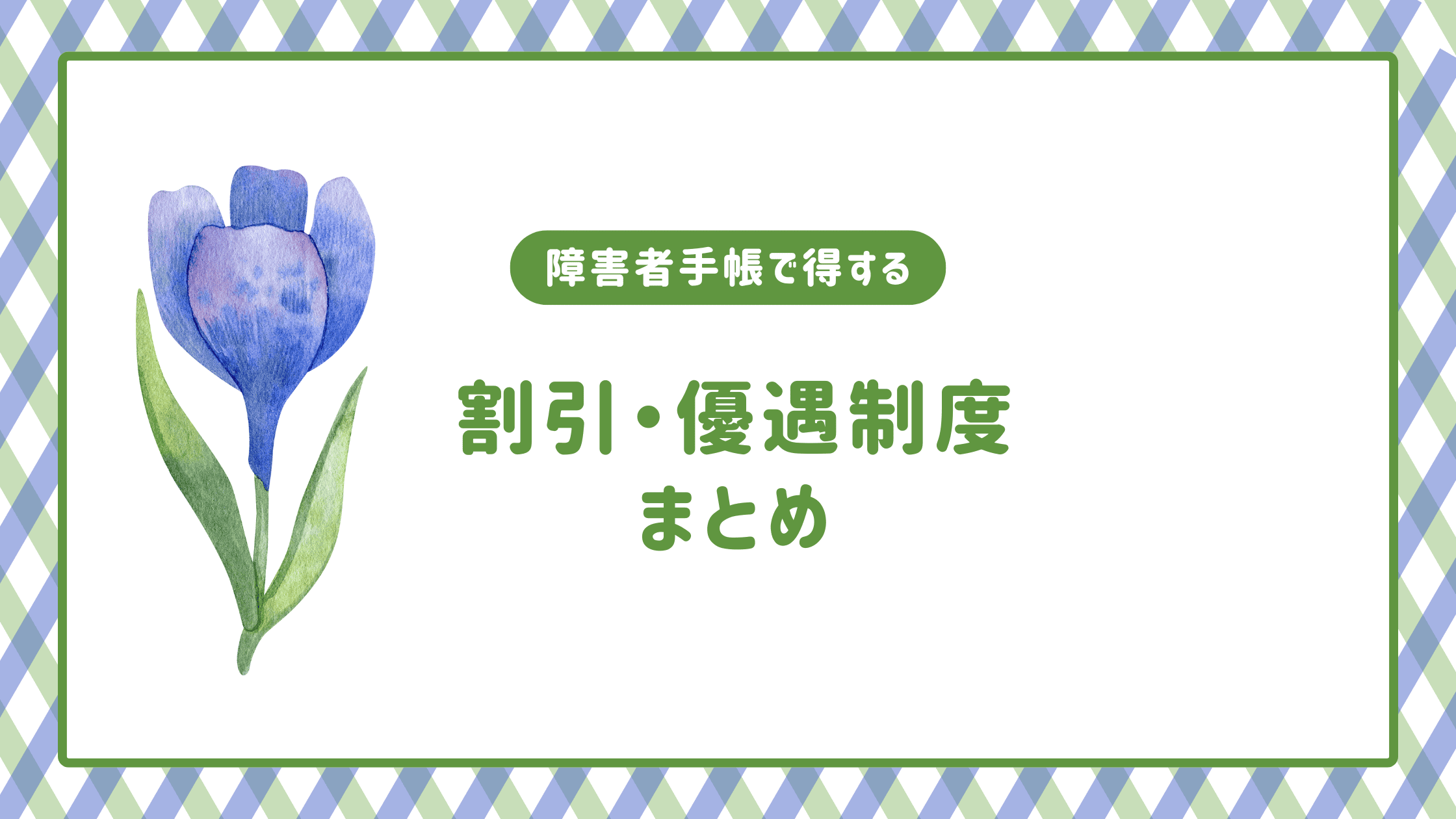
- 障害者手帳
- 精神障がい
- 身体障がい
- 発達障がい
- 知的障がい
障害者手帳で得する10の割引・優遇制度まとめ
「障害者手帳を持っているのに、まだあまり活用していない」――そんな人はけっこう多いようです。実は、手帳には“割引・優遇制度”がたくさん存在し、使いこなせば生活やお出かけがぐっと楽になります。
本記事では、割引・優遇を10項目に整理し、どんな場面で使えるか/どのように使うか/注意点 を詳しく解説します。
地域や施設ごとに適用内容は異なるため、利用前には必ず公式情報の確認を。
1. 交通機関の割引 ─ 通勤・通院・旅行が安くなる
JR/私鉄・地下鉄の運賃割引
障害者手帳を提示することで、鉄道運賃が割引になる制度があります。2025年4月からは、精神障害者保健福祉手帳保持者への割引を導入しました。
参考リンク:交通新聞
例えば、手帳に「旅客鉄道運賃減額欄に第1種または第2種」と書かれていれば、普通乗車券や定期券などで割引対象となる場合があります。介助者も割引されるため、大変お得な制度です。
参考リンク:JR東日本 お身体の不自由なお客さまへ
地下鉄・私鉄・地下鉄でも割引あり
Osaka Metroなど、私鉄や地下鉄でも身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳に応じた割引を行っている例があります。
参考リンク:Osaka Metro 障がい者手帳による割引
通勤・通院、日常移動がグッと安く
日々の通院や通勤、定期的な外出がある人は割引が大きく、手帳を提示するだけで負担を減らせます。
2. 高速道路・駐車場・レンタカー・自家用車利用でもサポートあり
公共交通ではなく車移動をする場合にも、手帳があると優遇があります。たとえば、高速道路の通行料金や有料道路の通行料が割引又は免除になる制度があります。
また、公営駐車場や福祉対応駐車場での無料または割引待遇、レンタカー利用料の割引制度を提供する業者もあります。
自分で運転する人、介助者が運転する場合など条件が異なるため、事前確認が大切です。
3. 飛行機・船舶など長距離移動の割引
国内線の航空便でも、手帳による割引を設定している会社があります。たとえば、ANAやJALをはじめ、一部LCCでも身体障害者割引が適用されることがあります。
また、船舶、フェリー、遊覧船などの海上交通やロープウェイなどでも、割引対象となることがあります。運営会社によって異なるので、予約時に必ず確認を。
遠くへの旅行や帰省、長距離移動を計画しているなら、手帳の割引を使うことで大きな節約につながります。
4. タクシー・バス・公共交通の割引 ─ 日常の移動コスト軽減
路線バス・高速バスの割引
多くのバス会社で、身体障害者手帳または療育手帳を持つ人の運賃割引制度を実施しています。たとえば、普通路線バスや高速バスの運賃が半額になる場合があり、付き添い者1名が割引対象となることも。
タクシー利用時の割引
タクシーを利用する際も割引を受けられるケースがあります。手帳の等級やタクシー会社によって異なりますが、割引や補助制度がある地域もあります。
公共交通が使いにくい人や、雨の日・荷物が多いときなど、タクシー割引は助かる制度です。
5. 映画館・美術館・博物館などの文化施設の割引・無料化
映画館の割引料金
多くの映画館では、障害者手帳を提示することで割引料金で鑑賞できます。場合によっては付き添い者1名まで同じ割引が適用されることもあります。
たとえば、一般料金が約2,000円の映画館であれば、1,000円で鑑賞できる例も報告されています。
美術館・博物館の入館無料または割引
国や自治体が運営する美術館・博物館では、多くの場合、障害者手帳の提示で入館料が無料または割引になることがあります。付き添い者1名も割引対象となる施設が多いようです。
文化・芸術を気軽に楽しめる
移動や体力的な心配があっても、こうした割引があると“気軽なお出かけ”がしやすくなります。文化・芸術へのアクセスが身近になるのは嬉しいメリットです。
6. レジャー・テーマパーク・動物園・水族館の割引・特典
手帳を持っていることで、テーマパーク・動物園・水族館などでの入場料割引(または無料化)、同伴者の割引などが受けられることがあります。
たとえば、ウェブ上で紹介されているケースでは、入場料が半額または無料、付き添い者も割引対象など。
家族や友人と一緒に外出する機会が増えるため、社会参加や気分転換にもつながります。
7. スポーツ施設・カラオケなど余暇施設の優遇
映画館やテーマパークだけでなく、カラオケ、スポーツ施設、温泉、レジャー施設などでも、手帳を使った割引や優遇が提供されていることがあります。
例えば、室料割引、入場料割引、付き添い者の割引など。余暇やリフレッシュの機会が増えるのは、心身の健康にもつながります。
──ただし、施設ごとに対応が大きく異なるため、事前に確認することが重要です。
8. 介助者・付き添い者の割引適用 ─ 一緒に行動する人もお得に
多くの割引制度では、本人だけでなく 介助者や付き添い者1名も対象 になることがあります。特に交通機関、テーマパーク、映画館、文化施設などでこの制度が適用される例が多いです。
これにより、一緒に出かける家族・友人も割引を受けられ、経済的な負担を軽くしやすい点が大きなメリットです。
9. 公共料金・携帯電話・通信サービスなど生活コストの割引
手帳保持者向けに、携帯電話会社や通信サービスで割引を実施している場合があります。たとえば、携帯の基本料金割引、インターネットプロバイダの割引、あるいは公共料金(地域によっては水道やNHK受信料の割引)の対象になることも紹介されています。
毎月の固定費の削減につながるため、長期的には大きな効果があります。
10. 税金・福祉サービス・補助金など制度的メリット
手帳があることで、医療費の助成、税金の軽減、補装具の助成、住宅改修支援など、割引・免除以外の福祉サービスを受けられる場合もあります。これらは国や自治体の制度によるため、居住地域や等級により異なりますが、活用すれば生活の質を大きく支えてくれます。
手帳による優遇制度は「割引だけ」ではなく、「安心して暮らせるためのインフラ」として機能することも少なくありません。
✅ 手帳を「最大限活用する」ためのポイント
・手帳は常に携帯を
割引を受けるには原則「提示」が必要。外出時には手帳を持ち歩く習慣をつけること。
・事前に公式サイトで確認を
施設や事業者によって割引制度の有無や内容が異なるため、予約や訪問前に公式情報のチェックを。
・同伴者の割引を確認
付き添いや介助者が割引対象かどうか、事前に要確認。同行者の有無でお得さが大きく変わる場合があります。
・地域・自治体の独自制度もチェック
全国共通の割引だけでなく、自治体ごとの福祉サービス・助成制度を市役所等で聞いてみるのがおすすめ。
・デジタル手帳・アプリの活用も検討
最近では、手帳情報をスマホで管理できるアプリもあり、提示が手軽になることがあります。
注意点:すべてがどこでも同じではない
割引対象かどうかは「施設・事業者による」。手帳があっても対象外のところもある。
障害の「等級」「手帳の種類(身体/療育/精神など)」によって割引内容が変わる。
同伴者の割引が「付き添い者のみ」「1名まで」「本人のみ」などで条件が違う。
割引内容の変更や終了があるため、訪問前に最新情報のチェックが必要。
まとめ:手帳は「権利」知らなきゃ損、使えば得
障害者手帳は、ただの身分証明ではありません。交通、移動、余暇、文化、生活コスト、福祉…さまざまな制度で、“負担を減らすための権利”として機能します。
もしまだ使いこなせていないなら、まずはこの記事で紹介した10の割引制度をチェックしてみてください。
手帳があることで、外出も旅行も、趣味も、あなたらしい暮らしが、もっと自由に、もっと豊かになります。
参考リンク・動画
障害者手帳を使った割引・サービス20選!賢く活用する方法も解説 ふらっと
障害者手帳割引でお得に施設を利用! Disability
障がい児育児で利用できる障害者手帳・受給者証の割引一覧 famicare
大阪版 休職者のためのリワークナビ
https://www.youtube.com/embed/Md6hiPzySdk
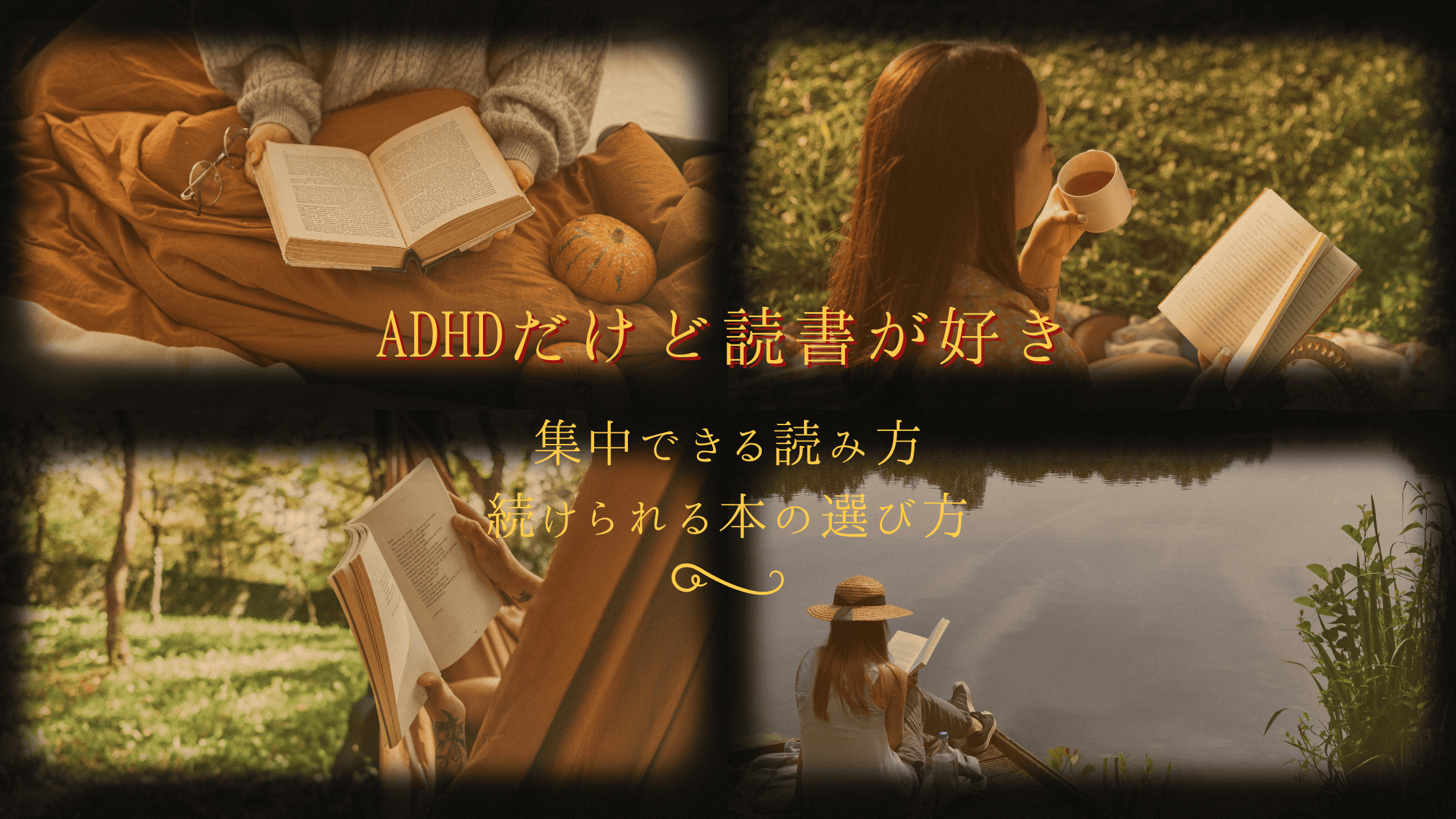
- 読書
- 趣味
- 精神障がい
- 発達障がい
ADHDだけど読書が好き!集中できる読み方・続けられる本の選び方
「ADHDなのに、読書が好き。だけど集中が続かない。」そんな声は、とても多く聞きます。
ページを開いても頭に入らなかったり、5分ごとにスマホに意識が飛んでしまったり、読み終わる前に別の本を開いてしまったり——。私自身もADHDとして同じ経験を繰り返してきました。
しかし、ADHDだから読書が向かないわけではありません。むしろ、興味がハマった瞬間の没入力や多角的な発想は、読書と相性が良いことも多いのです。
この記事では、当事者の読み方のコツ × 専門家の知見 × 読書に向く本の選び方 を、わかりやすく丁寧にまとめました。
ADHDの特性とうまく付き合いながら、読書を「好き」で終わらせず、「続けられる」に変えるための実践ガイドです。
集中できない理由は「努力不足」ではない
ADHD特性が読書に影響する仕組み
ADHDの脳は、注意の切り替えが早い/ワーキングメモリが弱い/刺激への反応が強いという特徴があります。
これは「集中力が弱い」ということではなく、興味の移動が速い・情報を保持し続けるのが苦手という脳の傾向です。
読書中に意識が外に飛んでしまうのは、脳が刺激の高い方向へ自然に動くためで、本人の怠慢ではありません。
「読めない日がある」は当たり前
ADHDの集中力は日によって波があるため、昨日は読めたのに、今日は全く頭に入らない…ということが普通に起こります。
これは決して「自分は続かない人間だ」と責める理由にはならず、脳のコンディションの問題です。
読書が好きなADHDの強み
ADHDの人は、・好きなジャンルの没入力が極端に高い・本の世界を立体的にイメージできる・本から得た知識を別のジャンルに応用できるという長所も持っています。
読書を“続ける”方法さえ見つかれば、ADHD読書はむしろ人生を豊かにする強力なツールになります。
ADHDでも集中できる「読み方の工夫」
短時間 × 高頻度で読んだ方がうまくいく
なぜ短時間がいいのか
ADHDは「最初の集中」が一番大変。しかし一度入り込むと、長時間読めてしまうこともよくあります。
そのため、最初のハードルを極限まで下げるという工夫が効果的です。
たとえば「最初の3分だけ読む」「1章ではなく1段落だけ読む」という方法は、とても負担が軽く、入りやすい。
心理学でも「作業興奮(やり始めると続く)」が知られており、ADHDには特に相性が良い方法です。
「読む時間帯」を固定すると定着しやすい
朝起きてすぐ、寝る前の10分など、生活のどこかに“読書の引き金”を置くと継続が安定します。
意識が散らかりやすいときは「ながら読書」に切り替える
ながら読書はADHDの味方
音声読書(Audibleなど)+散歩音声読書+家事など、別の動きと組み合わせると集中が散らかりにくくなる人も多いです。
特に「歩きながらの読書」は研究でも集中力向上が示されており、ADHD専門家も推奨しています。
音声読み上げアプリを活用
Kindleの読み上げや、Audibleのナレーションは、ADHDと相性抜群。特に物語系は音声のほうが頭に残る人も多いです。
「脳の状態」を整える
静かな場所より“ちょい雑音”がいいことも
ADHDは静かすぎる環境だと逆にソワソワしやすく、適度なノイズが集中を支えることがあります。
「作業 雑音」でYouTube検索すると、集中に使える音源が多数あります。
参考リンク:「作業用 雑音」のYoutube動画検索結果
読む前にスマホを別の部屋に置く
認知科学的に「手元にスマホがあるだけで集中力が下がる」ことがわかっています。
ADHDならなおさらで、読書前に意識的に距離をとることが大事になります。
ADHDに向いている本の選び方
「読みやすさ」で選ぶ本は失敗しにくい
文字が大きく行間が広い本を選ぶ
ADHDは視覚処理が疲れやすいため、行間が狭い本は頭が飽和しやすくなります。
岩波文庫よりも新書サイズ、漫画エッセイ、図解本などのほうが続きやすい傾向があります。
図と文章が混在する本は負担が少ない
図解やイラストが入っていると、脳が情報処理しやすく、読書のハードルがかなり下がります。
興味の「強度」で本を選ぶ
ADHDは“好き”が読書の燃料になる
興味が爆発したジャンルは驚くほど深掘りできるのがADHDの強み。
「途中でやめてもOK」「飽きたら次へ」で問題ありません。興味が自然に動くのは特性なので、流れに合わせてジャンルを渡り歩くほうが長続きします。
今の気分にフィットするかが重要
ADHDは気分依存が強いため、同じ本でも「今日の自分」に合わないと集中できません。
本棚に“複数冊スタンバイ”しておき、その日のコンディションに合わせて選ぶ方法が有効です。
読書を“習慣”に変えるための実践テク
読書の「成功体験」を積み重ねる
読み終わったページ数を可視化する
ADHDは成果が見えるとモチベーションが上がるため、読書メモアプリや、本に付箋を貼る方法が効果的です。
読めなかった日も「ゼロではない」にする
・1行だけ読む・タイトルだけ読む・目次だけ見るこれだけで「やれた」と脳が記録し、習慣が安定します。
読んだ内容はアウトプットする
ADHDはアウトプット型の学習が向いている
・ノートにまとめる・SNSで感想を書く・友人に話すなど、人に伝える前提で読むと集中が続きやすくなります。
noteに感想を書くのは特に相性がいい
文章にしようと意識するだけで集中力が高まり、読み飛ばしが減ります。
自分が読んできた記録として、noteを作成すると、自分の軌跡がみられて達せ感を感じられます。
参考リンク:note
読書は「気分のリズム」とセットで考える
調子のいい時間帯を使う
ADHDは一日の中で集中できる時間が存在するため、その“波”に合わせて読書することで継続率が高まります。
調子が悪い日は「音声」だけに切り替える
頭が働きにくい日は音声だけにする、図解だけ見るなど、当日モードに合わせて柔軟に切り替えてみましょう。
まとめ:ADHDでも読書は楽しめる。
「ADHDだから読書が苦手、続かない。」そう思い込んでいた時期が、私にもありました。
でも実際は、読み方を変えれば、ADHDは読書を強い味方にできる特性を持っています。
・短時間 × 高頻度・ながら読書・脳の状態に合わせる・興味の強度で本を選ぶ・複数ジャンルを並行で読む
こうした工夫が組み合わさると、読書は驚くほど楽しく、深く、人生の力になります。
ADHDの脳は、制御が難しい時もあるけれど、その分 ハマったときの集中力・創造性は圧倒的です。
ぜひ、今日のあなたに合う読み方・本の選び方を試してみてください。
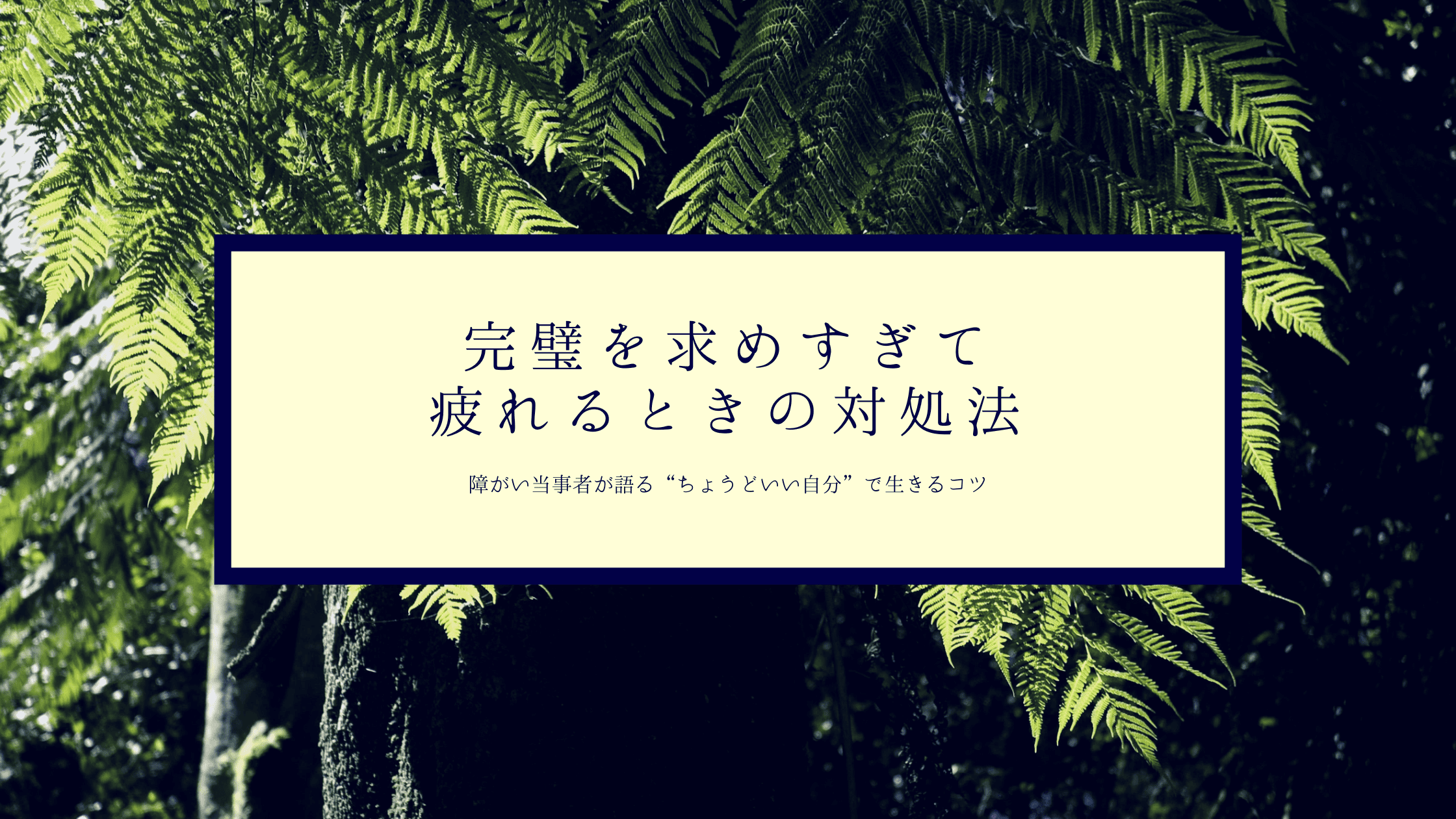
- マインドセット
- 精神障がい
- 身体障がい
- 発達障がい
- 知的障がい
【完璧を求めすぎて疲れるときの対処法】障がい当事者が語る“ちょうどいい自分”で生きるコツ
「完璧にやらなきゃ」「迷惑をかけたらどうしよう」そんなプレッシャーで、いつの間にか心も体も限界ギリギリ…。
特に、発達障がい・精神障がい・身体障がいなど、日常にひと工夫が必要な人ほど“できない自分を隠そうとして、過剰に完璧を追い求めてしまう”ことがあります。
でも本当は、完璧じゃなくていい。むしろ「ちょうどいい自分」で生きるほうが、長く安定して自分らしく生きられます。
この記事では 完璧主義で疲れてしまう理由 と、障がい当事者の視点からの“回復に向かう具体策” を紹介します。
なぜ完璧を求めすぎてしまう
「嫌われたくない」「迷惑をかけたくない」から
人が完璧主義に陥りやすい背景には、“人間関係への不安” が深く関わっています。
・失敗したら評価が下がる・弱みを見せると距離を置かれる・頼ると“できない人”と思われる気がする
こうした気持ちは、実はとても自然なものです。
しかし、これが強すぎると、毎日が“失敗できない戦場”のような感覚になり、心は次第に疲弊していきます。
「他の人はできている」という思い込み
SNSが当たり前の今、がんばっている人、成功している人、明るい日常ばかりが目に入ります。
結果として「自分だけができていない」という錯覚が生まれます。
特に障がい特性があると比較対象が“健常者中心”になりやすく、できない自分を責めすぎてしまうことにつながります。
「やりすぎてしまう」という性格傾向
心理学では“適応的完璧主義”と“非適応的完璧主義”があると言われます。後者は、基準が高すぎて、どれだけやっても満足できないタイプ。
障がいのある人の中には・繊細性が高い・集中するとやりすぎる・こだわりが強い・周囲の反応を敏感に読み取りすぎるなどの特性を持つ人も多く、完璧を追いやすい傾向があります。
なぜ障がいと「完璧主義」は結びつきやすいのか?
「迷惑をかけたらいけない」という強いプレッシャー
障がいがあると、日常で周囲の配慮を得る場面があります。そのたびに、「迷惑をかけているかも」と感じる人は少なくありません。
その気持ちが強すぎると、必要以上に“完璧であろうとする努力”につながり、体調を崩す引き金になります。
“できないこと”をカバーしようとして過剰に頑張る
発達障がいの人は、できることとできないことの差が大きい傾向があります。身体障がいの人は、日常の一つひとつの動作が工夫を必要とします。精神障がいの人は、気力が波のように大きく変動します。
そのため、できない部分を隠す・補うために過剰に完璧を求めるという構造が起こりやすいのです。
「自分でやらないと」と抱え込みやすい
周囲に頼るハードルが高く、相談が苦手だったり、気持ちを言葉にしづらかったり、特性によるコミュニケーションの難しさも存在します。
その結果「全部ひとりでなんとかしよう」となり、パンクしやすくなります。
完璧主義から抜け出すための実践ステップ
「70点の自分」を意識してみる
完璧(100点)を求めるほど、達成するハードルは高くなります。そこで有効なのが“70点でOK”の基準をつくること。
70点=「生活が崩れず、人に迷惑をかけず、自分も疲れすぎないライン」これは、障がい特性のある人にとって現実的で持続可能な基準です。
70点は妥協ではなく、丁寧なセルフケア。
この考え方が身についてくると、完璧主義の重圧が一気に軽くなります。
「できない日があってもいい」と練習する
精神障害や慢性疾患があると、波があるのは普通のこと。でも、多くの当事者が言います。
“できなかった日の自分を許すのが一番むずかしい”
これは本当にその通りです。でも、許せるようになるほど、回復は早くなります。
意識したいのは“できる日”“できない日”どちらも自分という感覚。
“今日は体調が少し落ちている、だからゆっくりする”と認められることが、実は大きな進歩です。
頼るスキルを小さく身につけていく
最初は大きなお願いでなくて大丈夫です。
・「返信が遅れるかもしれません」と先に伝える・「今日は体調次第で参加します」と言ってみる・「これを手伝ってもらえると助かる」と一文添える
これを繰り返すことで、“頼っても嫌われない体験” が蓄積され、自信に変わります。
当事者が語る「完璧でない自分」との向き合い方
できない時期があったから今の自分がいる
多くの障がい当事者が語るのは、
「倒れて初めて、自分の限界を知った」
という経験です。
限界を知ることで、・仕事の優先順位のつけ方・家事の外注・休むタイミング・人に甘える勇気が少しずつ身についていきます。
これは“弱さ”ではなく生きるためのスキル です。
完璧じゃない方が人とつながれる
完璧な人より、「ちょっと抜けてる人」「ほどよくゆるい人」のほうが周囲は話しかけやすいもの。
完璧を手放すことは、実は 人間関係を豊かにする 効果もあります。
SNSで“当事者の声”に触れる
完璧主義から抜け出すヒントは、当事者の発信に詰まっています。
YouTubeでも多くの当事者が発信しており、「自分だけじゃない」と感じられます。
●当事者が語る完璧主義・生きづらさ
flier公式チャンネル:【繊細さんのサバイバル術】「HSPを生きづらさの理由にするのは甘え?」https://youtu.be/uOdccHuAaxY?si=msfLTDOMyiIXeSFd
東海テレビ NEWS ONE:“見えない障害”と生きる12歳男の子「今思うのは発達障害あっての俺だから」皆が生きやすい社会へのヒントhttps://www.youtube.com/watch?v=tA43bsR1NQY
TBS CROSS DIG with Bloomberg:学生時代は「うっかり者の面白キャラ」社会人では「死にたい」…自己肯定感どうやって上げた?https://www.youtube.com/watch?v=xwL0l2lMVMM
今日からできる“ちょうどいい”生活習慣
「がんばる日」と「がんばらない日」を意識的につくる
障がい特性による疲れやすさは、本人にしかわかりません。だからこそ、最初からスケジュールに“休む日”を入れておくことがとても大切です。
できなかったことより“できたこと”を見る
完璧主義の人ほど、できなかった部分だけを見がちです。でも、どんな日でも必ず「できたこと」は存在します。
・布団から起きられた・メッセージに返事できた・買い物に行けた・横になりながらでも仕事をした
この積み重ねが、自己効力感を確実に高めます。
周囲に前もって伝えておく
たとえば、・急な予定変更がある・疲れやすい・体調に波がある
こうした特性は、前もって伝えておくと一気に楽になります。
まとめ:完璧を手放すことは、弱さではなく“強さ”
完璧を目指すことが悪いわけではありません。でも 「疲れすぎるほど完璧を求めること」 は、あなたの人生を苦しめます。
障がいがあってもなくても、心や体に負担をかけすぎず、自分のペースで生きるために必要なのは
・70点でOKとする勇気・できない日も自分だと認める柔らかさ・頼るスキルを少しずつ育てる習慣
完璧を手放すことは、あなたの生活を“ちょうどいい心地よさ”へ導く大切な一歩です。
参考リンク
●厚生労働省|発達障害者支援ポータルhttps://hattatsu.go.jp/
●YouTube:精神科医・樺沢紫苑たった一言で「完璧主義」を直す方法https://youtu.be/5B02_XoHJ9E?si=hDc3O83fl9JyWZxI
●YouTube:メンタリストDaiGo「完璧主義を治す方法の切り抜き3選」https://www.youtube.com/watch?v=RApAA7T10qY
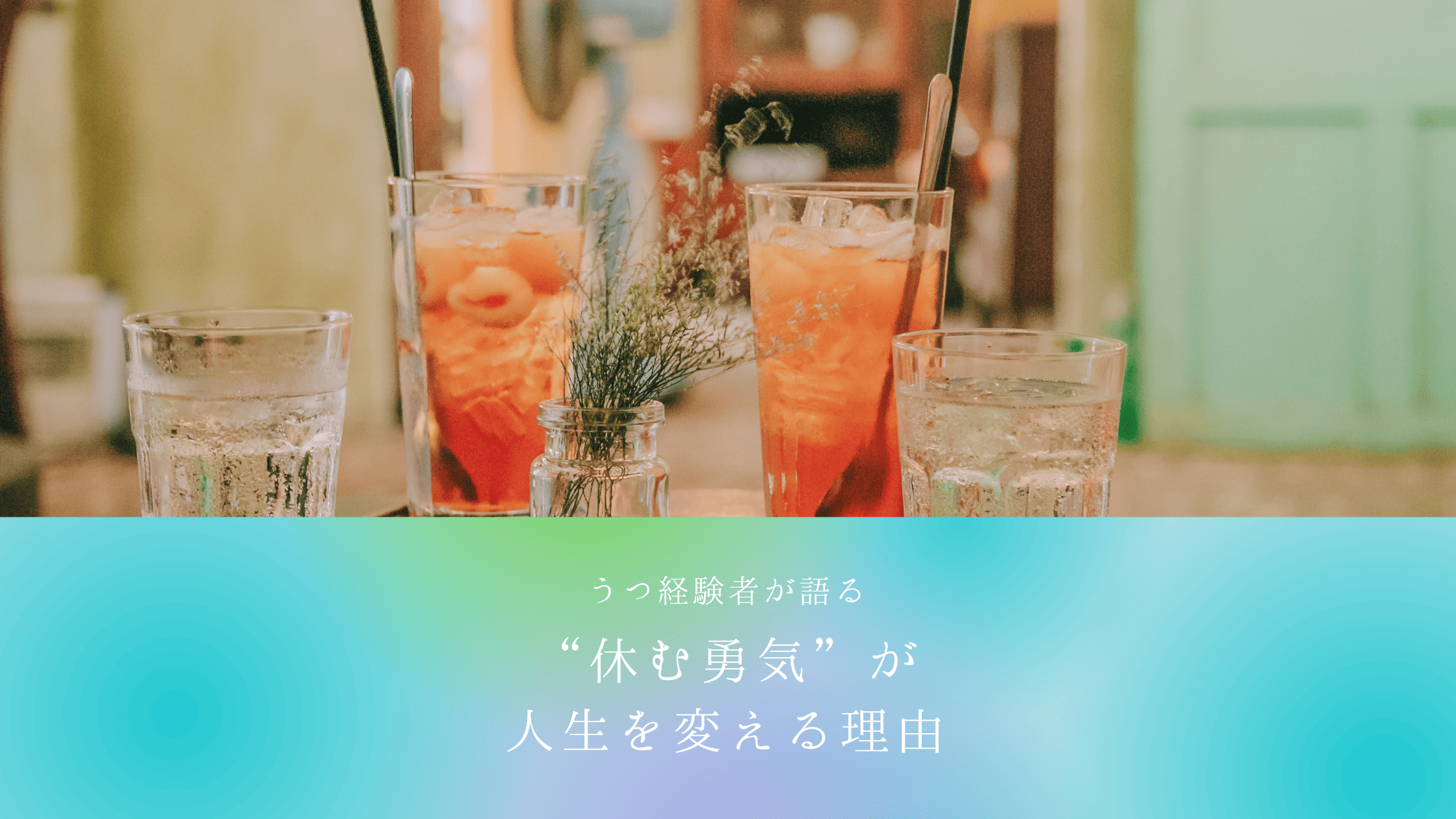
- マインドセット
- 精神障がい
- 発達障がい
【うつ経験者が語る】“休む勇気”が人生を変える理由
「休んだほうがいい」と頭では分かっているのに、いざ休もうとすると胸がざわつき、罪悪感が押し寄せる――。
うつを経験した人の多くが、この矛盾した苦しさに悩みます。私自身も、疲れて動けないのに「休むのは甘えだ」「もっと頑張らないと」と自分を追い詰め続けた結果、心と体が限界に達した経験があります。
同じように考えてしまう方々のために、この記事では・うつ経験者が感じる「休むことの怖さ」・休むことで起きる心身の変化・うつ当事者が実際に使った“休む技術”・家族・職場との向き合い方などを、経験者の視点からわかりやすく解説します。
後半には、信頼できる参考リンクや動画も掲載しました。あなたが安心して「休む」という選択を取れるよう、丁寧に届けたいと思います。
休むことが“怖い”のは、あなたの性格の問題ではない
「休む」と聞くだけで罪悪感が出てくる理由
うつ状態にあると、脳は“危険から身を守るモード”に入り、正常な判断が難しくなります。本当は休んだほうが良いのに、次のような思考が自動的に浮かびやすくなります。
・「私が止まったら周りに迷惑がかかる」・「ここで休んだら何もできない人間になる」・「頑張れない自分が嫌だ」
これは根性や性格の問題ではありません。脳がストレスで疲弊し、“誤作動”を起こしている状態です。
実際、厚生労働省の「こころの耳」でも、うつ症状では「休息が必要」「思考の偏りが起きやすい」と説明されています。
つまり、休むことが怖いのは“あなたが弱いから”ではなく、“脳が疲れ切っているサイン”なのです。
参考リンク:厚生労働省 こころの耳 https://kokoro.mhlw.go.jp/
経験者が語る「限界まで頑張り続けた結果」
私自身、休むことに抵抗があり・職場に迷惑をかけたくない・弱い自分を認めたくない・復帰できなくなったらどうしようという思いから無理を続けました。
しかし、実際は逆でした。
・休まなかったことで集中力がさらに落ちる・小さな作業でもミスが増える・感情のコントロールがきかない・体調が悪化し、立ち上がることすら辛い・結果的にもっと長い休職期間になった
“休む勇気を出せなかったことこそ、回復を遅らせた原因”でした。
「休んだら終わり」ではなく「休むから回復する」
休むことで脳と体が回復するメカニズム
うつになると、自律神経やホルモンバランスが乱れ、脳のパフォーマンスが極端に落ちます。その状態で無理を続けると、回復に何倍もの時間がかかります。
反対に、“適切に休む”ことで次の変化が起こります。
・脳の過活動が落ち着き、思考がクリアになる・感情の波が安定しやすくなる・睡眠の質が上がる・体のだるさが減り、動ける時間が増える・「また頑張りたい」という気持ちが自然に戻ってくる
これは、医学的にも裏付けられています。休むことは“逃げ”ではなく、“治療”なのです。
参考リンク:厚生労働省 こころの耳 うつ病の治療と予後 https://kokoro.mhlw.go.jp/about-depression/ad003/
罪悪感は時間とともに薄れ、できることが増える
休み始めた当初は、正直しんどかったです。「本当にこれでいいのか?」と不安が押し寄せました。
でも、数日〜数週間と休息を続けるうちに、
・朝のしんどさが少しずつ軽くなる・気持ちが沈む日が減る・“できる日”が日単位から週単位に増えていく・小さな達成感を感じられる瞬間が出てくる
と、ゆるやかに前に進めるようになっていきました。
休むことは、人生の“停止”ではなく、次に進むための“助走”です。
経験者が実践した「休む技術」
「休むと決めること」も行動のうち
最初の一歩は、“休むと決めること”でした。
・「今日は何もしない」と宣言する・罪悪感が出たら「今は治療中」と言い聞かせる・1日を“休息のために使う”と意識づける
これは怠けではなく、心のリハビリです。
完全に休む日/少しだけ動く日を分ける
うつの回復期は、波があります。“動ける日”と“動けない日”が交互に来るのは普通です。
私は、次のように分けました。
・何もできない日は「完全休養日」・洗濯物をたたむ、買い物に行くなど軽い行動だけの日は「ゆる動く日」・調子が良い日は散歩や軽い作業を試す
このように“段階をつける”ことで、無理なく活動量を戻せました。
情報を選ぶ:SNSよりも専門サイトを
回復期は不安が強く、ネット検索を繰り返してしまいがちです。しかし、経験談の中には不安を煽る情報もあります。
私は次のように情報源を絞りました。
・「こころの情報サイト」https://kokoro.ncnp.go.jp/・NHKの専門記事や特集・精神科医の動画(YouTubeなど)
特に、精神科医・樺沢紫苑氏の「うつ病をものすごく改善する休息法」動画は大変参考になりました。
https://youtu.be/eRs86ojS7uQ?si=Q5MRd_ENwipEy12R
YouTube:精神科医・樺沢紫苑の樺チャンネルhttps://www.youtube.com/@kabasawa3
家族・職場にどう伝える?経験者のリアルな視点
正直にすべてを話さなくていい
うつを理解してくれる人ばかりではありません。私は当初、職場に状況を丁寧に説明しようとしましたが、返って疲れてしまいました。
伝えるべきは、・今は治療が必要であること・医師の指示に従って休む必要があることこの2つだけで十分です。
詳しい症状や原因を伝える義務はありません。
家族には「どうしてほしいか」を具体的に伝える
家族は助けたい気持ちが強い一方、どう接すれば良いか分からず戸惑うことがあります。
私は・言葉はいらないがそっとしておいてほしい時間がある・相談したい日は自分から話す・責める意図がなくても、アドバイスが苦しく感じる時があるなどを伝えたことで、お互いが楽になりました。
「理解されない経験」も傷として残る
「休むって甘えでしょ」「働けるように努力したら?」と言われたこともあります。
ただ、今振り返れば、“理解されなかったこと=私がおかしいという証拠” ではありません。
理解がないのは、相手の知識不足であり、あなたの価値とは無関係です。
休む勇気が、人生を大きく変える
休んだからこそ得られた「気づき」
休んで初めて、自分がどれほど疲れていたかに気づきました。そして、少しずつ感覚が戻ってくることで、
・「心が楽だ」という感覚・朝の空気が気持ちいいと思える瞬間・ごはんの味が分かる喜び・他人と話すエネルギーが湧いてくる感じ
こうした“小さな回復の兆し”に気づけるようになりました。
休まなければ、何ひとつ取り戻せなかったと思います。
人生の優先順位が変わる
うつを経験した多くの人が口を揃えて言うのは、「働き方や生き方そのものを見直せた」ということです。
私自身も、・人の期待に応えすぎない・完璧を目指さない・疲れたら休む・“無理しない自分”を許すという価値観に変わりました。
結果として、人間関係も仕事の仕方も安定し、以前より生きやすくなりました。
まとめ:休むことは、勇気ある選択
うつ経験者として、強く伝えたいことがあります。
休むことを“諦め”と思わないでほしい。休むことは“治療”であり、“前に進むための準備”です。
そして、「休まなければならないほど頑張ってきたあなたの努力の証拠」です。
どうか、あなた自身を責めないでください。あなたはもう十分すぎるほど頑張ってきました。
今必要なのは、前に進む努力ではなく、“立ち止まる勇気”です。
その勇気が、あなたの人生を変えていきます。

- クリスマス
- イベント
- 身体障がい
手話で楽しむクリスマス — 音だけじゃない“あたたかさ”をみんなで共有するためのアイデアガイド
クリスマスといえば、賛美歌、キャロル、楽しい歌声。けれど、聴覚障がいのある人にとって“音”は必ずしも楽しさのすべてではありません。
代わりに手話があることで、まったく異なるクリスマス体験が生まれます。手話を使って歌ったり、物語を紡いだり、家族や仲間と視覚的・身体的に”贈りもの“のような時間を共有できるのです。
この記事では、手話でクリスマスを楽しむアイデア、歌・ストーリー・交流方法、手話動画の紹介など、実用的かつあたたかいプランをまとめました。
手話でクリスマスソングを楽しむ方法
有名キャロルを手話で歌おう
クリスマスの定番ソングを、手話で歌うことは非常に豊かな体験になります。たとえば「きよしこの夜(Silent Night)」は、ゆったりとしたリズムのため手話で表現しやすく、ジェスチャーを通じて歌詞の意味を深く伝えることが可能です。
参考リンク:Youtube動画
手話歌動画の参考例
日本には、手話でクリスマスソングを演じる動画がいくつかあります。YouTubeでは「手話 クリスマスソング」で検索すると、沢山の動画が出てきます。
歌を通じてのコミュニケーション
歌を手話で共有することで、家族や友人との対話が生まれます。
たとえば、手話で歌ったあとに「どの歌詞が好きか」「手話でどう感じたか」を話し合って、感動を視覚的に分かち合う時間を作るのもおすすめです。
クリスマスストーリーを手話で伝えるアイデア
手話絵本・ジェスチャーストーリー
クリスマスイブや絵本やストーリーを、手話を交えて語る時間を作れます。
手話と同時にジェスチャーや簡単なセット(布、小道具)を使えばより視覚的に魅せることが可能です。
支聴者+聴覚障がいの人
聴こえる人と手話が使える人がペアになってストーリーを語ると、支援と共感の両方が伝わります。
聴こえる人がナレーションを語り、手話側が手話ストーリーを担当するスタイルがオススメです。
https://youtu.be/089oymHkUAY?si=ZEUzESHAdF5EV1sM
物語をみんなで作るワークショップ
参加者全員でオリジナルのクリスマス物語を作るワークショップも楽しいです。
テーマに沿って手話で相談しながら登場人物を決め、ジェスチャーやサイン(手話)で物語を演じてみましょう。
子どもも大人も一緒に参加できる参加型の時間になります。
“見るクリスマス”としての交流アイデア
手話ビンゴ・クイズ
クリスマスにまつわる手話単語(サンタ / 雪 / 星 / トナカイ)を使ったビンゴやクイズを実施。
参加者が手話を使ってマークを指す、答えをサインするなどの工夫で視覚的なゲームができます。
手話を使ったプレゼント交換
「サイン・カード」を用意して、互いにメッセージを書いてプレゼントを交換。渡すときは手話でも気持ちを伝えます。
聴こえる人も手話で気持ちを伝える練習になるうえ、温かな交流が生まれます。
サイレント・サンタセッション
音を使わない“サイレント”なサンタショー。
「サンタから贈り物をもらう」「サンタの動きをマネする」などを通じて、視覚・体感でクリスマスを味わう演出が可能です。
手話を取り入れたクリスマス準備のコツ
環境を整える(光・スペース・視線)
手話を使うには、顔や手の動きがよく見える明るさが重要です。
照明を調整し、手話を交わすスペースを確保しておきましょう。
役割分担を明確にする
手話が得意な人、ストーリーを語る人、小道具を担当する人など、準備段階から役割を分けておくことでスムーズな進行が可能です。
リハーサルをしよう
手話歌やストーリーを本番前にリハーサルすることで、当日の緊張を軽くし、全員が安心して楽しめる時間をつくることができます。
よくある質問とその答え
Q:手話ができない人も参加できますか?A:もちろん参加できます。聴こえる人も手話を学びながら参加することで、より学びのある交流になります。
Q:子どもや高齢者も大丈夫?A:はい。手話は年齢関係なく使える言語です。小さな子ども向けの語りや、高齢者がゆったりと参加する工夫も可能です。
Q:オンラインでも楽しめますか?A:可能です。Zoom や Teams などで「手話歌セッション」「クリスマス手話劇」を企画すれば、遠くにいる人ともクリスマスを共有できます。
まとめ:手話でつながる、クリスマスのあたたかさ
手話を使ったクリスマスは、“音”がなくても“心”や“手”で語り合える温かな時間になります。歌、物語、交流ゲームを通じて、聴覚障がいのある人も聴こえる人も一緒に笑い、一緒に祝える。
音のある世界だけがクリスマスではありません。手話という視覚の言語を通じて、すべての人があたたかなクリスマスを過ごせます。
ぜひ、あなたのクリスマスパーティーに手話を取り入れてみてください。見るクリスマス、触れるクリスマスが、きっと新しい思い出になります。
🔗 参考リンク・動画
「手話 クリスマス」動画:YouTube で「手話 クリスマス」などと検索すると複数見つかります
NPO法人「日本手話通訳士協会」 https://www.jsti.gr.jp/
@Living 聞こえない人と聞こえる人が安心して生きていくために。手話の基礎知識と聴者が知っておくべきこと
大阪市公式ウェブサイト 手話を 学ぼう! 手話で 話そう !