大人のADHDの9割はADHDではない?疑似ADHDがふえている可能性
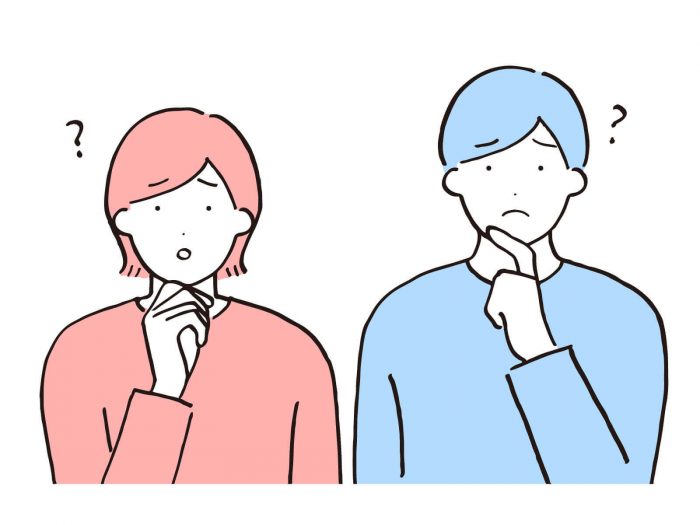
大人のADHDの9割はADHDではない?疑似ADHDがふえている可能性
発達障がいが話題になり、「大人の発達障がい」という言葉も聞かれるようになりました。「発達障がいが急激に増加している」とも、ネット記事などでよく見られるようになりましたね。
しかし、実際はASDやLDなどの発達障がいには増加傾向は見られず、ADHDのみが著しく増加しています。なぜ、ADHDのみが増加しているのでしょうか。原因は、ADHDの診断のむずかしさです。ADHDの診断の危うさや、疑似ADHDについて解説します。
大人のADHDの9割がADHDではない?
「発達障がいは生まれつきであり、治らず、治すものでもない」というのが定説です。また、生まれつきの発達障がいの特性は、12歳までに顕著にあらわれます。
なので、大人の発達障がいは、「子どものときにあった発達障がいが見過ごされ、検査を受けず、そのまま大人になってしまった」と、よく推測されています。
しかし、大人の発達障がいの存在を疑うような研究結果が発表されました。
大人の発達障がいと子どもの発達障がいは同じではないかもしれない
ニュージーランドの南東にある地方都市ダニーデンで、1973年に生まれ、同じ環境で育った子どもたち137人を対象に、子どもたちが0歳から38歳になるまで、追跡調査がおこなわれました。
まず12歳までに発達障がいの診断をし、同じ子どもたちが38歳になったときに、もう一度、発達障がいの診断をした結果が、以下になります。
|
時期 |
発達障がいと診断された人数(137人の内) |
|
12歳までに発達障がいの診断をしたとき |
61人 |
|
38歳で発達障がいの診断をしたとき |
31人 |
発達障がいは生まれつきであり、治るはずがないのに、発達障がいの特性があると診断された数が、半分ほど減少しています。
さらに、38歳で発達障がいと診断された31人のうち、子どもの頃に発達障がいと診断された人の数は「3人」しかいませんでした。
つまり、「年齢が上がると、9割近くが発達障がいではなくなっていた」という結果になります。大人になるにつれ、発達障がいの特性が薄まったのか、ほかの要因があるのか。
ただ、「発達障がいは生まれつきのもので、治らず、治すものでもない」という定説とは違います。子どもの発達障がいと大人の発達障がいは、同じではないかもしれず、「大人の発達障がい」の存在自体も危うくなります。
大人のADHDと子どものADHDに異なる特性が見つかる
同じニュージーランドでの研究結果により、大人のADHDと子どものADHDでは「知能指数」や「知能の特性」に違いが見つかりました。
子どものADHD・・・3歳児の時点で健常児よりも知能指数が低く、字を読むことや実行することに困難が見られる。
子どもの頃にADHDと診断された方は、38歳の時点でも知能指数が健常者よりも低いという結果でした。
けれど、38歳の時点で、生活に支障が出ている度合いは、大人のADHDの方が大きいと報告されています。大人の発達障がい者は知能や実行することに目立った欠陥は見られず、検査では障がいの程度は軽度。けれど、本人が報告する行動上の問題や困りごとは、子どものADHD者よりも深刻でした。
また知能検査の結果では、「知能の特性」に違いがありました。
知能検査WAIS-Ⅲでは、①言語理解②知覚統合③ワーキングメモリー④処理速度の指数を調べられますが、
子どものADHD・・・言語理解・処理速度が最も低い。知覚統合の一部である知覚推理が最も高い。
大人のADHDの方は、子どものときにADHDだと発覚した方と、得意・苦手な能力がまったく逆であることが明らかになりました。同じ発達障がいのはずなのに、なぜ違いが見られるのでしょうか。
子どもの発達障がいが見過ごされて大人になったケースの「大人の発達障がい」はないわけではありません。けれど、いま当たり前に言われているほど多くはない可能性が出てきています。
疑似ADHDとは?
ADHDは誤診が多い。大人のADHDの存在も「急激に増加」といわれるほど、多くはないかもしれない。このようにADHDの診断に危うさがある理由は、疑似ADHDといわれるものが多くあるからです。
疑似ADHDとは、ADHDではないのに、脳の活発部位の偏りがADHDと同じで合ったり、同じ症状が確認されており、ADHDと区別がつきにくい状態を指します。
養育環境により脳は変化する
虐待など、養育環境が合わなかった家庭の子どもの脳と、ADHDの脳の状態は区別がつきにくいといわれており、同じ症状が確認されます。さらに虐待などを受けた子どもの脳は脳機能だけでなく、脳の構造までも変化するので、ADHDなのか、虐待によるものなのか、診断が非常にむずかしくなります。
ADHDの症状があるASD
ADHDと間違われやすいのが、自閉症スペクトラム障がい(ASD)です。ASDの約3割に、ADHDの特性である「多動・不注意」が見られるといわれています。
そしてASDの方がADHDの薬を飲み続けた結果、いつまでも症状が改善しないというケースが多く報告されています。
依存症や心理的外傷など他の要因
子どもはゲームやスマホ依存症、大人はアルコール依存症などで、
・ぼーっとしてしまう
・集中がすぐに途切れる
・もの忘れをしやすい
・物事を順序だてて考えられない
など、ADHDにも見られる症状が確認されます。睡眠不足のときにも見られる症状です。
また心理的外傷を受けたとき、抗不安薬などを飲んだときなども、ADHDに似た症状があらわれます。
疑似ADHDはより重い問題を抱えていることも
疑似ADHDがADHDと診断され、ADHD向けの治療や投薬がおこなわれると、根本的な問題がまったく解決しないまま、長い年月を経てしまうという大きなリスクがあります。
またADHDの薬は、ADHD者だけではなく、健常者でも効きます。「ADHDの薬が効く=ADHDである」の方式は成り立たないところが、また診断をむずかしくしています。
なので、ADHDの薬で症状が改善されたと思いこみ、原因が解決しないまま薬に依存してしまう方もいます。
ADHDの診断時に確認したいこと
多動や不注意による困りごとで診察を受け、質問紙や問診だけでADHDと診断されて薬を処方された場合は、何を根拠にADHDの診断が出たのか確認した方が良いでしょう。
「症状からADHDと診断した」「チェックリストで基準値よりも多い結果が出たから」という理由が返ってきたときは、注意が必要です。
- 発達障がいが生じた時期をいつと認定したのか
- 不安障がいや気分障がい、依存症、ほかの障がいの疑いはないのか
- 注意力、計画力、処理速度、ワーキングメモリーなどの検査結果を確認
12歳までに発達障がいだと断定できる症状が見られていない場合は、大人の発達障がいが疑わしいように、発達障がいではない可能性があります。不安障がいや気分障がい、そのほかの障がいの疑いがないか確認した方が良いでしょう。
また検査結果で、「注意の持続」より「選択的注意」の方が弱い場合は、ASDが疑われます。
ADHDだと早く診断が出た場合は、注意深く確認しましょう。
まとめ
「大人の発達障がい」が注目される裏で、疑似ADHDがふえている可能性があります。
ADHDがさまざまな障がいと症状が似ていたり、養育環境によって脳の構造までも健常者と異なるものへ変わってしまったりするためです。
ADHDではない人がADHD向けの治療や投薬を受け、問題が解決されないまま、薬依存になってしまうと、重い問題を抱えていくことになります。
問診や質問紙だけでADHDと診断された場合は、根拠となるところを聞き、ほかの疑いの障がいはないかを確認したり、検査結果をチェックしたりして説明を受けるようにしましょう。
参考